主体と客体が分離した認識では、認識は世界をつねに直線的に見る。というのも、無限遠点自体が主体の位置になっていることを、主体自身がまだ気づいていないからだ。直線の果てにあるものが何か分からない。この宇宙の果てには何があるのだろう。主体はそうやって、「無限」に想いを馳せるのだ。それが世界を見ている自分自身の位置であるということに気づくこともなく。。
こうして、当然のことながら、主体と客体が分離した世界では、空間も時間も直線的にイメージされることになる。古典物理学の記述様式はこうした認識に素直に従っている。物理学がいう「実在」とは、こうした直線的世界で捉えられる対象のことをいうのであり、それらはすべて計測可能、量的に実数化が可能なものとしてある。
しかし、20世紀になって、ミクロの世界からこうした記述様式には収まらない現象が現れてきた。それが量子の世界だ。まず、この量子の世界には直線がない。量子力学の世界はe^iθという複素平面上の円環によって支配された世界であり、そこに直線は存在していないのだ。物理学はこうした謎めいた円環から、彼らのいう「実在」としての物理量を引き出すために、円環を無理矢理、直線化させる手法を取らざるを得なかった。それが運動量やエネルギーの量子化という手法だ。運動量であれば、∂/∂x、エネルギーであれば∂/∂tを用いて、円環から接線を導出し、無理矢理、直線化させるのだ。
物理学はどうしても、こうした直線化された時間と空間の世界に、存在を見たがる。それが、物理学のいう「実在」なのだから、致し方ないことではあるのだが、直線の世界は、もともと円環の微分化によって出現してきたものだ。量子現象から見れば、物理現象の本質は円環の方にある。なのに、どうしても直線化しないと気が済まない。量子論が分かりにくくなっているのは、物理学が持ったこの実在に対する見誤りにある。
話を元に戻そう。世界を認識しているわたしたち人間の位置は時間と空間の中にはいない。確かに物質的身体は時間と空間の中にあるものだが、認識の当体である精神の位置は時間と空間の外部にある。それが「無限遠点」だ。主体の、この無限遠点への収まりによって、すべての直線は円環化される。そうすると、世界から3次元空間と1次元の時間は消え去る。そして、そこにe^iθという円環が現れてくる。つまり、量子の世界とは、主体が無限遠点として世界の中に入り込むことによって、主客未分離となった世界の数学的形式化になっているのだ。
神秘家や哲学者たちは、この主客未分離の世界について、幾多の言葉を使っていろいろと表現してきた。しかし、それらの言葉は言ってみれば、ムードの言葉であって、それを確かめる自然的根拠に欠けている。でも、いまや、わたしたちは量子論という自然学を手にしている。主客未分離の世界が具体的にどういう生態を持っているかを知りたければ、量子論が展開している素粒子の構造の内部へと、無限遠点を住処とした自らの命を持って侵入していけばいい。そこでは、思考するものと思考されるものの見事な一体化が起きている。理性がイデアに触れる現場がそこにはあるのだ。こうした思考は同時に、デカルトやカント以来、わたしたち人間を支配していた主体性の哲学、認識論を終焉へと導く。
認識論のこの終焉のもとに、世界を対象として眼差すような意識は静かに息を引き取っていくことだろう。認識は世界の根底に存在そのものとなって入り込み、「永遠」としての認識を開始し始めることになる。そのとき、「あるもの」は、すべて「なるもの」へとメタモルフォーゼを起こすのだ。
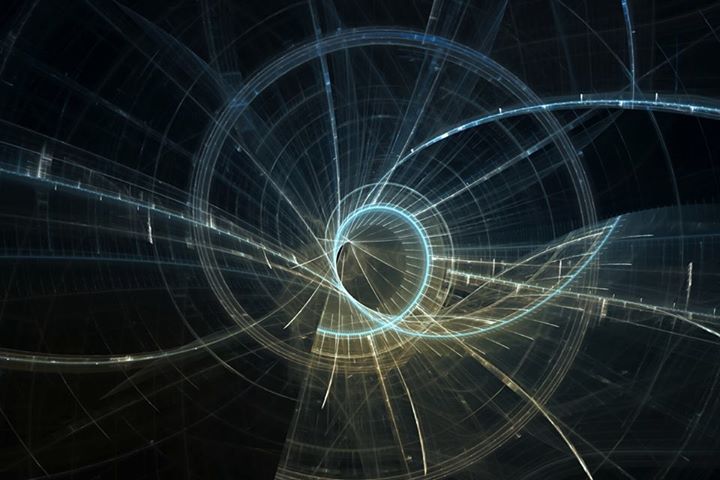







12月 2 2014
量子論は認識論を解体する
主体と客体が分離した認識では、認識は世界をつねに直線的に見る。というのも、無限遠点自体が主体の位置になっていることを、主体自身がまだ気づいていないからだ。直線の果てにあるものが何か分からない。この宇宙の果てには何があるのだろう。主体はそうやって、「無限」に想いを馳せるのだ。それが世界を見ている自分自身の位置であるということに気づくこともなく。。
こうして、当然のことながら、主体と客体が分離した世界では、空間も時間も直線的にイメージされることになる。古典物理学の記述様式はこうした認識に素直に従っている。物理学がいう「実在」とは、こうした直線的世界で捉えられる対象のことをいうのであり、それらはすべて計測可能、量的に実数化が可能なものとしてある。
しかし、20世紀になって、ミクロの世界からこうした記述様式には収まらない現象が現れてきた。それが量子の世界だ。まず、この量子の世界には直線がない。量子力学の世界はe^iθという複素平面上の円環によって支配された世界であり、そこに直線は存在していないのだ。物理学はこうした謎めいた円環から、彼らのいう「実在」としての物理量を引き出すために、円環を無理矢理、直線化させる手法を取らざるを得なかった。それが運動量やエネルギーの量子化という手法だ。運動量であれば、∂/∂x、エネルギーであれば∂/∂tを用いて、円環から接線を導出し、無理矢理、直線化させるのだ。
物理学はどうしても、こうした直線化された時間と空間の世界に、存在を見たがる。それが、物理学のいう「実在」なのだから、致し方ないことではあるのだが、直線の世界は、もともと円環の微分化によって出現してきたものだ。量子現象から見れば、物理現象の本質は円環の方にある。なのに、どうしても直線化しないと気が済まない。量子論が分かりにくくなっているのは、物理学が持ったこの実在に対する見誤りにある。
話を元に戻そう。世界を認識しているわたしたち人間の位置は時間と空間の中にはいない。確かに物質的身体は時間と空間の中にあるものだが、認識の当体である精神の位置は時間と空間の外部にある。それが「無限遠点」だ。主体の、この無限遠点への収まりによって、すべての直線は円環化される。そうすると、世界から3次元空間と1次元の時間は消え去る。そして、そこにe^iθという円環が現れてくる。つまり、量子の世界とは、主体が無限遠点として世界の中に入り込むことによって、主客未分離となった世界の数学的形式化になっているのだ。
神秘家や哲学者たちは、この主客未分離の世界について、幾多の言葉を使っていろいろと表現してきた。しかし、それらの言葉は言ってみれば、ムードの言葉であって、それを確かめる自然的根拠に欠けている。でも、いまや、わたしたちは量子論という自然学を手にしている。主客未分離の世界が具体的にどういう生態を持っているかを知りたければ、量子論が展開している素粒子の構造の内部へと、無限遠点を住処とした自らの命を持って侵入していけばいい。そこでは、思考するものと思考されるものの見事な一体化が起きている。理性がイデアに触れる現場がそこにはあるのだ。こうした思考は同時に、デカルトやカント以来、わたしたち人間を支配していた主体性の哲学、認識論を終焉へと導く。
認識論のこの終焉のもとに、世界を対象として眼差すような意識は静かに息を引き取っていくことだろう。認識は世界の根底に存在そのものとなって入り込み、「永遠」としての認識を開始し始めることになる。そのとき、「あるもの」は、すべて「なるもの」へとメタモルフォーゼを起こすのだ。
By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: 量子論