●生ける光と死せる光
周囲に知覚されている事物をベルクソンのいう「イマージュ」として捉え直し、改めて見つめていると、おのおのの事物がそれ自身の過去を背後にたなびかせながら、それを見ている主体と一緒に存在し続けているような、そんな感覚が芽生えてきます。空間が過去を含み持って厚みを増してくるようなこないような、何やらそんな感じです。
このように、ベルクソンによれば、過去は過ぎ去った現在の知覚などでは決してなく、現在=知覚(ベルクソンは純粋知覚と呼びます)の背後に付き添う記憶とともに存在しつづけているものなのです。ですから、そこで生起している知覚は、もはや以前のような瞬間の切り取りとしての知覚ではなく、数々の記憶に支えられたイマージュとしての知覚でしかあり得ません。このように純粋知覚から記憶へと移行することで、物質という概念を破棄し、精神へと向かうことがベルクソン哲学のまさにキモと言っていいのですが、ここにヌース的な分析を施した場合、こうしたイマージュとしての知覚を一体どこに想定すればよいのか、その場所性が問題になってきます。
ベルクソンは、この問題については直観で捉えるしかなく、空間化された時間のように、持続が根づいている場所を(構造として)幾何学的に表現することは不可能だと言っているのですが、一方で、下図1のような円錐モデルを用いて、持続の具体的な振る舞い方を比喩的に説明してもいます。この円錐はヌースの観点から見てもかなり興味を引くものなので、ちょっと紹介しておきます。
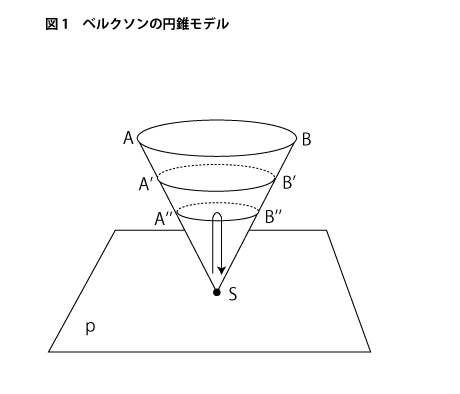
ここに描かれている円錐の全体性SABが記憶に蓄えられたイマージュの全体を意味します。頂点Sが現在、すなわち純粋知覚の場です。ベルクソンによればこれは身体のイマージュです。身体は常に現在とともにあり、僕らの行動の起点となりますが、これは分るように常にingの世界です。ベルクソンは、この現在としての身体と密接に結びついているのが感覚-運動のシステムだとし、その場所を平面Pとして表します。つまり、想起によって引っ張り出されてくる記憶と、運動や行動の習慣化によって獲得されている身体的記憶を区別して考えているわけです。実際に通学路を思い出しながら歩いている人はいませんよね。ベルクソンの言う通り、確かに習慣はつねに現在に根を張っているという言い方ができます。
一方、通常の記憶の場所は円錐SABの様々な断面として表されます。時間の流れは頂点Sが平面Pとつねに接しながら、平面Pを押すように円錐自体を成長させてくのに対応し、新たな過去をA’B’、A”B”というように生産し続けていきます。現在は想起によって記憶を引っぱり出して、そのときどきの精神水準を作り出してくるわけですが、ベルクソンによれば、意識はつねにこの円錐内部を反復しており、その反復によって記憶が現在にもたらされるとしています。つまり、意識は精神の内部において常に現在と過去との間を振動しているというわけです。この振動の状態が「持続」と考えてよいでしょう。
とまぁ、ざっと、ベルクソンの円錐モデルの説明をしましたが、その他、意識状態についてのいろいろなことがこの円錐モデルを通して説明できるのですが、興味がある人はベルクソンの『物質と記憶』を読んで下さい。というところで、話を本題に戻します。こうした持続空間が一体どこにあるのか、という問題です。
気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが、ベルクソンが何気に出してきたこの持続円錐は相対論に登場するミンコフスキーの光円錐ととても似ています。もちろん、光円錐の方は単に時間と空間の関係をその高さと底面の広がりに取って、両者の関係性をあくまでも物理的に把握するために作り出された幾何学的モデルであって、そこにベルクソンが語るような持続の意味づけは一切ありません。しかし、ヌース理論が説く人間の内面、外面という概念を念頭に置いて、この光円錐自体を反転させてみたらどうなるでしょうか(下図2参照)。
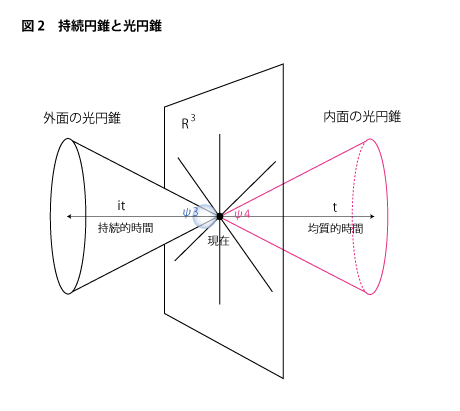
そこには虚時間における光円錐とも呼んでいいものが現れますが、おそらく、この光円錐がベルクソンの持続円錐の意味を持っているのではないかと考えられるのです(ヌース的には円錐というよりも球体となる)。その理由は今までこの拙論でお話してきた下記のような理由からです。
1、人間の外面は知覚そのものが生起している場所であり、数学的には射影空間として考えられること。
2、人間の外面では奥行きという方向性が一点に潰されており、潰された奥行きは光速度状態と称してもいいような過去ー現在を全て含み持った薄膜として視野空間上に存在させられているということ。
3、この薄膜はモノの見えとその背後の空間をすべてを含み持っており、記憶はその薄膜の厚みの中に重層的に存在させられていると考えられること。
4、この記憶の重なりがポンティの言う見るものとしての主体の息づきとして考えられること。
5、この薄膜の厚みは、物理学的には虚時間とよばれる4次元空間の方向の微小長さの軸によって支えられていると考えられること。
こうしたヌース理論の予想が正鵠を得ているのかどうかはまだ分りません。しかし、とりあえずは、目の前のモノから広がっている空間を、4次元の軸(視線)の相互反転関係を用いて人間の外面と内面という二つの領域に分離させ、それぞれに「持続空間」と「均質時空」の意味を付与することは、ベルクソンの主張を簡潔な形で整理する上で極めて有効な手法となります。一方に持続を保持した記憶が活動する分割不能な空間があり(人間の外面)、方や他方に時間の流れにおける現在を一瞬、一瞬の点のように分割し、それらをパラパラめくりの動画のようにして概念化して整理している空間がある(人間の内面)。前者は物質がまさに記憶として存在する、それこそベルクソンが言うところの精神の住処にふさわしい場所となり、後者は僕らにおなじみの時空となります。
こうして物質的身体=主体という人間型ゲシュタルトが提供する頑な意識感覚は弱められ、人間の外面と人間の内面という概念のもと、世界自体が世界自身を主体的側面と客体的側面に「対化」として分離させているというトランスフォーマーが所持する世界概念の基礎を形作ることができてくるわけです。







7月 29 2008
時間と別れるための50の方法(23)
●生ける光と死せる光
周囲に知覚されている事物をベルクソンのいう「イマージュ」として捉え直し、改めて見つめていると、おのおのの事物がそれ自身の過去を背後にたなびかせながら、それを見ている主体と一緒に存在し続けているような、そんな感覚が芽生えてきます。空間が過去を含み持って厚みを増してくるようなこないような、何やらそんな感じです。
このように、ベルクソンによれば、過去は過ぎ去った現在の知覚などでは決してなく、現在=知覚(ベルクソンは純粋知覚と呼びます)の背後に付き添う記憶とともに存在しつづけているものなのです。ですから、そこで生起している知覚は、もはや以前のような瞬間の切り取りとしての知覚ではなく、数々の記憶に支えられたイマージュとしての知覚でしかあり得ません。このように純粋知覚から記憶へと移行することで、物質という概念を破棄し、精神へと向かうことがベルクソン哲学のまさにキモと言っていいのですが、ここにヌース的な分析を施した場合、こうしたイマージュとしての知覚を一体どこに想定すればよいのか、その場所性が問題になってきます。
ベルクソンは、この問題については直観で捉えるしかなく、空間化された時間のように、持続が根づいている場所を(構造として)幾何学的に表現することは不可能だと言っているのですが、一方で、下図1のような円錐モデルを用いて、持続の具体的な振る舞い方を比喩的に説明してもいます。この円錐はヌースの観点から見てもかなり興味を引くものなので、ちょっと紹介しておきます。
ここに描かれている円錐の全体性SABが記憶に蓄えられたイマージュの全体を意味します。頂点Sが現在、すなわち純粋知覚の場です。ベルクソンによればこれは身体のイマージュです。身体は常に現在とともにあり、僕らの行動の起点となりますが、これは分るように常にingの世界です。ベルクソンは、この現在としての身体と密接に結びついているのが感覚-運動のシステムだとし、その場所を平面Pとして表します。つまり、想起によって引っ張り出されてくる記憶と、運動や行動の習慣化によって獲得されている身体的記憶を区別して考えているわけです。実際に通学路を思い出しながら歩いている人はいませんよね。ベルクソンの言う通り、確かに習慣はつねに現在に根を張っているという言い方ができます。
一方、通常の記憶の場所は円錐SABの様々な断面として表されます。時間の流れは頂点Sが平面Pとつねに接しながら、平面Pを押すように円錐自体を成長させてくのに対応し、新たな過去をA’B’、A”B”というように生産し続けていきます。現在は想起によって記憶を引っぱり出して、そのときどきの精神水準を作り出してくるわけですが、ベルクソンによれば、意識はつねにこの円錐内部を反復しており、その反復によって記憶が現在にもたらされるとしています。つまり、意識は精神の内部において常に現在と過去との間を振動しているというわけです。この振動の状態が「持続」と考えてよいでしょう。
とまぁ、ざっと、ベルクソンの円錐モデルの説明をしましたが、その他、意識状態についてのいろいろなことがこの円錐モデルを通して説明できるのですが、興味がある人はベルクソンの『物質と記憶』を読んで下さい。というところで、話を本題に戻します。こうした持続空間が一体どこにあるのか、という問題です。
気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが、ベルクソンが何気に出してきたこの持続円錐は相対論に登場するミンコフスキーの光円錐ととても似ています。もちろん、光円錐の方は単に時間と空間の関係をその高さと底面の広がりに取って、両者の関係性をあくまでも物理的に把握するために作り出された幾何学的モデルであって、そこにベルクソンが語るような持続の意味づけは一切ありません。しかし、ヌース理論が説く人間の内面、外面という概念を念頭に置いて、この光円錐自体を反転させてみたらどうなるでしょうか(下図2参照)。
そこには虚時間における光円錐とも呼んでいいものが現れますが、おそらく、この光円錐がベルクソンの持続円錐の意味を持っているのではないかと考えられるのです(ヌース的には円錐というよりも球体となる)。その理由は今までこの拙論でお話してきた下記のような理由からです。
1、人間の外面は知覚そのものが生起している場所であり、数学的には射影空間として考えられること。
2、人間の外面では奥行きという方向性が一点に潰されており、潰された奥行きは光速度状態と称してもいいような過去ー現在を全て含み持った薄膜として視野空間上に存在させられているということ。
3、この薄膜はモノの見えとその背後の空間をすべてを含み持っており、記憶はその薄膜の厚みの中に重層的に存在させられていると考えられること。
4、この記憶の重なりがポンティの言う見るものとしての主体の息づきとして考えられること。
5、この薄膜の厚みは、物理学的には虚時間とよばれる4次元空間の方向の微小長さの軸によって支えられていると考えられること。
こうしたヌース理論の予想が正鵠を得ているのかどうかはまだ分りません。しかし、とりあえずは、目の前のモノから広がっている空間を、4次元の軸(視線)の相互反転関係を用いて人間の外面と内面という二つの領域に分離させ、それぞれに「持続空間」と「均質時空」の意味を付与することは、ベルクソンの主張を簡潔な形で整理する上で極めて有効な手法となります。一方に持続を保持した記憶が活動する分割不能な空間があり(人間の外面)、方や他方に時間の流れにおける現在を一瞬、一瞬の点のように分割し、それらをパラパラめくりの動画のようにして概念化して整理している空間がある(人間の内面)。前者は物質がまさに記憶として存在する、それこそベルクソンが言うところの精神の住処にふさわしい場所となり、後者は僕らにおなじみの時空となります。
こうして物質的身体=主体という人間型ゲシュタルトが提供する頑な意識感覚は弱められ、人間の外面と人間の内面という概念のもと、世界自体が世界自身を主体的側面と客体的側面に「対化」として分離させているというトランスフォーマーが所持する世界概念の基礎を形作ることができてくるわけです。
By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: イマージュ, ベルクソン, 人間型ゲシュタルト, 内面と外面