1月 13 2007
差異と反復………4
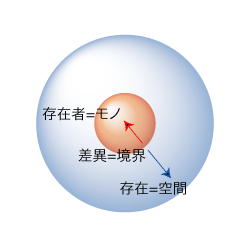 さて、このドゥルーズ哲学のほのかな香りをおかずとして、主食であるヌースの「差異と反復」の話に移ろう。
さて、このドゥルーズ哲学のほのかな香りをおかずとして、主食であるヌースの「差異と反復」の話に移ろう。
存在者と存在との差異。一般には思考不可能とされているこの存在論的差異の道程を何とか思考の対象として描像することができないか、それがヌースの試みだと言っていい。また、その差異の連なりを思考対象としていく知性の在り方自体が、本来、ヌース理論がNOOS(nous=創造的知性)と呼ぶもののことである。この差異を顕在化させていくために、ヌースはおよそ次のようなプロセスのもとに思考を進めて行く。
1、存在と存在者の差異は僕らの認識においてどのような差異として現れてくるのか。
2、1で見出された差異を幾何学的な概念として抽出することはできないか。
3、その抽出された概念を被造物の根源的要素とも言える光子と結びつけることはできないか。
4、そこから、物理学が見出した高次元多様体の形作る内部対称性を差異と反復の拡張システムとして解釈することはできないか。
5、そして、このシステムを構造主義やポスト構造主義が追いかけている無意識構造の在り方と結びつけることはできないか。
とっかかりはこうした順番である。もちろんこの先もまだあるが、とにかく、存在者と存在の間における距離を一つの長大な円環構造と見なし、永遠回帰が辿る一つの循環路の在り方を白日のもとに晒そうとする試みがヌース理論だと思ってもらえばいい。それは言い換えれば、僕らが所持している意識のすべての中を自意識的に辿っていくということでもある。これらすべての項目についてダイジェストするのはちょっと大変なので、ここでは1〜3までのごくかいつまんだあらましを紹介しておこう。
1、存在と存在者の差異は僕らの認識においてどのような差異として現れてくるのか。
世界が極限的な差異において「2なるもの=対化」として存在と存在者の関係を作り出しているのだとすれば、すべてが逆さまに映されている現象側にはその差異は始源における「2なるもの=対化」として現れているはずである(ドゥルーズは本性の差異は延長の中で量や質として逆さまに映されるという)。この原初の差異の中へと侵入できなければ極限の差異へと向かう通路は永遠に見えることはない。
そこで、ヌースはこう考える。被造物における原初の「2=対化」を単純にモノと空間のことと考えてはどうか、ということである(左上図参照)。つまり、存在-存在者の関係は被造物の世界においては空間とモノの関係として姿を表しているのではないか、ということだ。実際、空間はすべての存在者の母胎となるものだが、空間自体は存在者とは呼びにくい。空間はモノによってのみ、その存在を不在として露にし、文字通り、現象世界全体を出現させるための一者的同一性として振る舞っている。そう考えれば、存在そのものの臨在として空間ほどその名に似つかわしいものはない。(もちろん、モノ=物質と見るならば、そこには気体や液体の状態もあるわけで、確固としたかさばりのモノとは少し異なるものとなる。液体や気体の本性についてはヌースでは別枠できっちりと説明していくことになる。)
認知心理学でいう「地(フィギア)」と「図(グラウンド)」の関係に明らかなように、モノは空間なしでは認識に浮上することはないだろうし、空間もまたモノなしでは認識に昇ってくることはない。そして、このような二項対立の図式に常に付きまとっているのが「同一性」というものである。この場合で言えば、空間はあくまで空間であって、モノはあくまでモノであるという大前提がそれだ。空間とモノが互いの存在証明のために相補的な関係として現出しているとするならば、対象認識は認識の矢が空間とモノの間を行ったり来たりし、互いを反照し合うことによってそれぞれの同一性を保証し合うことによって成り立っているということになる。つまり、存在と存在者の間にある存在論的差異は、僕らの認識の中ではまずもってモノと空間それぞれの同一性を保証し、それら両者間の反復として姿を表しているということなのである。そこで、次のことが問題となってくる——ではそれら両者の差異とは一体何なのか?言ってみれば、ここが始源から放たれる第一の差異の入り口となるわけだ。
認識におけるモノと空間の間の反復は当然のことながら差異が存在するから起こる。しかし、その差異とは一体何のだろうか?空間とモノの場合であれば、その差異は両者の境界、つまり、界面にあるのではないかという直感が誰にでも働くことだろう。この界面は言い換えれば、〈内部/外部〉境界を形作っているものだ。しかし、界面を物質=存在者のイメージで追求していったとしても、それは曖昧模糊とした量子レベルの確率存在の中にとけ込んでいくだけで、確固とした差異面が認識に浮上してくることはない。第一、空間とモノとの差異について思考する限り、その差異がモノとして表されるはずもないだろう。対象認識とは人間が持った概念の問題であって、物質的な表象レベルの問題などではないからだ。つまり、実体としてモノと空間の差異があるというより、観念が概念を用いてモノと空間を区別するような象りを与えているということなのである。ここから思考が持つ眼差しはその対象を〈物質的なもの〉から〈量子的なもの〉へと方向を転換することになる。つづく。







2007年1月14日 @ 11:24
存在と存在者の差異って何でしょうね。ソフトウェア工学のオブジェクト指向、さらに進んでエージェント指向は、そうした哲学的な考え方を、技術的に取り込んでいったものではないかと、私は思います。オブジェクト指向で言う「オブジェクト」とは、いわゆる「モノ」と「ふるまい」を併せ持ったものです。エージェント指向では、そうしたオブジェクトにその「ふるまい」をさせる要件を自ら取りに行くようなものをエージェントと呼んでいます。生物の場合、存在と存在者の関係は、むしろ、このエージェント指向の考え方に近いように思います。
ヌースで言っていることが、私たちふつうの学校教育を受けた者として、一見バラバラに見えて難しく感じるのは、例えば、ひとつ前の次元で、M1,M2,M3,M4が次元の基底(単位)だったものが、次の次元では、N1=f(M2),N2=f(M1),N3=f(M3),N4=(M4)、さらにN5が付加されている、といった感じで、前次元の順序が組み替えられ、さらに新しい次元の基底が加えられるといった類の考え方だからかもしれません。そういう観点から眺めると、今見えている観点における要素を、そのまま延長して次の次元の要素と考えることは意味をなさないわけです。「認識」というものも、おそらくそのようなもので、私たちは「認識」した後の「認識結果」、いや「認識結果」の表現だけを眺めているわけです。ところがすべてが終わった後では、私たちの意識はその「認識結果」側、いや「認識結果」の表現側に貼り付けられてしまっています。
レヴィ=ストロースは、『親族の基本構造』の中で、ブルバキの数学者アンドレ=ヴェイユとともに、人類学に群論を具体的に持ち込んでいます。部族におけるグループ間の婚姻という問題について、群論における「積」として、性別の違いによる婚姻の型の振り分けという「関数」の合成を与えています。これがある意味画期的だったのは、関数が変換する対象が「部族のグループ」ではなく、「婚姻という関係」の方だったことです。
したがって、以降レヴィ=ストロースの考え方をベースに発展していった「構造主義」哲学における「構造」とは、集合の要素ではなく要素間の「関係」で構成されるものを指すようになったと思います。私たちは、具体的実体としての「部族」の方には意識がすぐ向きますが、背後の関係としての「婚姻パターン」の方はなかなか「見えて」きません。「部族」という「存在者」は、「婚姻」によって「存在」付けられているとも言えます。そして、その本来見えなかった「婚姻」を「存在物」として扱ったとき、さらにその背後で、「婚姻」を「存在」づけているものが見えてくるように思います。こうした存在-存在者のシフトの連鎖から、次々により上位の存在側へと逃れていくものこそが「差異」なのではないかと思います。
2007年1月15日 @ 02:01
>永遠回帰が辿る一つの循環路の在り方を白日のもとに晒そうとする試みがヌース理論だと思ってもらえばいい。
反証可能性がないものは理論ではありません。
それはコウセン説に過ぎません。
理論を名乗るのであれば、いい加減、反証可能性を示してください。
またOCOTに聞いただけのことを自分のアイデアだとは思わないように。
キミ以外にOCOTから聞いた者はいくらでもいるでしょう。