2月 12 2007
トツカノツルギ
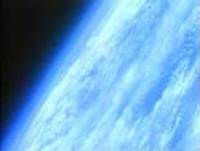
さて、前回は、若干、オチャラケ気味で「上と下」の導入を書いたが、「上と下」について、ヌースの話をマジモードで始めるとちょっと大変になる。それは地球の自転や月の公転や、太陽やその他の諸惑星、さらには銀河、銀河団などについて、いろいろと話していく必要があるからだ。「回転とは等化」というヌースの鉄則がある。諸惑星たちは単にビックバンの残響力でいたずらに回っているわけではない。そこには「次元等化」という大事な働きが潜んでいるのである。ただ、それらについてはまだよくまとまっていないので、またのお楽しみとしておこう。とりあえず、ここでは地球表面が5次元球面であるということについて、少し補足して話を終わらせたいと思う。
2月8日の書き込みで僕は次のように書いた。
>ヌース理論が語る元素とは、物質の構造ではなく精神の構造である。ヌース理論の文脈では、元素は人間の外面の意識構造(潜在化した無意識構造)であった素粒子構造が、(描像可能な)対象として顕在化を起こした際のその認識の在り方そのものとして解釈される。
ここでいう精神の構造とはヌース理論が語るイデアのことである。イデアとはそれを思考することがそのまま物質の創造となるような観念のことだ。このイデアは、当然のことながら、ロゴス(通常の理性)では把握することはできない。ロゴスは被造物に関する知のみを対象とし、それは、いうなれば分断知である。ギリシア哲学の伝統においては、イデアを対象と見なす知性がヌース(nous)とされる。だから、「ヌース」理論は当然のことながら、科学的ロゴスが物質の中に見い出してきた種々の被造物の構造を、創造者が用いた創造的思考(nous)の形跡へと逆変換していくことになる。トランスフォーマー型ゲシュタルトがその眼差しのもとに顕在化させた5次元球面が地球表面のカタチに一致したとすれば、そこで思考された5次元球面はイデアの範疇であるがゆえに、そのまま地球表面を覆う何らかの物質として出現していなければならない。それは何か——。
もうお分かりだろう。それが大気圏である。その組成は科学的知見によればN2(窒素)とO2(酸素)とされている。つまり、端的に言えば、トランスフォーマーが次元観察子ψ7〜ψ8、ψ*7〜ψ8という次元観察子を潜在的なものの状態から顕在化させ、それが5次元球面のカタチであるということがはっきりと認識されたならば、彼らがその時点で所持している幾何学認識(カタチ)は、そのまま大気圏に変身しているということなのである。すなわち、大気圏とは5次元球面が見えている状態そのもののことを指すということだ。
要は、僕らは単に生理化学的な意味だけではなく、意識的にも大気圏とともに生きてい「た」わけである。その意味で身体を中心とする空間は地球精神が持った空間と言い換えることもできるだろう(ヌースでは「反核質」といいます)。だから、地球を起点とした宇宙空間について思考を巡らすときは、必ず身体とともにある思考を行なわなければ何の意味もない。身体抜きでは今の科学的宇宙論が展開しているような「地球は約46億年前にドロドロの溶岩の固まりから生まれました」的な全く奇妙な話にしかならないのだ。
さぁ、僕らは言うなれば地球にばらまかれた無数の十字架である。この十字架を旋回させてみよう。そうすると、そこには天とを結ぶ無数の光の線が生まれる。この一本一本の光線は僕らが「星の光」と呼んでいるものだ。はるか銀河と地球はこの光線によって螺旋状のへその緒のように結ばれている。十字の柄(つか)の先に延びた光の剣(つるぎ)。大地に深く突き刺されたこの聖剣(エクスカリバー)を抜き取るためには、僕らは太陽系が何かを知らなければならない。
銀盤に輝く月を眺めてみよう。何でそれは回っている?太陽の目映い輝きに見入ってみよう。やつは一体何をやってる?諸惑星たちが奏でる天球の音楽に耳を傾けてみよう。やつらはなぜ仲良く黄道面に並んでる?そこには、みんなそれなりの理由がある。20段存在するイデアの階段を昇ったとき、僕らはその理由の半分を知ることができるだろう。
ちょっとファンタジーSF的に進め過ぎか? まぁ、エンターテインメントなのだから、いいか。







2月 20 2008
メルカバー雑感
ヤハウエは眠っているときは一神だが、創造を再開するときは二神になる——これクリエーションに当たっての大事な原則。でないと鏡による再帰的な次元上昇のループが作れないから。だから、『生命の樹』における左右の柱も本当は双対になって四本になっていないといけない。それぞれの双対関係がキアスムを作るとき、中央の柱に沿って螺旋上昇のエネルギー(カドケウスに巻き付いた二匹の蛇=次元上昇していくヌースの対化)が供給されてくることになる。このエネルギーを次々と連結していくときに、そのポイントポイントで歯車のような役割を果たすのが「メルカバー」だ。メルカバーは普通は「神の戦車」と訳されているけど、こやつが生まれてくるときは赤ん坊なのだから、「神の乳母車」と言い換えた方が優しくていいと思うな。ヌース理論がいうところの例の4位一体、ペンターブ的構造だ。金剛界マンダラやホピ族の紋章にもあるあのサイコロの「五」の目のような絵柄が意味しているものだね。あっ、そう言えば、薩摩藩の家紋でもある○に十もその類いでごわす。
「5」はヌースでは差異化を行なうための回転の象徴数。もちろん、無限との連結という意味で、これはペンタグラムや正五角形とも深く関係している。ドゴン神話にも「フォニオ」というのがあって、これが円に十字のカタチを持っていて、神話の中ではアカシアから生まれた創造の種子とされている。僕ら日本人におなじみの寺院のマークの「卍」も同じ力の別の表し方だ。もちろん、これが逆回転してしまうと、ハイル、ヒットラー!!になってしまう。こわ。
メルカバーのカタチはスピリチュアルの世界では「マカバ」でおなじみだよね。それは3次元立体としては双対のカップリングした正四面体(上図参照)として表すけど、ヌース理論でもカタチは全く同じ。意識が通過していくためのヘクサグラムの無限回廊を作り出していくための回転だ。つまり、光の通り道だね。ただし、ヌース理論ではあのカタチを3次元立体としてみもないし、オカルティックな象徴としても見ない。今度の『アドバンスト・エディション』でも書いたけど、おかたく数学的に言えば、4次元空間と4次元時空が重なり合った「等角写像」として見てる。簡単に言えば、4次元構造の3次元世界への影だ。
双対の正四面体として合体しているのはヌースでいう「止核精神の対化」というやつで、これが4次元軸を持って回転していれば、双対時空のことを意味している。つまり、これら2つの正四面体の回転とは君と僕が意識している時空そのもののことを表しているわけだ。今度の本で書いた次元観察子ψ6〜ψ*6に当たるものだね。この『アドバンスト・エディション』ではそれら両者を君と僕それぞれの「想像的自我」と呼んだ。つまり、君が普通に、「あなたとわたし」って呼んでいるもののことだ。ヌースから見ると、時空という概念は実は自我と同じものなんだ。意識と空間構造は決して切り離して考えることができない——これがヌースの面白いところだね。
つまり、時空概念で意識が支配されているうちは、君は自我を決して消滅させることはできないってこと。まぁ、消滅させる必要もないんだけど。。。で、この自我として働いている正四面体の回転軸をうまく相手側と交換できると、あ〜ら不思議、4次元時空が4次元空間に早変わり、あっと言う間にミクロの創造空間側に反転しちゃたみ〜。これがヌースでいう「位置の等化」という作業になる。ψ5の顕在化だ。
これは何を言ってるのかと言うと、相手の目に映る自分を自分と思うんじゃなくって(これは「後ろ」を見てることと同じこと)、自分自身の目に映っている世界の方、つまり「前」を自分と思え!!ってことなんだ。その世界の方がほんとうの「現実」であって、相手の眼差しによって支えられている自分の方は水の中の幻影のようなものだそぉ〜て言ってる。そのへんの意識の行き来をやっているところが、実は物理学が「弱い相互作用」と呼んでいるものの本質。わぁっ、砂子さんもびっくり。だから、砂子さんはヌース的方向で物理のことを考えている。つまりヌースから見ると物質の根底は僕らの魂とつながっているってことなんだ。魂を語る者は、魂ではなく、物質を語れ。『シリウス革命』でも書いたように、あがなわれるべきは魂ではなく、物質なんだ。物質に僕たちのスピリットを注ぎ込んで行かなくちゃいけない。その奇跡的な出来事のことをクリスチャンたちは「ペンテコスタ(聖霊降臨)」と呼んできたんだね。だから、スピリチュアルな人も思考は苦手と言う前に、物質のことをもっと考えて欲しい。わたし待つわ。いつまでも待つわ〜♪って物質が歌ってるよ。
「人神」オリジナル版の表紙に書いてあった「シリウスの力が今、地上に降臨する」ってのは、人間の意識が物質の内部に分け入って、そこから、物質が創造されたルートを再度、辿って行くことなんだよね。それがヌースがいう「アセンション」の本質だと思ってね。フォトンベルトとか、銀河系とか聞いて、遠い空の彼方を見てはダメ。銀河も太陽系も素粒子も、その本質はすべてこの地上に「見えないもの」として全部重なっているんだよ。つまり、人間が生きているこの場所こそが全宇宙ってこと。
By kohsen • 01_ヌーソロジー • 6 • Tags: アセンション, シリウス革命, メルカバー, 人類が神を見る日, 位置の等化, 生命の樹, 素粒子