9月 27 2012
紀要論考の公開
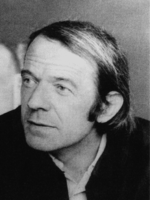 昨年度、大学へ提出した紀要論考。紀要が発刊になったので、この場を借りて公開しておきます。ドゥルーズ哲学の照準に重ね合わせて、ヌーソロジーのたくらみをひっそりと忍ばせております。題して『21世紀はドゥルーズの世紀になるか』。
昨年度、大学へ提出した紀要論考。紀要が発刊になったので、この場を借りて公開しておきます。ドゥルーズ哲学の照準に重ね合わせて、ヌーソロジーのたくらみをひっそりと忍ばせております。題して『21世紀はドゥルーズの世紀になるか』。
21世紀はドゥルーズの世紀になるか
SAF 半田広宣
1.オイディプス的構造を乗り越えるために
「いつの日か世紀はドゥルーズ(Gilles Deleuze)のものとなるだろう」とフーコー(Michel Foucault)が予言して、はや数十年の月日が流れた。この間、現代哲学の主流はフランスのポスト構造主義から英米を中心とした分析哲学へと移行し、ドゥルーズの弁を借りるなら哲学はまさに哲学内部から出現した哲学の暗殺者によって殲滅の危機に瀕していると言える。ドゥルーズにとって分析哲学は科学の範疇に属するものにすぎず、またそれが科学である限り思考をオイディプス化に導くものであり、生命の力を衰退させる否定的な力の側に与しているのである。こうした現代哲学の窮状を見れば、フーコーの予言にあるドゥルーズのものとなるはずの「世紀」がもはや20世紀でなかったことは明らかだが、翻ってこの21世紀は果たしてドゥルーズのものとなるのであろうか。「哲学とは概念を創造することである」とドゥルーズはつねに言い続けてきた。概念とは一般に事物が思考によって捉えられ、かつ表現される時の思考内容や表象、またその言語表現の意味内容のことをいう。ドゥルーズ自身、表象=再現前化を一貫して批判し続けた哲学者だったことを考えれば、彼が論じる「概念の創造」における概念という言葉が持つ意味は一般に使用されるそれとは全く違うものであることは容易に想像できる。2011年に生起した「3.11」という出来事以降、生命の力に対する迫害や抑圧を国家と個の間におけるダブルバインドというかたちでより一層リアルに感じるようになったわれわれ日本人にとって、ドゥルーズの言う「概念の創造」はこのダブルバインドを人間にもたらしているオイディプス的構造を乗り越えるための唯一の方法であると筆者は感じている。その意味でもドゥルーズが彼の哲学において一体何を企図していたのか今一度真摯に検討を加えてみる必要があるだろう。この小文ではドゥルーズの絶筆となった小論のタイトルともなっている『現働的なものと潜在的なもの』をキータームとしてドゥルーズ哲学のエッセンスとその思考のベクトルが秘めた可能性(ドゥルーズならばそれこそ潜在性と呼ぶだろうが)を探ってみたい。
2.現働的なものと潜在的なもの
『現働的なものと潜在的なもの』はクレール・パルネ(Claire Parnet)との共著である『対話』の中の巻末付録として設けられたわずか7ページほどの短い論考である。ドゥルーズ哲学の最も基底的な骨格とされる「現働的なもの」と「潜在的なもの」という二つの概念がそのままタイトルに付されたこの論考がドゥルーズの遺稿となったことは決して偶然ではないように思われる。周知のようにドゥルーズの思考の足跡は大きく四つの時期に区分することができる。まずは思想史家としてヒューム、ベルクソン、ニーチェ等の研究をスタートさせ、第二期はそれらの研究成果を『意味の論理学』『差異と反復』といった主著の中でドゥルーズ独自の理念論として発表する。第三期になると一転、精神分析家のフェリックス・ガタリと共同して『アンチ・オイディプス』や『千のプラトー』を著し、自らの理念論をより実践的な思想とするために社会学的、政治学的な分野へとその応用可能性を論じていく。第四期は打って変わって知覚論や感性論へと分け入り、『感覚の論理』『シネマ』等の極めて深遠なドゥルーズ的芸術論を繰り広げる。『現働的なものと潜在的なもの』はこうした思考の遍歴を経た後に自らの思想の一つの総括のようにしてしたためられた。元来、「現働的なもの」と「潜在的なもの」という対比概念は『差異と反復』の第二章「それ自身へ向かう反復」で示されたドゥルーズの時間論にその多くを負っている。ここではその詳細を語る余裕がないので別の観点からの説明に止めざるを得ないが、「潜在的なもの」とはドゥルーズが考える理念の様態のことであり、「現働的なもの」とは潜在的なものが諸々の種や対象として現象の中にあらわれ出たもののことをいう。通常、この現働的なものと潜在的なものはドゥルーズ哲学を支える二元的要素に見られがちなのだが、しかし、これら両者は決してプラトンのイデアと仮象のような短絡的な二項関係を意味するものではない。ドゥルーズが展開する生成の地理学においては、この両者は互いが互いを包含するような形で、ある二つの仕方において一つの回路を形成している。それはドゥルーズに言わせれば「ある場合には、潜在的なものが現動化されるような巨大回路の中で、現働的なものが[自ら]とは別のものとしての潜在的なものに向かうという仕方で、ある場合には、潜在的なものが現動的なものと結晶化するような最小回路の中で、現働的なものが自分自身の潜在的なものとしての潜在的なものに向かうという仕方」(1)においてである。ここで巨大回路と最小回路という明瞭な対比で言及されているように、ドゥルーズによれば、生成は現働的なものと潜在的なものとのカップリングによって絶えず変動を起こしていく〈時-空間〉的力動であるのだが、このカップリングの仕方には大きく分けて二つの類型があるのである。それは単純明快に言えば力が大きく開いて生成を産出する場合と、力が小さく閉じて生成を産出する場合の二通りの仕方と言っていいだろう。力が大きく開いて働く場合は潜在的な諸力が浮上し、現働的なものとして作用していた諸力はあくまでもその補完部分の中に取り込まれる。反対に、力が小さく閉じて働く場合には現働的なものが自らの中に潜在的なものを押さえ込み、潜在的なものを表象=再現前化の再帰的円環の中に閉じ込めてしまう。ドゥルーズ哲学に敢えて二元論的要素を見て取ろうとするならば、このような二通りの生成の回路の在り方がそれに相当すると考えなければならない。これら二つの生成の回路は『意味の論理学』で論じられたところのクロノス的時間における生成とアイオーン的時間における生成とも言えるだろうし、スピノザ(Baruch De Spinoza)に即して言えば、順に能産的自然と所産的自然と呼ばれるものに相当するだろう。
このような新しい二元論的図式の構想はドゥルーズの中ではすでに『ニーチェと哲学』において用意されていたと考えてよい。なぜなら、この二元性はニーチェ(Friedrich Nietzsche)が能動的な生成と反動的な生成と呼ぶものにほかならないからである。ドゥルーズがニーチェの哲学の中に見たのは、これら二つの回路の切り換えを決行する蝶番とも言える「根源」の到来についての思考であった。この「根源」の到来は周知の通り「存在するものすべての最高の形相」(2)であるところの永遠回帰と呼ばれているもののことである。ドゥルーズはいう。「根源には、能動的な力と反動的的な力との差異が存在する。能動と反動は継起的な関係にあるのではなく、根源そのものにおける共存関係のうちにある」(3)のであり、「反動的な力の側からみると、差異的な系譜学的境位は逆さまに現れる」(4)と。そして、ここで逆さまに現れる差異的な系譜学的境位こそが、潜在的なものを最小の回路の中に閉じ込めている現働的なものが主導権を握ったわれわれ人間=自我という反動的生成の場なのである。つまり、根源には根源の転倒した「人間」という像が常につき纏っているのだ。ドゥルーズが絶えず哲学に「概念の創造」を要求するのもこのニーチェ的な「根源」としての永遠回帰の場所性を念頭においての問題提起だと考える必要があるだろう。となれば、「概念の創造」とはニーチェのいうところの「力への意思」の言い換えでもあり、発生論的な境位における諸力の総合の原理たる理念の創造のことだと言っても過言ではない。事実、ドゥルーズは『差異と反復』において諸力の総合の原理をそのままドゥルーズなりの超越論的構成の原理と重複させて論を進めていく。現働的なものが支配する超越的な場の中で「思う我」と「ある我」との両極の間でひび割れていたデカルト的コギトはニーチェのいう「価値評価する視点の転倒」を導入することによって、〈現働的なもの/潜在的なもの〉がただ反復するようなクロノス的円環に捻りを入れ、このひび割れを修復するような超越論的運動に入るということである。この新たな境位において主体は今まで文字通り潜在化していた潜在的なのものを純粋な内在性のうちに自らの本性として発見することになる。潜在的なものが現動的なものの支配下にあるうちは単にベルクソン(Henri Bergson)的な持続としてしか働くことはなく、表象=再現前化の運動の中に絡み取られてしまう。それは「反動的諸力は能動的な力からその一部ないしほぼすべてを抜き去り、そしてそれによって能動的になるのではなく、逆に、能動的な力を反動的諸力と合流させ、新たな意味においてそれ自体反動的となるようにする」(5)からである。ベルクソンが哲学の中に潜在的なものというアイデアを導入したのは大いに評価されるとしても、その潜在的なものの奥行きをベルクソンのようにただ悪戯に拡張していっただけでは、それはクロノス的時間の中で現動的なものに回収されるにすぎず、神秘主義と見紛うような茫洋とした生気論に終始するしかない。ドゥルーズにとってベルクソニズムをより精度の高い生成論に生まれ変わらせるためには、ニーチェという逆光のプリズムを介入させ、潜在的なものの諸力をそのままダイレクトに能産的自然の生成力へと変容させる必要があったのである。ドゥルーズ哲学のキーワードとなる差異と同一性の関係についてもほぼこれと同じことが言える。現働的なものにおいて差異は同一性に従属するものでしかないが、ニーチェ的な存在の転回においては大いなる肯定によって潜在的なものが認識の表面へと出現し、そのために今度は同一性が差異に従属する側に回ることになる。つまり、同一性は差異の系譜学的展開であるところの、「諸差異を他の諸差異に関係させるシステム」(6)によって担保されるものでしかなくなるのである。
3.現代物理学とドゥルーズ的思考
『現働的なものと潜在的なもの』の冒頭において、ドゥルーズは「哲学とは多様体の理論である」(7)ともいう。ドゥルーズによれば潜在的なものも現働的なものもすべてこの多様体の範疇の中に含まれている。哲学が「概念の創造」であり、かつ、それが同時に多様体の理論であるのであれば、哲学とは理念としての多様体を思考によって空間的に創造する営みにほかならない。それは直裁的に言えば、〈時-空間〉的力動の在り方を現働的なものの優位性から潜在的なものの優位性へと転換させ、われわれの時空に対する知覚様式を全く別な様式へと変革していくことに等しい。この変革によって、今まで客観世界に従属して働いていた内在野は主客関係を超越論的に総合した内在平面へと変容を起こし、そこでの概念を理念として機能させることが可能になるのである。しかし、周知のように、あのソーカル事件以降、「多様体」「微分」「特異点」といったドゥルーズが用いる物理数学的概念は科学者たちからは概念の濫用として幾分疎まれがちなものになったことは否定できない。願わくは科学者たちには細かい専門用語の用法ではなく、ドゥルーズの思考の底辺に潜むそのダイナミズムにより注意を払ってほしいものである。量子力学が明らかにするところによれば、物理的な力の成り立ちは位置と運動量や時間とエネルギーの間の正準交換関係における差異に依拠している。このことは本論で紹介した現動的なものと潜在的なものの二通りのカップリングが作る差異によって力の根源の場が生まれるとするドゥルーズの思考と深い関連を示してはいないだろうか。かつ、量子力学から発展した場の量子論では、電磁力や弱い力、強い力における三つの相互作用の統合を高次元の複素多様体における回転対称性の拡張の中に求めているのだが、こうした統一理論の理論的発展の流れは差異の差異化を潜在的なものの進展と見なすドゥルーズの思考線に沿って進んではいないだろうか。さらに言えば、現在、超弦理論よりもより根源的な理論と考えられているM理論に登場する空間の極大領域と極小領域を関係付けるT双対性は、「無限は大と小は同一であることを、そして極限的なものたちは同一であることをも意味している」(8)と断言するドゥルーズの潜在的直観が現働化されたものの表現ではないだろうか。こうした現代物理学が到達した知の状況をも踏まえて、われわれには今、科学的思考の先端と哲学的思考の先端との協同における新しい空間概念の創造が必要なのである。ドゥルーズが長年にわたって温めてきた理念論はそのための高精度な羅針盤として欠かすことのできないものであり、現働的イマージュの中で捕縛された科学的な表象を潜在的イマージュへと一気に変態させる能力を秘めている。科学的諸概念がひとたび潜在的なものをベースとする領域へと価値転換を起こしたときには、現代物理学がいうところの力の超統一場の理論は、文字通り、力の発生論的境位における諸力の総合の原理と有意味な一致を見るに違いない。なぜならば、ドゥルーズが言うように科学的思考はすでに「時間の空虚な形式」としての永遠回帰を経験しているのであり、あとはそこに流れる直線的時間を「永遠に脱中心化されるひとつの円環」(9)へと接続させるイマージュが加わりさえすれば、あの能動的生成の扉が開くことになるからである。そのときわれわれはドゥルーズが言わんとした巨大回路の入口に立つことになるだろう。無論、これはあくまで21世紀がドゥルーズのものになれば、という仮定の話だが。
(1) ジル・ドゥルーズ / クレール・パルネ『対話』(河出書房新社2008年)234頁
(2) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)96頁
(3) ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(国文社1991年)86頁
(4) ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(国文社1991年)86頁
(5) ジル・ドゥルーズ「意味と諸価値」-ドゥルーズ/没後10年、入門のために(河出書房新社)155頁
(6) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)185頁
(7) ジル・ドゥルーズ / クレール・パルネ『対話』(河出書房新社2008年)229頁
(8) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)78頁
(9) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)182頁







4月 25 2013
持続から襞へ—ドゥルーズの空間論の行方
年に一回、大学の方に提出することが義務づけられている紀要用の小論。去年からドゥルーズをテーマに書いている。今年はドゥルーズの空間論についてごく簡単にまとめた。ヌーソロジーが背景にあると、バラバラに分散した様々な哲学者の思考に共通する線が見えて、結構まとめやすい。ここで紹介するドゥルーズの空間論を、〈奥行き〉と〈幅〉という鍵概念を通して現代物理学が展開している量子論的空間(複素空間のシステム)と結びつけその前景化をはかることがヌーソロジーの目指すところである。さて、現行の素っ気ない4次元時空という概念に対して、わたしたちが真に生きる空間をどこまでふくよかにイメージしていくことができるか。。これからです。
持続から襞へ——ドゥルーズの空間論の行方
半田広宣
From Duration to Le Pli——The Future of Deleuze’s theory of space
Kohsen Handa
1.はじめに
ドゥルーズがその中期の主著『差異と反復』(1968年)において示した時間論は周知の通りドゥルーズ存在論の骨格的基盤をなすものである。この時間論はわれわれが経験する時間がどのような条件で意識上に成り立っているのか、その超越論的総合の在り方をベルクソンの哲学やフロイト、メラニー・クラインらの精神分析的知見、さらにはニーチェの永遠回帰の思想を織り交ぜながら、存在論的無意識の深い射程の中で認められたものであり、哲学史上、数ある時間論の中でも最も重厚かつ緻密な考察で満たされている。しかしその一方で、空間論の方はどうかというと、少なくとも『差異と反復』を見る限りにおいては時間論のような体系づけられた展開は見られない。実際、『結論』を含めて全体で6章からなるそのテキストの構成において、第2章の全体がほぼ時間論の詳説に割かれているのに対して、空間に関するまとまった論述は第4章のごく一部分で取り上げられるのみである。もちろん、これはドゥルーズが「空間によってではなく、むしろ時間によって問題を提起し、解決する」(1)というベルクソン哲学の規則を忠実に遵守しているからだとも言えるが、ベルクソンのいう時間は純粋持続のことであるから、そこではもはや時間と空間の区別がつきにくいものになるという事情もあるだろう。結果的にドゥルーズが空間論について細密な考察を行うのはライプニッツ論として著した『襞』(1988年)まで待たねばならないが、そこではベルクソン哲学が示した精神の弛緩と緊張のあらゆる段階がライプニッツのモナドロジーを経由してドゥルーズ独自の空間的な存在様式で表現され、「襞」の空間論として展開されていく。この小論ではドゥルーズがベルクソンから引き継いだ持続の観念がどのようにしてこの「襞」の空間論へと発展していったのか、その道筋を簡単に辿ってみたい。
2.幅と奥行き
ベルクソン哲学を踏襲したドゥルーズにとって「経験が与えるものは、つねに空間と持続が混合したもの」(2)でしかない。本来、外在性の形態としての空間は継起のない外在性を示しているにすぎず、それは〈空間の空虚な形式〉と呼んでよいものである。そのような空間は量的な同質性しか示すことはなく、長さを指し示す物差し同様、段階的な差異しか含まない。時間にしても同じである。外在性の形態としての時間は瞬間の継起でしかないのであるから、それは生まれてはすぐに壊れ去ってゆくものであり、そこに持続がなければ経過する時間という認識自体が生まれることはないだろう。「物質とは記憶である」のみにとどまらず、時空もまた記憶に裏打ちされて初めて意味を持つ存在となるのである。となれば、われわれが時間に直線という空間的表象を浸透させてしまっているのと同様、空間の延長性にもつねに持続が混合させられていると言えよう。混合したものを慎重に区別すること。これもまたベルクソン哲学の規則であった。果たして、ベルクソンが指摘したこのような空間の延長性と持続の混合に対してドゥルーズはどのような区別を持って臨んだのだろうか。
ドゥルーズはそのためにまず空間における奥行きを「深さ」と呼んで、その幅(横や縦)と区別する。本来、持続として作用している時間を空間化させると同時に、空間の延長性に対して時間を浸透させているものの原因をこの〈奥行き=深さ〉の幅化という一般化に見るのである。
「深さが、延長量として捉えられるや、それは、生み出された延長の一部をなし、もはや、他の二つの延長量(縦と横)に対するおのれ自身の異質性を即自的に含むということをやめてしまう」(3)
なぜ〈深さ=奥行き〉が幅と異質なのかと言えば、奥行きには必然的に時間の経過が内在させられており、それは「もっとも遠い過去を、現在と共存している過去として証示する」(4)からにほかならない。奥行きにおいての〈遠さ-近さ〉という距離概念が時間の経過と同じ意味を持つことは容易に理解できるだろう。特殊相対性理論が明らかにした時空概念では百光年先の彼方にある世界は百年前の世界と同じ意味を持つ。普通、われわれは奥行きを幅へと一般化し、時空における延長量として捉えてしまいがちだが、実際の知覚においてはその延長性は一点で同一視されており、いわば「事物なき媒体の厚み」(5)としてしか経験されることはない。この単純な経験的事実は時間についての直線的な把握をたちどころに無効にする。なぜなら、奥行きにおけるこの一点同一視はもはや時空上の延長性の点的な射影といったようなものではなく、意識において時間が把持されている状態そのものの空間的様態として考えられるからである。つまり、奥行きの中には「生ける現在」を構成するための時間の縮約=過去全体が息づいていると考えられるのである。このような奥行きはもはや延長でもないし、現れては次々と消えていく継起的な時間でもないことがすぐに了解されるだろう。それはまさに現在と過去の同時性を達成している純粋持続が息づく場所のようなものへと変貌している。われわれが世界と関わりを持つのは必ずこの〈奥行き=深さ〉を通じてであり、それは「その本質からして延長の知覚に巻き込まれて」(6)おり、「知覚不可能なものでありながら、知覚されることしか可能でないもの」(7)でもあり、他の諸次元を包含する次元として空間ならび時間の延長性の母胎となるものとなる。こうしてドゥルーズにとっては〈深さ=奥行き〉は一方で一般性でもあり、一方では特異性でもあるような「空間の純粋な錯綜体」(8)と化す。表象はこの純粋な錯綜体が持った二つの性格によって「われわれを一気に物質の中に置く知覚の方向」と「われわれを一気に精神の中に置く記憶の方向」(9)の二つの純粋な現存へと振り分けられているのである。言うまでもなく、前者は幅によって一般化された奥行きの中に見られる表象であり、後者は奥行き本来の〈深さ〉の中に見られる表象である。
3.物質の即自へ
このように奥行きと幅との間に絶対的差異を見て取るドゥルーズの空間に対する思考は現象学を理性から知覚の場へと遷移させようと試みたメルロ=ポンティの思考を受け継いでいるとも言える。メルロ=ポンティは一生涯にわたってこの「深さ」としての奥行きのなかに実存を見る思考を継続しつづけ、その晩年に「見る者」である主体もまた奥行きの中に含まれているという結論にたどり着いた。
「見える現在はわたしの視界をさえぎるのであり、言いかえれば、時間と空間が彼方に拡がっていると同時に、それらは見える現在の背後に、奥の方にひそかに存在しているのだ。そんなわけで、見えるものが私を満たし、わたしを占有しうるのは、それを見ている私が無の底からそれを見るのではなく、見えるもののただなかから見ているからであり、見る者としての私もまた見えるものだからほかならない。」(10)
メルロ=ポンティがこのように〈奥行き=深さ〉のなかに主体の可能性を根付かせようとした理由がどこにあったのかと言えば、それはフッサール現象学のような対自の哲学、つまり「意識はつねになにものかについての意識である」とあからさまに言明するような表象の哲学、意識の哲学からの脱却を意図してのことである。ドゥルーズもまた『ベルクソンの哲学』を著した時点ですでに「空間そのものが物のなかに基礎づけられ、物と持続との関係のなかに基礎づけられ、空間もまた絶対に帰属し、その《純粋性》をもたなくてはならない」(11)と考え、主体の同一性を保持する現象学のような哲学の乗り越えを諮っている。奥行きがひとたび〈深さ〉として純粋持続との結合を果たせば、ドゥルーズの思考の文脈から言えば、それは「感性作用を引き起こし、感性自身の限界を定めている」強度の場の出現ということになり、もはや外延量ではなく即自としての内包量へと変質する。こうしてドゥルーズは「深さと強度は存在においては同じものである」(12)と断言し、〈奥行き=深さ〉を潜在性としての差異が息づく内在平面への侵入口として思考するのである。〈奥行き=深さ〉がもし内包量であるとすれば、純粋持続としての主体(それはもはや主体とは呼べないかもしれないが)は物質の内部に入り込んでいると言わねばならない。つまり、ベルクソンが言うように「われわれが対象を知覚するのはわれわれのうちにおいてではなく、対象のうちにおいて」(13)なのである。しかし、〈奥行き=深さ〉のなかに純粋持続を見とったとしても、果たしてそれがいかにして「物のなかに基礎づけられる」というのだろうか。ドゥルーズはこの基礎づけにライプニッツの哲学を接続させるのである。
4.襞化するモナド
前述したように〈奥行き=深さ〉は知覚的事実としてつねに一点で同一視されている。このとき奥行きを構成している線は外延性の中で見れば、物質としての身体の位置と宇宙の果てにある点を結ぶほぼ無限の長さを持つ線としてイメージされることになろう。しかし身体は物質の質点であると同時に物質に対する「観点」でもあることを忘れてはならない。ドゥルーズは『襞』の中でライプニッツの「モナド」を念頭において「観点を占めるもの、観点において射影されるものとは形而上学的な点、つまり魂、あるいは主体である」(14)と言う。ライプニッツにとって「モナド」とはこの形而上学的点としての「単純実体」のことであり、それは「そこ」へと世界が集中していく中心のことを意味している。「ちょうど、中心つまり点はまったく単純なのであるけれども、そこへと集中する線によって作り出される角度は無数にあるようなものである」(15)とライプニッツがいうように、観点は外延性としての奥行きを自らの「点」のなかに取りまとめ、その中心化の位置を保持している。奥行きのこの中心への集中によって身体は単に空間の一点において存在するのではなく、その集中点が上位の点となって「多を含みそれを表現している一、すなわち単純なる実体」としてのモナドとなるのである。ライプニッツに拠れば、モナドは決して世界の多を一の中に表象する機能を持つだけではなく、同時に、このモナドがモナドの複合体として多の中の一の中へと含み込まれる性質を持っている。つまり「一の中の多」は「多の中の一」へと折り返され、それが再び「一の中の多」への自己表出(exprimer)を果たし、そこから再度、表象化(représenter)の次元へと至るのである。こうしたモナドの中心化から脱中心化への折り返しの仕組みをドゥルーズは『差異と反復』の中で〈巻き込み/implication〉と〈繰り広げ/explication〉と呼び、これら両者を潜在性が持つ二つの基本的な存在様式と見なした。これは「持続は一か多か、多であればそれはどのようにしてか」(16)というベルクソンが提示した問題に対するドゥルーズなりの回答でもあるだろう。世界の多を表象した観点としてのモナドは〈奥行き=深さ〉によって微視的領域へと巻き込まれ、そこで脱中心化を果たし他のモナドとの複合的関係に入る(この複合関係を裏支えするものがドゥルーズのいう「構造としての他者」である)。そこからまた幅の方向へと宇宙の隅々にわたって巨視的領域へと繰り広げられることによって、今度は世界を表出する側へとまわる。そしてそこに浮上してくる無数の表象をまた観点としてのモナドが回収し、〈奥行き=深さ〉においてまた巻き込んでいく……。このように、モナド化の原理は〈巻き込み-繰り広げ〉の運動を〈奥行き=深さ〉という差異化の軸と〈幅〉という同一性の軸を通して多重に反復し地層化させていく仕組みを持つことになる。ここにいたってドゥルーズの多様体の哲学、いわゆる「襞」の空間論の基礎的なイマージュが確立されることになるのである。
5.襞の行方
では、こうしてベルクソンの持続論、メルロポンティの奥行き論、そしてライプニッツのモナド論を媒介にして精製されたドゥルーズによる『襞』の理念論は一体どこに向かおうとしているのだろうか。一般に言われているように、そこにドゥルーズの初期研究の対象であったスピノザの「実体における一義性」やニーチェの「永遠回帰」を見ることは確かに容易い。しかし、この問題については、中期の『差異と反復』と後期の『襞』の間にドゥルーズ自身のある種の〈転回〉が見られ、そこに明確な方向性を見て取ることは難しい。たとえば、『差異と反復』で示された強度的なものにおける〈巻き込み-繰り広げ〉の運動は〈差異化=微分化〉〈異化=分化〉を司る意味で差異のシステムの中核を意味するものでもあり、このシステムは同時に現働的な自我の背後で潜在的に働く個体化のシステムとしても解釈されていた。しかし、ガタリとの共同戦線を組んだ『アンチオイディプス』(1972年)や『千のプラトー』(1980年)では、このような個体化を導く発生の議論はほとんど見られなくなる。そこで議論の中心となってくるのは機械状無意識と化して変動しゆく世界-存在史論を軸とした精神分析批判や、言論的-貨幣論的、社会学的-政治学的な議論を通した資本主義批判である。ドゥルーズのこうした実践的思想への転向は活動家でもあるガタリとの共同を考えれば当然のことと言えるが、それによってドゥルーズがベルクソンから継承した「人間的なものと超人間的なものにわれわれを開くこと、人間的条件を超越すること」(17)という哲学が本来持った意味の射程が、極めて見えにくくなっているのもまた事実である。ドゥルーズは遺稿となった『現働的なものと潜在的なもの』(1996年)という小論において、潜在的なものが向かうべき方向性には「潜在的なものが現動化されるような巨大回路」と「潜在的なものが現動的なものと結晶化するような最小回路」(18)という二つの回路が存在すると書き遺している。果たして、このときドゥルーズは自らが描き出したこの存在論無意識の海図の中で自身の思考の現在をどのポジションに置いて見ていたのだろうか。ひょっとすると、この両回路のつなぎ目の捻れに生じた大渦の中に投げ込まれ、自らが現在地不明となってしまったドゥルーズがいるのではなかろうか。もしそうなら、そこで漂流し続けているドゥルーズを哲学の未来が救助することは果たして可能だろうか。おそらく、われわれにはまだその位置さえつかめていないように思える。
〈参考文献〉
(1) ジル・ドゥルーズ(1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 24
(2) ジル・ドゥルーズ(1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 33
(3) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 164
(4) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 165
(5) M・メルロ=ポンティ(2009)『知覚の現象学・2』みすず書房, 93
(6) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 166
(7) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 166
(8) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 163
(9) ジル・ドゥルーズ(1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 18
(10) M・メルロ=ポンティ(1989)『見えるものと見えないもの』みすず書房, 158
(11) ジル・ドゥルーズ (1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 47
(12) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫, 170
(13) アンリ・ベルクソン(2001)『思考と運動・上』第三文明社, 102
(14) ジル・ドゥルーズ(1989)『襞』河出書房新社, 42
(15) 池田善昭(1999)『「モナドロジー」を読む』世界思想社, 29
(16) ジル・ドゥルーズ (1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 82
(17) ジル・ドゥルーズ (1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局, 20
(18) ジル・ドゥルーズ / クレール・パルネ(2008)『対話』河出書房新社, 234〜235
By kohsen • 01_ヌーソロジー, 06_書籍・雑誌, ドゥルーズ関連 • 4 • Tags: アンチ・オイディプス, イマージュ, スピノザ, ドゥルーズ, ニーチェ, フロイト, ベルクソン, メルロ・ポンティ, モナド, ライプニッツ, 奥行き, 特殊相対性理論