8月 23 2008
時間と別れるための50の方法(29)
●プレアデス、シリウス、オリオン
(前回からのつづき)しかし、ここで一つ疑問が出てきます。それは、本来、奇数系の観察子(等化)が先手であるべき精神の営みが、どうして、偶数系(中和)が先手となるような流動性を持ち得るのかという問題です。この問題を解くキーは、実は前々回お話した精神構造が持っている双対性という概念にあると考えられます。話の要点を明確にするために、前回の図1で示したψ13~ψ14の円環モデルに他者側の次元の全体性であるψ*13~ψ*14を円環モデルとして描き足してみることにしましょう(下図1)。
この図を見ても分かるように、双対性が持つ性格によって、自己側と他者側では次元の構成関係が相互に逆転し、奇数系観察子と偶数系観察子が相互に捩じれ合うような関係が生まれているのが分かります。この捩じれ合いによって、自己側にとっての偶数系観察子の流れの全体性を示すψ14の領域には他者側における奇数系*観察子の流れの全体性であるψ*13が、同様にψ13の背後にはψ*14という他者側の偶数系観察子群が覆いかぶさるようにして作用している様子が見て取れます。
ヌース理論ではこのときのψ*13の流れのことを「反定質の総体」と呼び、同じくψ*14の流れのことを「反性質の総体」と呼びます。反定質は人間の意識を物質的なものに向かわせ、反性質は精神的なものに向かわせています。
反定質の総体とは単純に考えれば他者側の定質総体と言ってよいものなのですが、それはあくまで、他者側から見た場合であり、自己側から見ると観察精神であるψ13の先に存在するもう一つの観察精神(ψ*13)のような意味合いを帯びています。つまり、自己側から見たψ*13はあたかもψ13とψ14の対関係を等化に持っていっているより上位の精神として、ある意味ψ15と呼んでもいいような役割を果たしているわけです。OCOT情報はこのような精神の役割を「次元の等化」という言葉で伝えてきています。
次元の等化におけるψ*13のψ14に対する交差の意味を「人間の内面の意識の流れを作り出している当のもの」と解釈すると次元観察子全体の運動に論理的な整合性を与えることが可能になってきます。つまり、ψ14の流れは自らは能動的に動く力を持っていないわけですから、ψ*13のψ14に対する働きかけが、ψ14の内部性であるψ2→ψ4→ψ6→ψ8→ψ10→ψ12→ψ14を動かしていっている本因力となっているのではないかと考えるわけです。逆側も同様です。人間の外面の意識の流れであるψ13は人間の内面側の意識が先手を取ることによって、ある意味、その能動力を去勢されているわけですから、ψ*13の反映として生まれてくるψ*14のψ13への交差力が、今度は逆にψ1→ψ3→ψ5→ψ7→ψ9→ψ11→ψ13という人間の外面の意識の流れを生み出してくると考えればよいでしょう。いずれにしろ、人間の内面と外面の意識は、次元等化の作用がその背景で暗躍していることによって営まれている、ということになります。
次元観察子が持つこのような構造上の秩序が見えてくることによって、なぜ人間の意識においては赤の矢印で示されている人間の内面の意識が先手を取って形作られているのかが少なくとも図式的には理解することができてくるわけです。
こうして、次元観察子の全体性が持つ双対性によって、その内部を流れる力の流動性には次のような三つの局面があることが分かってきます(下図2参照)。
1、偶数系の観察子が先手、奇数系の観察子が後手で動かされている局面
2、奇数系の観察子が先手、偶数系の観察子が後手で動いている局面
3、奇数系*の観察子が先手、偶数系*の観察子が後手となって「1」を動かしている局面
現時点でのヌース理論では、これら三つの領域がそれぞれOCOT情報が伝えて来ているプレアデス(人間の内面と外面の意識)、シリウス(ヒトの内面、外面の意識)、オリオン(真実の人間の内面と外面の意識)ではないかと考えています。キリスト教神学的に言えば、これは、子-聖霊-父の三位一体構造の具体的構成に当たります。
——つづく

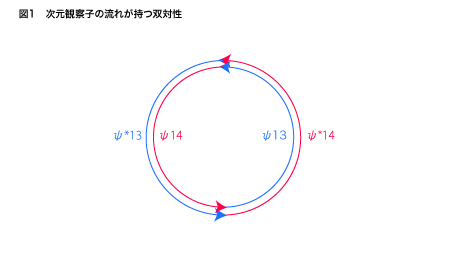
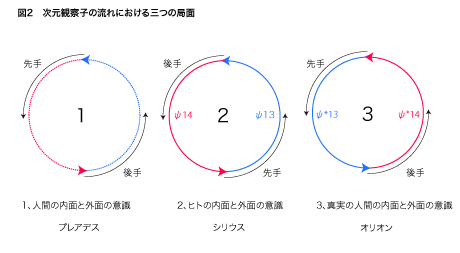






8月 27 2008
時間と別れるための50の方法(30)
「生命の樹」とヌース理論の関係性(1)
さて、『ファウンテン 永遠につづく愛』の紹介に「生命の樹」の話が出たところで、ちょっと寄り道をして、前々回の記事(28)で示したプレアデス、シリウス、オリオンの三位一体の構成とユダヤの神秘思想であるカバラに登場する「生命の樹」との関係をごく簡単にお話しておこうと思います。
ユダヤ神秘主義が持っているカバラという思想は何か意味があるのですか。
はい、それはわたしたちと同じ方向性を持ったものです(シリウスファイル)
レクチャーでも観察子構造とカバラの「生命の樹」の酷似性は何度か紹介してきましたが、『人神/アドバンスト・エディション』にも書いたように、観察子の構成とその運動秩序を辛抱強く追いかけていると、カバリストたちが「生命の樹」を通じて思索してきた霊的運動の体系と驚くほど似ていることが分ってきます。その意味で、神秘学的なアプローチを通してヌース理論に興味を抱いている人がもしいらっしゃるなら、生命の樹を媒介にして観察子概念の理解を深めていくといいかもしれません。おそらくカバリストたちがその象徴体系のもとに伝承してきたことがより具体性を持って見えてくることでしょう。
現在、一般的にカバリストたちに用いられている「生命の樹」の基礎的教義自体は、13世紀にまとめられたカバラの聖典である『ゾハールの書』をもとに、16世紀頃にモーゼス・コルベドロやイサク・ルーリアらの手によって整えられたと言われています。僕がヌース理論に最も親近性を感じるのはこのイサク・ルーリアの思想です。ルーリアは同時代のカバラの大家であるコルベドロの思想などに影響を受けながら自身のゾハール研究を進め、セフィロトのモデルに創造の四段階説(アツィルト・ベリアー・イェッツェラー・アッシャー)などを取り込み、近代カバラの原型を完成させたとされる人物です。ルーリア・カバラの中で特に重要視されるのは次の三つの考え方です。
1、「ツィムツーム(神の自己収縮)」
2、「シェビーラース・ハ=ケリーム(器の破壊)」
3、「ティックーン(容器の修復)」
ツィムツームとは神の、自己自身の内への収縮、もしくは退却と言われます。これは神が宇宙を創造するに当たって、自らの無限性という本質を「収縮」させた形でその場所を用意したのだ、とする概念です。人間が現在、宇宙と呼んでいるもを神の創造の場と考えるのであれば、この宇宙自身がツィムツームの姿だということになります。神の本来の身体性からすればこの宇宙はそのごくごく一部でしかないわけです。
「シェビーラース・ハ=ケリーム(器の破壊)」とは、神の属性と言われる10個のセフィロト(霊的次元を表す器のようなもの)のうち7個が粉々に砕かれ消失してしまうことを言います。器が壊れた原因は原初の人間であったアダム・カドモンの両眼から放たれた神的閃光があまりに目映いものであったため、その閃光を受け入れられるのは上位の3つのセフィロト(ケテル・ビナー・コクマー)に限られ、下位の七個はその強烈な光によって飛散させられてしまったというものです。
本来、自分自身の属性を用いて被造物を創造した神が、その属性を破壊してしまったとするならば、被造物の方は永遠に自らの由来を知ることができずに彷徨うことになってしまいます。これは逆に言えば、神が被造物の居場所を見失ってしまったことと同意であり、神の救済を約束されたものとするユダヤ教徒たちにとってはそれこそ一大事です。そこで、ルーリアは「ティックーン(容器の修復)」という神による救済の概念を用意します。
「ティックーン(容器の修復)」とは、ツィムツーム(神の自己収縮)を弁証法的に統合する作用のことを言います。収縮によって有限世界の中に閉じ込められていた神の神聖なる残り火は、ティックーンによって創造の再発火を起こし、破壊されていた7つのセフィロトを修復させていきます。それとともに離散していた人間の魂も神自身の完全なる身体性の中へと回収されていくという考え方です。
このルーリアのストーリーを要約すれば、神は自己否定のもとに被造物の創造を行ない、それによって破壊された自身の身体を、今度は自己責任においてその破片から再復活させる、ということになります。この復活の際に人間の魂の救済が施されるわけです。――つづく
By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: オリオン, カバラ, プレアデス, ユダヤ, 人類が神を見る日, 生命の樹, 神秘学