1月 20 2007
差異と反復………7
単に3次元の広がりとしてしか認識されていないこの空間には反転したもう一つの3次元空間が重畳している。一つは客体の場(人間の内面)となり、そして、もう一つは主体の場(人間の外面)となっている。これがヌース理論がこの十数年の間言い続けてきていることだ(前者が次元観察子ψ4、後者がψ3に対応する)。
この二つの空間を可視的なイメージに置き換えることは可能だ。それには下図に示したよう正六面体のフレームワークを紙の上に描いてみるといい。この正六面体を3次元立体として見ると二種類のものがイメージできるはずだ。そして、それらは相互に反転していることが分かるだろう(ネッカーの立方体)。対象認識にはこうした2つの空間の存在が暗躍しているのだ。
このような描像を用いて対象界面をイメージしてみると、そこには対象の内壁と外壁が同居している様子が朧げながらも浮かんでくるのではないかと思う。つまり、反転した空間を考慮に入れると、モノと空間の境界面はその内部と外部それぞれの同一性を無効にするような形で存在させられているということになる。つまり、内部=外部、外部=内部という関係を成立させているということだ。内部と外部の向き付けが不能な面。。こうしたイメージはあのおなじみのメビウスの帯が提供してくれるのを僕らは知っている。実際に、前回紹介した2次元射影空間RP^2の切り口は縁のないメビウスの帯になることが幾何学的には分かっている。
つまるところ、僕らの対象認識においてモノの内部と外部を差異化させているのは、このメビウスの帯的な空間の捻れなのだ。これは別の言い方をすれば内部方向と外部方向を等化している力、つまりヌースでいう「最小精神」のカタチである。その等化に反映されているのが中和としての3次元空間だ。内部と外部の間に捻れがあるにもかかわらず、それが見えないと、その捻れ自体が境界のように見えてしまう。それがおそらくモノの界面の現出に潜むからくりである。トポロジカルな言い方をすれば、モノと空間の境界面とは4次元空間における2次元の結び目と言えるのかもしれない。僕らが慣れ親しんでいるのはひものような1次元図形の結び目だが、この結び目を作るには最低3次元の空間が必要になる。ひもの結び方を知っている者にとっては、結び目ができていようとそれは単なる一本のひもにすぎない。しかし、結び目が何か知らない者にとっては、それは奇妙なこぶのように見えてしまう。それと同じで、モノ概念は2次元の結び方を知らない3次元意識だけに存在するものなのだろう。
メビウスの帯の場合、捻りとは帯の幅方向の180度回転に当たるが、3次元空間の場合、捻られたのは無限小と無限大方向相互の180度回転である。このとき、人間が3次元認識の中で「点」と呼んでいたものは、無限大の球面(平面)のようなものに置き換わる。つまり、無限小と無限大の対称性が形作られたということだ。そこが背景正面としてのψ3の位置である。当然、その捻れが見えていないものが反映としてのψ4の位置となる。ψ4はψ3が持った捻れをψ1とψ2の境界のようなものに感じ、等化という回転(捻り)の働きが裏で暗躍しているがゆえに、ψ1(無限大方向)とψ2(無限小方向)の間を反復してしまうのだ。
こうして、等化=差異、中和=反復というヌース理論の文脈からの「差異と反復」の最も基本的な鋳型が幾何学的に構成されたことになる。ということで、次で終わろうかな。。長くなってしまった。。

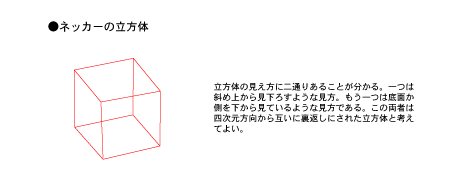






1月 22 2007
差異と反復………8
3、その抽出された概念を被造物の根源的要素とも言える光子と結びつけることはできないか。
さて、ここからが問題の核心に入ってくることになる。ヌース理論とは一言で言えば、意識と物質の統合理論である。統合というからには、それは意識の理論ではあってはならないし、また、物質の理論であってもならない。また逆に、それは意識の理論でなければならないし、かつ、物質の理論でもなければならない。この双方の要請を満たすためには、当然、その思考対象として物質と意識を仲介するための第三の新種の概念が必要となる。それがこのブログでも時折顔を出している「観察子」というヌース理論特有の概念だ。観察子が「観察」という意識的要素と、「子」という粒子的要素を併せ持った名称になっているのもそうした動機付けがあってのことだと思ってほしい。要は、物質構造も意識構造も観察子から成り立っている——そうした考え方のもとに全く新しい宇宙生成論を作り上げたいのである。
今までの論旨の運びを振り返ってみよう。
まずはハイデガーが提起した存在と存在者の差異を創造者と被造物の関係と見なした。そして、その関係は被造物の世界では空間という「一」とモノという「多」の関係として現れているのではないかと仮定した。そこで、被造物世界における存在と存在者の差異は空間とモノとの差異として見なされるのではないか、という推論を立てた。そして、この空間とモノの差異を幾何学的に追いかけてみると、結果として、反転した3次元空間の存在が要求されることになった。反転した3次元空間の実質的意味は射影空間の性質を通して、知覚が成立している視野面そのものの在り方であるということが予想できてきた。知覚が立ち上がっている場所はいまだ自己が生まれる前の純粋知覚の場であり、ここは未だ剥き出しの無意識の主体の位置ではないのかという予測を立てた。哲学的議論からすれば、この場所は第一の内在面とも呼べる場所であり、ハイデガーのいう「現存在」たる人間そのものの萌芽の場所となっている。とまぁ、こんな感じになるだろうか。
このことから、最初に見えていた空間とモノは当然、現存在たる人間が見ているものであるから、本当は、現存在=という差異が先に存在しており、その後、空間とモノという対化が反復のもとに観察に晒されている、ということになる。つまり、外面の3次元が先手で、内面の3次元は後手なのである。差異がまず存在し、その後反復がくる。なぜなら、差異という回転力がなければ反復という振動が起こり得るはずがないからだ。反復は差異の下次元的射影である。このへんの事情は「差異と反復1」に描いた図を見ていただければ一目瞭然だろう。
君が目の前にモノと空間を認識しているとき、意識はその両者の間を反復している。そして、その反復力の大本となっているのは、それを見つめている君自身の存在なのだ。右行ってぴょん。左行ってぴょん。右行ってぴょん。左行ってぴょん。それに飽きたら上行ってぴょん。下行ってぴょん。下に見えるは、左右のぴょん。あ、ぴょん、ぴょん、ぴょん。おっとさんが呼んでも、おっかさんが呼んでも、ききっこなぁ〜しよ。井戸の周りでお茶碗かいたのだぁ〜れ?
悪ふざけはこのくらいにして、いよいよ核心に触れなければならない。それは、今まで話してきた差異と反復の幾何学的鋳型をもとに、この構造をどのようにして光子(電磁場)と結びつけるのか、ということである。電磁場は場の量子論によれば、複素平面上の単振動として表せることが分かっている。つまり、電磁場も差異と反復の構造を持ち合わせているわけだ。では、電磁場においては一体何が差異で、何が反復しているのか——まずは、その様子を複素平面上の円運動からチェックしてみることにしよう。 つづく
(今回でこの連載は止めようと思ったけど、トーラスさんからの激励があったので、もちっと続けますたい。)
By kohsen • 差異と反復 • 0 • Tags: ハイデガー, 差異と反復