12月 9 2008
時間と別れるための50の方法(57)
●止核と核散について………トランスフォーマー型ゲシュタルトが持つ意義
正六面体と正八面体の4つの階層によって構造化されたプラトン座標の機構。これは次元観察子の骨組みと言っていいものに当たりますが、ここで見ていただきたいのは、正八面体における3本の立体対角線と正六面体における4本の立体対角線の関係です(下図1)。
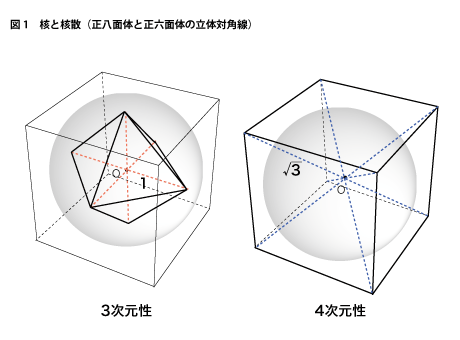
これらの立体対角線の長さは正八面体を1とすると正六面体は√3です。正八面体と正六面体が持っているこの立体対角線の数「3」と「4」の関係は、神秘学の系譜が「3」と「4」を宇宙の成り立ちの根本的要素と見るのと同じで、ヌーソロジーの観点から見てもとても奥深いものを感じさせます。つまり、観察子のシステムというのは、ユークリッド次元でいうとそれこそn次元(n→∞)に向かって限りなく続いていくのですが、しかし、「数が1から4までしか存在しない」のと同じ理由で、空間も実は3次元的な観念と4次元的な観念がベースとなって、5次元以上の空間というのは、実は、3次元的なものと4次元的なものの反復による多重化によって構造化されているにすぎないということなのです。
そのように考えた場合、プラトン立体というのは確かに「立体」という名が冠せられてはいるのですが、実は、通常考えられているような3次元ユークリッド空間内の立体的な表象として捉えられるべき形状ではなく、空間の根底にセットされた本源的な観念の機構のようなものではないかと考えられます。
そのような理由からかどうかは分りませんが、OCOTは、この正八面体のことを「核(かく)」、正六面体のことを「核散(かくさん)」と呼び、次元構成をコントロールしていくための調整質と見なしているようです。核とは文字通り、意識の働きの中核を意味する言葉で、核散はその中核を解体させることを意味します。
プラトン座標ではこの正八面体と正六面体が三重構造をもって構成されているわけですが、この「核」と「核散」が持った働きの三重性は、スピリチュアルな数字遊びが好きな方には「6・6・6」と「7・7・7」と言った方がピンとくるのかもしれません。ここでの「6」は正八面体が持った方向性の数(±x、±y、±z)を意味し、これが三重構造をとっている「6・6・6」では、次元観察子のシステムは観察子の連結の要となっている4次元性を見失い、各々の観察子階層の差異が見えなくさせられてしまいます。このとき「核」は「止核」していると言い、特に次元観察子ψ1~ψ2での止核力は「スマル(核質化した不連続質の意)」と呼ばれます。これはいわゆるモノの自己同一性を作り出している力のことです。物質概念のことですね。
一方、ここでいう「7」とは、観察子の差異を見出す√3エッジとしての4次元性のことです。この「7・7・7」の方では核散ルートの方向性が開かれ、「核」は「6・6・6」の差異を見せてくると同時に、解体を余儀なくされていきます。そして、言うまでもなく、この「核」から「核散」への接続は、現在ヌーソロジーが行なっている「人間型ゲシュタルト」から「トランスフォーマー型ゲシュタルト」への移設作業のことを意味しています。ちなみに、この場合の「8・8・8」とは、「7・7・7」の付帯質として存在させられている時間の働きに相当していると言えるでしょう。
意識が「核質」に止められ「止核」して働いてる状態が『シリウス革命』でも紹介した「調整期」に当たり、核散に入っている状態が「覚醒期」に相当します。覚醒期においては、タカヒマラにおける止核作用が解除されて核散が生起し、中和作用(付帯質の働き)が等化作用(新しい精神の働き)へと変換されていくことになります。
ここで、プラトン座標の正六面体と正八面体に双対の正四面体を書き加え、拡散方向である4次元から垂直に見下ろしてみることにしましょう。すると下図2のような次元観察子のパースベクティブ(透視図)が目の前の空間に出現してきます。ヘクサグラムの多重構造です。この図形はヌーソロジーではシリウス次元を象徴する形の意味を持ちます。つまり、付帯質(人間の状態)を精神(ヒト)へと反転させていく次元です。付帯質が六茫星でそこに直立する軸が精神だと考えておいて下さい。
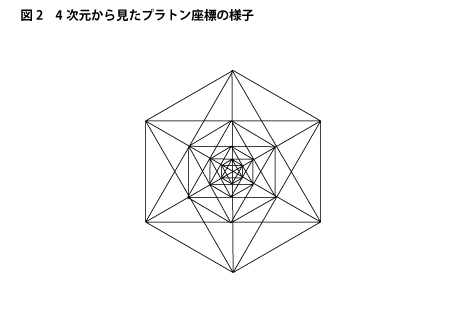
コ : ヘクサグラムとは何ですか?
オ : 中性質があるということです。意識が通る道のようなもの。(シリウスファイル)
「意識が通る道」というのはヌース(旋回的知性)のルートと同じ意味を持ちます。この道は視線を軸とする回転によって螺旋状に運動しながら観察子の次元を上昇させていくことになります。もちろん、その反映としてのノスも逆方向に交差しながら通過していきます。六茫星(ヘクサグラム)はシリウスの象徴です。次元上昇へのゲートがパックリと開かれている状態と考えて下さい。楽園への扉がやっと開いたということでしょう。この中性質についてはまだ解読が不十分なので、ここでは説明できません。解読が深まったら、いずれ、DNA構造について語るときに詳しく解説していきます。
――つづく







12月 12 2008
時間と別れるための50の方法(58)
●ケイブコンパスと元止揚空間
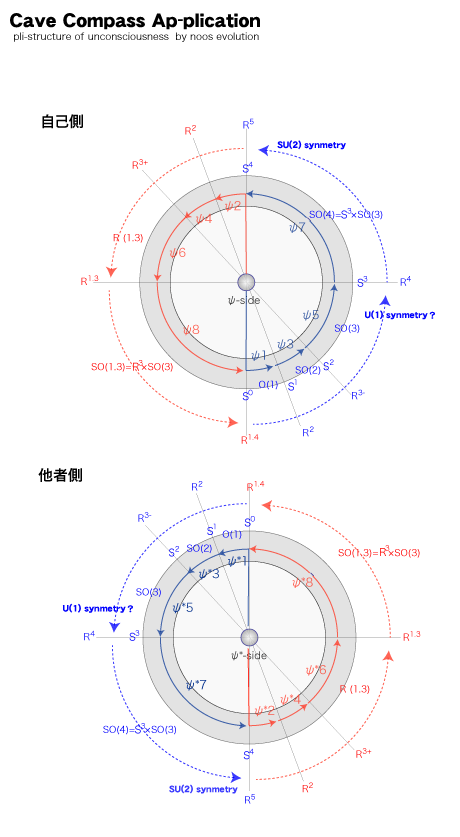
さて、ヌーソロジーが用いる次元観察子という耳慣れない概念について、その第一番目から第八番目に当たるものまでを解説してきましたが、とりあえずここでまとめの意味でも、今まで説明してきた次元観察子ψ1~ψ8の概念をケイブコンパス上で整理して配置しておきたいと思います。
「ケイブコンパス」というのは『シリウス革命』で紹介した「プレアデスプレート」という人間の意識次元の構造を表したモデルの改訂版のようなものです。「プレアデスプレート」は人間の意識発達を観察子の序数に沿って順序づけた円環モデルだったのですが、このモデルでは観察子相互の有機的な連結がうまく表せませんでした。どうしたものかと煮え切らない気分でいたときに、2001年になってドゥルーズ・ガタリの『アンチオイディプス』『千のプラトー』という二冊の書物と出会い、「プレアデスプレート」は一気に「ケイブコンパス」へと生まれ変わりました。あのときのコンバージェンスは強烈でした。四方八方に飛散していたヌーソロジーの世界イメージがドゥルーズ・ガタリの思想線に吸い付けられるようにことごとく一致していったからです。この「ケイブコンパス」のモデルが出来上がって、ヌーソロジーは単にオカルティックな知識だけではなく、現代思想の潮流とも接続が容易になったと言えます。
「ケイブコンパス」とは、言ってみれば無意識構造の海(人間の外面の意識の総体領域)を航海していくための羅針盤のようなものです。ヌーソロジーはこのケイブコンパスによって、フロイトから発した無意識研究の成果として著されてきた様々な諸理論、例えば、ピアジェやエリクソンが示した発達心理学や、ラカンの示した精神分析、さらにはユング派のノイマンが示した人類の歴史的な集合無意識の発達構造の仕組み等を、単に観念的なモデルではなく、今まで皆さんに解説してきた次元観察子ψ7〜ψ8を土台とした次元観察子ψ9〜ψ10、ψ11〜ψ12の空間構造の流れの中にマッピングしていくことになります。
ケイブコンパスが誘導していく無意識構造の世界は、最終的に元素番号1番と2番の水素-ヘリウム構造とシンクロしてきます。にわかには信じ難いかもしれませんが、これは人間の意識-無意識構造が実のところ、水素-ヘリウム構造の中で律動させられていたということを意味しています。今になって思えば、交信初期にOCOTがなぜ太陽の核融合の話にあれだけこだわっていたのかが分る気もします。
「では、あなたは太陽の本質について何か完全な解答をお持ちだというのですか。」
「完全とは申しませんが、プレアデス的統制より本質を捕らえているのではないかと思います。」
「なるほど、では、その本質について聞かせてほしいものです。」
わたしは科学を馬鹿にされたような気がして、やや挑戦的な口調になった。
「太陽とは、オリオンからプレアデスへと向かう意識の流動を、逆方向へと向かわせる力の総体が、人間の意識に現れている部分です。人間が進化の方向へ意識の反転を行うための鏡のような役目を持っています。オリオンが持った無限力の下次元的射影という表現もできますね。」
意識の反転のためのカガミ………………? あまりに抽象的で難解な表現だった。
『2013 : 人類が神を見る日/アドバンストエディション 』p.41
このケイブコンパスが露にしていく世界は、密教的に言えば、以前もご紹介したように胎蔵界曼荼羅に描かれた世界のことであり、カバラで言うならば、アッシャー界におけるマルクト(地球)-イエソド(月)–ネツァク(金星)-ホド(水星)-ティファレト(太陽)までの働きを含んだものと言えるのではないかと思います。
ケイブコンパスの全体性は、人間の無意識を構成するψ1~ψ14、ψ*1~ψ*14という合計28個の次元観察子の配置関係から構成されています。人間の外面側であるミクロ空間側ではこれらは素粒子構造の全体性を表しており、一方の人間の内面側であるマクロ空間側では「28」という数からも想像されるように、地球-月間を支配する28日の月の自転、公転周期に反映されてくることになります。まだ漠としたイメージでしかありませんが、ヌーソロジーでは素粒子空間と地球-月空間は7次元球面の表裏、同様に原子空間と太陽系空間もより高次の空間における同じ構造体の表裏関係として把握されてくるのではないかと予想しています。人間の内面の意識ではミクロとマクロが等化できていないので、「小さなものが大きなものを作る」という機械主義、還元主義的な世界観に入り込んでいますが、4次元に始まる高次元知覚能力が生まれてくれば、ミクロ世界とマクロ世界は同一のものの正反方向における射影のように見えてくるのではないかということです。
このシリーズで詳しくご紹介してきた次元観察子ψ1~ψ8は、こうした新しい宇宙ビジョンを描像化していく上で最も基礎となるプラットフォームとなっており、この基礎の部分をヌーソロジーでは「元止揚空間(げんしようくうかん)」と呼んでいます。「元止揚」という言葉の由来は、この空間領域が、前次元の人間の意識進化が作り上げたヒトの精神の力によって止揚されてきたものだと考えているところにあります。つまり、どうも旧次元の人間の意識進化の集大成がこの次元の人間の意識を支えるための土台として押し上げられてきているようなのです。
ヒトの精神と付帯質とは、観察子で言えば大系観察子Ω7とΩ8に当たるもので、これは人間の意識の覚醒において生起する次元観察子ψ1〜ψ14の顕在化が作り出していきます。その意味で次元観察子の顕在化を進めて行くトランスフォーマーとは、ヒトの精神の構築に着手する者という言い方ができるかもしれません。ケイブコンパス全体の構造を意識が知覚できたときに、トランスフォーマーはヒトの意識へと進化を果たすことになるのでしょう。ヌーソロジーが目指すとりあえずのゴールです。
人間の意識におけるψ7〜ψ8=Ω1〜Ω2………終了済み
人間の意識におけるψ9~ψ10=Ω3〜Ω4………終了済み
人間の意識におけるψ11~ψ12=Ω5〜Ω6………2012年に終了予定
人間の意識におけるψ13~ψ14(顕在化)=Ω7〜Ω8………2013年より突入予定
こうして作り出されたヒトの精神と付帯質である大系観察子のΩ7〜Ω8が、今度は、次の次元の人間の元止揚であるψ*7〜ψ*8を作り出し、次の次元の人間の意識はこのψ*7〜ψ*8を土台にして再び、ψ*9~ψ*10、ψ*11~ψ*12というように、胎蔵界曼荼羅の世界を経験していくことになるということです。『シリウス革命』で書いた宇宙的輪廻の具体的な仕組みがここにはあります。
この元止揚のシステムは、このシリーズの第56回目に紹介した「凝縮化」という作用によってもたらされてきます。凝縮化は次元観察子ψ、大系観察子Ω、脈性観察子φというタカヒマラを構成するすべての観察子の律動に一貫して貫かれている法則性です。この凝縮化は凝縮化に凝縮化を多重に重ね合わせていくことによって、最終的にはタカヒマラのすべてがψ1~ψ2領域に入り込んでくるような仕組みになっています。つまり、タカヒマラに凝縮化の仕組みが存在しているからこそ、タカヒマラで律動するすべての高次元精神の活動はモノ(ψ1~ψ2領域)の中にその影を作り出すことができているわけです。そして、その最たるものが、言うまでもなく、人間の肉体です。
ヒトへの道のりはまだまだ長いです。ゆっくり行きましょう。ちなみにヌーソロジーのシンポルナンバーである「2013」とは、位置の変換(顕在化)が始まる年です。手前味噌になりますが、現在ヌーソロジーが行なっていることが、多くの人に認知され始めるということかな?いや、そうした動きはヌーソロジーのみならず、世界の様々なところで起こってきていますから、霊性奪回の動きが社会的な潮流となり始めることを言うのでしょう。ヌーソロジー的に言えば、2012年で人間の意識は次元観察子ψ11~ψ12の段階が生み出してきた近代合理主義、科学主義、個人主義、さらには資本主義に終止符を打って、ψ13〜ψ14という位置の変換のステージへと突入していくことになります。OCOT情報をまともに受け取るならば、このステージは実は驚くほど短いんですね。たった24年で終了するようです。というのも、位置の変換の時期においては、どうも1年と次元観察子の1単位が同期するような仕組みがあるようで。。。ということは、2013+24=2037ですから、西暦2037年には位置の変換が完全化し、新しい人間の精神が元止揚として誕生してくるということになるのでしょうか。もし、アセンションというものが劇的な自然現象の変化として現れるというのならば、この2037年の方が本命かもしれません。「入神」です。人間の意識がヒトの精神に入ること。そのとき存在世界全体が反転を起こすことになります。ほんまかいな(笑)――つづく
By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 1 • Tags: アセンション, アンチ・オイディプス, オリオン, カバラ, ケイブコンパス, シリウス革命, タカヒマラ, ドゥルーズ, フロイト, プレアデス, ラカン, 人類が神を見る日, 付帯質, 元止揚空間, 大系観察子, 素粒子