9月 27 2012
紀要論考の公開
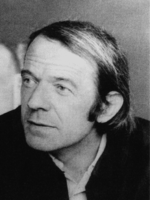 昨年度、大学へ提出した紀要論考。紀要が発刊になったので、この場を借りて公開しておきます。ドゥルーズ哲学の照準に重ね合わせて、ヌーソロジーのたくらみをひっそりと忍ばせております。題して『21世紀はドゥルーズの世紀になるか』。
昨年度、大学へ提出した紀要論考。紀要が発刊になったので、この場を借りて公開しておきます。ドゥルーズ哲学の照準に重ね合わせて、ヌーソロジーのたくらみをひっそりと忍ばせております。題して『21世紀はドゥルーズの世紀になるか』。
21世紀はドゥルーズの世紀になるか
SAF 半田広宣
1.オイディプス的構造を乗り越えるために
「いつの日か世紀はドゥルーズ(Gilles Deleuze)のものとなるだろう」とフーコー(Michel Foucault)が予言して、はや数十年の月日が流れた。この間、現代哲学の主流はフランスのポスト構造主義から英米を中心とした分析哲学へと移行し、ドゥルーズの弁を借りるなら哲学はまさに哲学内部から出現した哲学の暗殺者によって殲滅の危機に瀕していると言える。ドゥルーズにとって分析哲学は科学の範疇に属するものにすぎず、またそれが科学である限り思考をオイディプス化に導くものであり、生命の力を衰退させる否定的な力の側に与しているのである。こうした現代哲学の窮状を見れば、フーコーの予言にあるドゥルーズのものとなるはずの「世紀」がもはや20世紀でなかったことは明らかだが、翻ってこの21世紀は果たしてドゥルーズのものとなるのであろうか。「哲学とは概念を創造することである」とドゥルーズはつねに言い続けてきた。概念とは一般に事物が思考によって捉えられ、かつ表現される時の思考内容や表象、またその言語表現の意味内容のことをいう。ドゥルーズ自身、表象=再現前化を一貫して批判し続けた哲学者だったことを考えれば、彼が論じる「概念の創造」における概念という言葉が持つ意味は一般に使用されるそれとは全く違うものであることは容易に想像できる。2011年に生起した「3.11」という出来事以降、生命の力に対する迫害や抑圧を国家と個の間におけるダブルバインドというかたちでより一層リアルに感じるようになったわれわれ日本人にとって、ドゥルーズの言う「概念の創造」はこのダブルバインドを人間にもたらしているオイディプス的構造を乗り越えるための唯一の方法であると筆者は感じている。その意味でもドゥルーズが彼の哲学において一体何を企図していたのか今一度真摯に検討を加えてみる必要があるだろう。この小文ではドゥルーズの絶筆となった小論のタイトルともなっている『現働的なものと潜在的なもの』をキータームとしてドゥルーズ哲学のエッセンスとその思考のベクトルが秘めた可能性(ドゥルーズならばそれこそ潜在性と呼ぶだろうが)を探ってみたい。
2.現働的なものと潜在的なもの
『現働的なものと潜在的なもの』はクレール・パルネ(Claire Parnet)との共著である『対話』の中の巻末付録として設けられたわずか7ページほどの短い論考である。ドゥルーズ哲学の最も基底的な骨格とされる「現働的なもの」と「潜在的なもの」という二つの概念がそのままタイトルに付されたこの論考がドゥルーズの遺稿となったことは決して偶然ではないように思われる。周知のようにドゥルーズの思考の足跡は大きく四つの時期に区分することができる。まずは思想史家としてヒューム、ベルクソン、ニーチェ等の研究をスタートさせ、第二期はそれらの研究成果を『意味の論理学』『差異と反復』といった主著の中でドゥルーズ独自の理念論として発表する。第三期になると一転、精神分析家のフェリックス・ガタリと共同して『アンチ・オイディプス』や『千のプラトー』を著し、自らの理念論をより実践的な思想とするために社会学的、政治学的な分野へとその応用可能性を論じていく。第四期は打って変わって知覚論や感性論へと分け入り、『感覚の論理』『シネマ』等の極めて深遠なドゥルーズ的芸術論を繰り広げる。『現働的なものと潜在的なもの』はこうした思考の遍歴を経た後に自らの思想の一つの総括のようにしてしたためられた。元来、「現働的なもの」と「潜在的なもの」という対比概念は『差異と反復』の第二章「それ自身へ向かう反復」で示されたドゥルーズの時間論にその多くを負っている。ここではその詳細を語る余裕がないので別の観点からの説明に止めざるを得ないが、「潜在的なもの」とはドゥルーズが考える理念の様態のことであり、「現働的なもの」とは潜在的なものが諸々の種や対象として現象の中にあらわれ出たもののことをいう。通常、この現働的なものと潜在的なものはドゥルーズ哲学を支える二元的要素に見られがちなのだが、しかし、これら両者は決してプラトンのイデアと仮象のような短絡的な二項関係を意味するものではない。ドゥルーズが展開する生成の地理学においては、この両者は互いが互いを包含するような形で、ある二つの仕方において一つの回路を形成している。それはドゥルーズに言わせれば「ある場合には、潜在的なものが現動化されるような巨大回路の中で、現働的なものが[自ら]とは別のものとしての潜在的なものに向かうという仕方で、ある場合には、潜在的なものが現動的なものと結晶化するような最小回路の中で、現働的なものが自分自身の潜在的なものとしての潜在的なものに向かうという仕方」(1)においてである。ここで巨大回路と最小回路という明瞭な対比で言及されているように、ドゥルーズによれば、生成は現働的なものと潜在的なものとのカップリングによって絶えず変動を起こしていく〈時-空間〉的力動であるのだが、このカップリングの仕方には大きく分けて二つの類型があるのである。それは単純明快に言えば力が大きく開いて生成を産出する場合と、力が小さく閉じて生成を産出する場合の二通りの仕方と言っていいだろう。力が大きく開いて働く場合は潜在的な諸力が浮上し、現働的なものとして作用していた諸力はあくまでもその補完部分の中に取り込まれる。反対に、力が小さく閉じて働く場合には現働的なものが自らの中に潜在的なものを押さえ込み、潜在的なものを表象=再現前化の再帰的円環の中に閉じ込めてしまう。ドゥルーズ哲学に敢えて二元論的要素を見て取ろうとするならば、このような二通りの生成の回路の在り方がそれに相当すると考えなければならない。これら二つの生成の回路は『意味の論理学』で論じられたところのクロノス的時間における生成とアイオーン的時間における生成とも言えるだろうし、スピノザ(Baruch De Spinoza)に即して言えば、順に能産的自然と所産的自然と呼ばれるものに相当するだろう。
このような新しい二元論的図式の構想はドゥルーズの中ではすでに『ニーチェと哲学』において用意されていたと考えてよい。なぜなら、この二元性はニーチェ(Friedrich Nietzsche)が能動的な生成と反動的な生成と呼ぶものにほかならないからである。ドゥルーズがニーチェの哲学の中に見たのは、これら二つの回路の切り換えを決行する蝶番とも言える「根源」の到来についての思考であった。この「根源」の到来は周知の通り「存在するものすべての最高の形相」(2)であるところの永遠回帰と呼ばれているもののことである。ドゥルーズはいう。「根源には、能動的な力と反動的的な力との差異が存在する。能動と反動は継起的な関係にあるのではなく、根源そのものにおける共存関係のうちにある」(3)のであり、「反動的な力の側からみると、差異的な系譜学的境位は逆さまに現れる」(4)と。そして、ここで逆さまに現れる差異的な系譜学的境位こそが、潜在的なものを最小の回路の中に閉じ込めている現働的なものが主導権を握ったわれわれ人間=自我という反動的生成の場なのである。つまり、根源には根源の転倒した「人間」という像が常につき纏っているのだ。ドゥルーズが絶えず哲学に「概念の創造」を要求するのもこのニーチェ的な「根源」としての永遠回帰の場所性を念頭においての問題提起だと考える必要があるだろう。となれば、「概念の創造」とはニーチェのいうところの「力への意思」の言い換えでもあり、発生論的な境位における諸力の総合の原理たる理念の創造のことだと言っても過言ではない。事実、ドゥルーズは『差異と反復』において諸力の総合の原理をそのままドゥルーズなりの超越論的構成の原理と重複させて論を進めていく。現働的なものが支配する超越的な場の中で「思う我」と「ある我」との両極の間でひび割れていたデカルト的コギトはニーチェのいう「価値評価する視点の転倒」を導入することによって、〈現働的なもの/潜在的なもの〉がただ反復するようなクロノス的円環に捻りを入れ、このひび割れを修復するような超越論的運動に入るということである。この新たな境位において主体は今まで文字通り潜在化していた潜在的なのものを純粋な内在性のうちに自らの本性として発見することになる。潜在的なものが現動的なものの支配下にあるうちは単にベルクソン(Henri Bergson)的な持続としてしか働くことはなく、表象=再現前化の運動の中に絡み取られてしまう。それは「反動的諸力は能動的な力からその一部ないしほぼすべてを抜き去り、そしてそれによって能動的になるのではなく、逆に、能動的な力を反動的諸力と合流させ、新たな意味においてそれ自体反動的となるようにする」(5)からである。ベルクソンが哲学の中に潜在的なものというアイデアを導入したのは大いに評価されるとしても、その潜在的なものの奥行きをベルクソンのようにただ悪戯に拡張していっただけでは、それはクロノス的時間の中で現動的なものに回収されるにすぎず、神秘主義と見紛うような茫洋とした生気論に終始するしかない。ドゥルーズにとってベルクソニズムをより精度の高い生成論に生まれ変わらせるためには、ニーチェという逆光のプリズムを介入させ、潜在的なものの諸力をそのままダイレクトに能産的自然の生成力へと変容させる必要があったのである。ドゥルーズ哲学のキーワードとなる差異と同一性の関係についてもほぼこれと同じことが言える。現働的なものにおいて差異は同一性に従属するものでしかないが、ニーチェ的な存在の転回においては大いなる肯定によって潜在的なものが認識の表面へと出現し、そのために今度は同一性が差異に従属する側に回ることになる。つまり、同一性は差異の系譜学的展開であるところの、「諸差異を他の諸差異に関係させるシステム」(6)によって担保されるものでしかなくなるのである。
3.現代物理学とドゥルーズ的思考
『現働的なものと潜在的なもの』の冒頭において、ドゥルーズは「哲学とは多様体の理論である」(7)ともいう。ドゥルーズによれば潜在的なものも現働的なものもすべてこの多様体の範疇の中に含まれている。哲学が「概念の創造」であり、かつ、それが同時に多様体の理論であるのであれば、哲学とは理念としての多様体を思考によって空間的に創造する営みにほかならない。それは直裁的に言えば、〈時-空間〉的力動の在り方を現働的なものの優位性から潜在的なものの優位性へと転換させ、われわれの時空に対する知覚様式を全く別な様式へと変革していくことに等しい。この変革によって、今まで客観世界に従属して働いていた内在野は主客関係を超越論的に総合した内在平面へと変容を起こし、そこでの概念を理念として機能させることが可能になるのである。しかし、周知のように、あのソーカル事件以降、「多様体」「微分」「特異点」といったドゥルーズが用いる物理数学的概念は科学者たちからは概念の濫用として幾分疎まれがちなものになったことは否定できない。願わくは科学者たちには細かい専門用語の用法ではなく、ドゥルーズの思考の底辺に潜むそのダイナミズムにより注意を払ってほしいものである。量子力学が明らかにするところによれば、物理的な力の成り立ちは位置と運動量や時間とエネルギーの間の正準交換関係における差異に依拠している。このことは本論で紹介した現動的なものと潜在的なものの二通りのカップリングが作る差異によって力の根源の場が生まれるとするドゥルーズの思考と深い関連を示してはいないだろうか。かつ、量子力学から発展した場の量子論では、電磁力や弱い力、強い力における三つの相互作用の統合を高次元の複素多様体における回転対称性の拡張の中に求めているのだが、こうした統一理論の理論的発展の流れは差異の差異化を潜在的なものの進展と見なすドゥルーズの思考線に沿って進んではいないだろうか。さらに言えば、現在、超弦理論よりもより根源的な理論と考えられているM理論に登場する空間の極大領域と極小領域を関係付けるT双対性は、「無限は大と小は同一であることを、そして極限的なものたちは同一であることをも意味している」(8)と断言するドゥルーズの潜在的直観が現働化されたものの表現ではないだろうか。こうした現代物理学が到達した知の状況をも踏まえて、われわれには今、科学的思考の先端と哲学的思考の先端との協同における新しい空間概念の創造が必要なのである。ドゥルーズが長年にわたって温めてきた理念論はそのための高精度な羅針盤として欠かすことのできないものであり、現働的イマージュの中で捕縛された科学的な表象を潜在的イマージュへと一気に変態させる能力を秘めている。科学的諸概念がひとたび潜在的なものをベースとする領域へと価値転換を起こしたときには、現代物理学がいうところの力の超統一場の理論は、文字通り、力の発生論的境位における諸力の総合の原理と有意味な一致を見るに違いない。なぜならば、ドゥルーズが言うように科学的思考はすでに「時間の空虚な形式」としての永遠回帰を経験しているのであり、あとはそこに流れる直線的時間を「永遠に脱中心化されるひとつの円環」(9)へと接続させるイマージュが加わりさえすれば、あの能動的生成の扉が開くことになるからである。そのときわれわれはドゥルーズが言わんとした巨大回路の入口に立つことになるだろう。無論、これはあくまで21世紀がドゥルーズのものになれば、という仮定の話だが。
(1) ジル・ドゥルーズ / クレール・パルネ『対話』(河出書房新社2008年)234頁
(2) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)96頁
(3) ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(国文社1991年)86頁
(4) ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(国文社1991年)86頁
(5) ジル・ドゥルーズ「意味と諸価値」-ドゥルーズ/没後10年、入門のために(河出書房新社)155頁
(6) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)185頁
(7) ジル・ドゥルーズ / クレール・パルネ『対話』(河出書房新社2008年)229頁
(8) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)78頁
(9) ジル・ドゥルーズ『差異と反復』(河出書房新社2001年)182頁







6月 6 2013
「奥行き」と『2001:A Space Odyssey』
奥行きと幅について考えてると、まるで目の前の空間にポッカリとワームホールが空いたようで、どんどん深みに引き込まれ、おまけにグルグルと旋回ひねりが入っていくものだから、脳みその関節がガタガタに外されて、今まで抱いていた共通感覚=良識というものが木っ端みじんに粉砕されていく。
そこで今日も、存在論的妄想をひとつ。
まず、奥行きは時空ではない。では一体どこなのか——奥行きは空間的には無限小の中にしか指し示せない場所であり、時間的には「すべての時間を懐に抱いたところ」としか言いえないような非-場所である。そして、なおかつ「それは何か」と問うこともできない。というのも、それは「それ」といったような対象ではもはやないからだ。自らが自らをあらしめているもの。その存在のため他のものを一切必要としないもの。まさに哲学的な実体とも言えるような何ものかである。よって、そこに主体が持った意識の志向性などといった野暮ったい概念を持ち込むことももはや許されない。いわば奥行きは空間の即自体でもあり、時間の即自体でもあり、もっと言えば、認識、思考の即自のような場所ではないかと感じるのだ。このことに感応したとき、以前は、「これぞ真の主体だ!!」などと言って舞い上がっていたのだが、奥行きの深みに居づけば居づくほど、この非-場所を単に「真の主体」とか「永遠」とか安易に呼んでいいものかどうか。。
ドゥルーズは『差異と反復』の前書きで次のようなことを言っている。「現代哲学のなすべき仕事は、〈時間的-非時間的〉、〈歴史的-永遠的〉、〈個別的-普遍的〉といった二者択一を克服することにある」と。そして「時間と永遠性よりもさらに深遠なものとしての反-時代的なものを発見すること」と。
奥行きの本性は確実にここでドゥルーズがいう「反-時代的なもの」につながっているような感覚がある。反-時代的というのは別に時代に抗って自然に戻ろうとか、そういうことを言ってるわけじゃない。世界がこれまで進んできた方向に対して、その大本からUターンすることである。神秘主義的に言えばプロティノス的転回とでもいおうか、つまり、所産的自然としての精神の営みから能産的自然としての精神の営み、つまり世界を創造していく能動的諸力への変身を果たすということだ。ニーチェ=ドゥルーズならば、迷わず力への意思と呼ぶに違いない。
と、ここで、いきなり『2001:A Space Odyssey』のオープニングが。。。リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」のBGMとともに、月の向こうからゆっくりと地球が現れてくる。ダントン、ダントン、ダントン、ダントン♪〜そして今度はその地球の向こうからまばゆい光を放ちながら太陽が昇ってくる。。ダントン、ダントン、ダントン、ダントン♪〜嗚呼、なんという黙示録的ビジョン。
月の力を太陽の力へとメタモルフォーゼさせる地球という名の原初的精神。反時代的なものとはまさにこの「始源」へと突然変異したところの地球のことなのだろうと思う。奥行きに沈み込んでいた永遠としての月の潜在的諸力が、奥行きの開示と共に地上でうごめいていた知覚や言語や情動や思考のすべてを飲み込んで、太陽の内包性へと接続を果たしていく。わたしたちはそこに放たれるそのあまりの光の透明性にもはやモノを見ることはなくなり、観ることそのものへと変身を遂げていく。
ここに地球という天体の意義、つまり大地の意義がドゥルーズのいう〈時間的-非時間的〉〈歴史的-永遠的〉〈個別的-普遍的〉といった二者択一を克服するものとして立ち上がってくのだと思っている。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, 09_映画・テレビ, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: 2001年宇宙の旅, ドゥルーズ, ニーチェ, 奥行き, 差異と反復