12月 6 2018
ヌーソロジーは難しいものというよりも、まったく違うもの
ヌーソロジーの入門本なんかも書いてるRaimuくんのRaimu_botから次のようなツイートが流れてきた。
@raimu_mage_bot
ヌーソロジーが難しい理由は、半田広宣さんの語る哲学用語や量子力学の数式や、重厚な論理構造が難しいというのが一つと、語ってる概念を認識すること自体が難しいというのがもう一つ。前者は語り手の知恵と工夫でなんとかなる余地のある所だけど、後者は各自がセンスによって試していくしかない。
確かに、その通りだな~とは思いつつも、ちょっと補足をしたくなった。
ヌーソロジーは、最初にOCOT情報という極めて抽象度の高いチャネリング情報があって、それを解読していく過程で、神秘学、宗教、哲学、精神分析、量子論などの知識が必要になり、結果、現在のようなスタイルになっている。
実は、OCOT情報が伝えてきたことは「空間に対する認識を反転させよ」ということだけ。実際、その情報のほとんどは、反転した世界の意識風景を独自の幾何学概念で語ったものがほとんどだ。その意味でいうなら、ヌーソロジーは「難しいもの」なのではなく、「まったく違うもの」と考えて接した方がいい。
たとえば、あれほど頭脳明晰な物理学者たちに量子の本質が理解できないのはなぜか。この量子の本質は研究が進めば解明されるといった類の問題じゃない。その謎を解くためには全く別の思考形態が必要だということなんだよね。ヌーソロジーはそれを作りたいわけ。
ただ、その青写真とも言えるOCOT情報も、死海文書のようにバラバラに断片化されたものでしかないので、そのプロトタイプが意識に再構築されていくためには、それ相当の紆余曲折を経ないと無理だと思ってる。また、その紆余曲折の中で苦悩、葛藤することがとても大事。
ヌーソロジーをやるということは、その作業に参画するということでもあるので、意識が今までに経験したことのないような新種の苦悩を抱えこむことになる(もちろん、それに呼応した愉しさもあるけど)。そうした苦悩を好まない人は、ヌーソロジーには最初っから近づかない方が賢明。
まっ、それなりに異質さを理屈抜きに楽しむという選択もアリだけどね。
僕の見通しとしては、反転した意識のカタチが思考上に確実化すれば、物理学や哲学の知識も一切必要なくなるんじゃないかと思ってる。それらは、反転概念を判明なものにするための触媒のようなものなので、反転を起こすプロセスにはやはり欠かせないものって感じかな。
反転した空間は、物理学ではヒルベルト空間(量子系の状態空間の形式)として表現されており、哲学ではドゥルーズのいう差異化の空間(内包空間=スパティウム)として語られている。それを認識にあげることが空間認識の反転にストレートに繋がっている。
いずれにしろ、双方とも延長的なものではなく、持続的なもの。この延長感覚から持続感覚への切り替えというのが、哲学的センスが必要とされるところだね。それこそ、ハイパータイム的な感覚を身につけないといけない。
こうした移行がOCOT情報にいう「付帯質の外面(ニックネームはプレアデス)」から「付帯質の内面(同シリウス)」への意識進化ということになる。時間を空間のように見る、それこそ物質空間から精神空間の世界へと意識が方向を変えていくわけだね。それをシュタイナーなんかはエーテル界への参入(霊界参入)って呼んでるんだと思うといいよ。

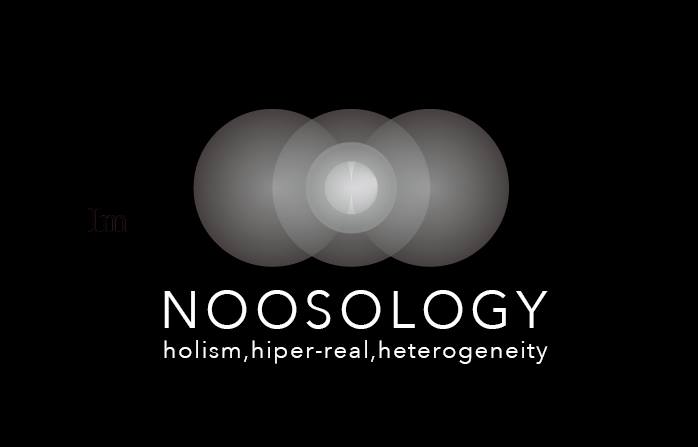






12月 27 2018
ψのケイブコンパスの全体像の大まかな解説
春井さんの話でケイブコンパスの全体像が出てきたので、ついでに言っておくと、次元観察子ψ10~9(ψ8~7含む)とψ12~11の間には断層があり、歴史意識的にはψ12~11は近代以降の意識に当たる。面白いことに、OCOT情報はこのψ12~11の領域を正確な意味で「人間」と呼んでいる。つまり、ψ10~9の段階では「人間」はまだ存在していなかったということだ。
これはよく言われてることだけど、人間とは近代の発明品のようなものと考えた方がいい。その意味で、人間は今後、僕らの想像を超えるような変化を見せていくことになる可能性を秘めている。現在の近現代が作りあげた人間観に固執する必要はどこにもない。人間について知ってる人間なんてどこにもいやしないのだから。人間は神と同じくらい神秘的な存在なのだ。
ということで、ついでにケイブコンパスについて、簡単に説明を入れておきます。
近現代の意識地層は破線で囲んだ場所に当たる。ψ10~9までは内在的視線は2次元(前後・左右)で水平的だけど、ψ12~11では4次元(前後・左右・上下・統合)となって、それが複素次元ではSU(4)(複素4次元の回転)に関係してくると考えられる。
ドゥルーズ=ガタリのいう「逃走線」はψ11後半の自己意識の完成の部分に当たる。ここは外面領域なので人間の意識がスキゾ化していて、理性が理性自身の解体を目論んでいる場所でもあるということだね。ψ12後半とψ11後半は資本主義における領土化と脱-領土化の反復回路のようなものと考えると分かりやすいかも。
で、問題は一番上の「最終構成」というやつ。これは個の意識発達においては「死」の領域を意味してる。歴史意識としては近現代的主体の死。OCOT情報では1989年からこの最終構成の領域に入っているとしてる。これは何かというと、ψ1~12までの構成をまるまる反転させる領域のことで、要は他者精神の世界。
人間の意識はノス(赤)が先手を取って動いているので、放っておくと、そのまま惰性でψ*2の流れの中に入って行ってしまう。それが今の僕たちの状況と考えるといい。これは、自己意識の基盤となっていた真の主体としてのψ5の位置を喪失するという意味だ。このような状況をOCOT情報は「人間の精神の中和」と呼んでいる。
つまり、精神が消え去ってしまうということ。決定的カオスだ。今の世界の状況、自分の心の状況を見れば、それは薄々と直感できるのではないかと思う。ニーチェ風に価値基盤の全崩壊、受動的ニヒリズムの蔓延化と言っていいかもしれない。
ただ、困ったことに、今の僕たちは現在の歴史発展の方向以外、人間の文明の進化のベクトルというものを想像することができないでいる。このままいくと、精神なき全きカオスが到来してくることになるわけだ。それを好む人はいいけど、好まない人もいるはずだ。だから、一つここらでオルタナティブを作らないといけないんじゃね?と、ヌーソロジーは言ってるわけだ。
それは、ドゥルーズ=ガタリが予見したように、ψ11後半のスキゾ化の方向が示唆している。最終構成において、ψ*2の方向へと侵入していくのではなく、そこで方向を捻って、自己意識の基盤であったψ5を奪回するために、ψ1→ψ3→ψ5の方向にある精神の位置を見つけ出すこと。これがヌーソロジーのいう「顕在化」の作業だと考えるといい。
これは、従来の意識の裏貼り側へと回りこむような意識の創造だ。哲学的に言うなら、超越論的なもの(人間の経験的意識を作り出していた無意識)の側へと、意識を反転させることを意味している。生がもたらす死ではなく、生をもたらす死を経験の俎上に上げていくということと言い換えてもいいだろう。
そして、この思考作業が同時に物質の秘密を明かしていく。ヌーソロジーではそういうシナリオになっている。
By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, ケイブコンパス, ドゥルーズ