6月 12 2019
Think totally different.
見えるもので見えないものを説明しようとするのではなく、
見えないもので見えるものを説明できるようになること。
奥行きの宇宙論とはそういうものだ。
これは先日話した「現象以前の一者とともにありながら、しかもそこに現象的多者を見る」という例の「双眼の士」の思考とも言える。
まず第一に「あるもの」を認識して、次にその根拠を考える―という思考ではダメなのだ。ヌース(創造的知性)は逆。自己の内的な位置に立ち、それが外にどう表現されているのかを考える。
実際、僕が経験したOCOT情報はすべてその文脈に沿っている。だからこそ得体の知れぬ異質性が漂っているわけだけどね。たとえば、元素については次のように語ってる。
●原子番号1 水素
・フタイ質がイチを持ち始める初めての反映
・進化の方向にある人間の思形の対化を等化に持っていく力と方向。
・イチの発露がタイカに交差する状態
●原子番号2 ヘリウム
・人間の意識における発露を持つものが発露を等化し、顕在化を内面に生み出すこと。変換作用。
何を言ってるかさっぱり分からないのではないかと思う。
僕も最初はそうだった。25年間の格闘の末、今なら少し解説ができる。
イチとは精神の位置といったような意味だ。彼らの世界では、精神がなければそこにはイチはない。
水素-ヘリウムの次元は「点球」とも呼ばれていて、それは僕らが日頃経験している物の象りとしての空間のことを意味している。言い換えるなら、触覚を通して感じる「かさばり」のことだ。
精神が自らの持続空間の中にこの物の象りの感覚を取り込む次元の知性への開示のことを「顕在化」と呼んでいると思えばいい。
OCOTによれば、人間の意識にはこの「顕在化」がまったく生まれていない。そりゃそうだ。持続空間という概念すらないのだから、精神の場所なんて思考のしようがない。
人間にはそうした精神の場所がまったく見えておらず、ただ漠然と物を知覚し、そこからアプリオリ(哲学でいうところの無意識の構成)によって自己意識を経験させられている。誰も自分で意識して自分になったわけじゃないからね。
OCOTは、そうした自己を組織化しているものが素粒子だと言ってる。元素は、その意味でいうなら、そのアプリオリとしての素粒子次元のもとになっているものだとも言える。
つまり、反転した世界では素粒子によって元素が作られているのではなく、元素によって素粒子が作られているってことだ。素粒子(人間の無意識)は精神の残響音のようなものとでも言いたげだ。そして、それは「―潜在的変換」でもある。宇宙が人間を「こっちだよ」と言って呼び戻している方向とでも言おうか。
だから、人間の知性が素粒子を実体として自らの持続の中で思考し、理解していくことができれば、そのプロセスがそのまま元素的なものへの生成へと繋がっていくってことになってくる。
このあたりは、ハイデガーなんかが言ってる「存在=アレーテイア(真理)」をおそろしいほどに詳細に語ってくれている感じだな・・・。
SFとして聴いても、最高に面白い話だと思うよ。
宇宙はトンデモないものなのだから、トンデモない発想をしないと、そりゃわからんよ。

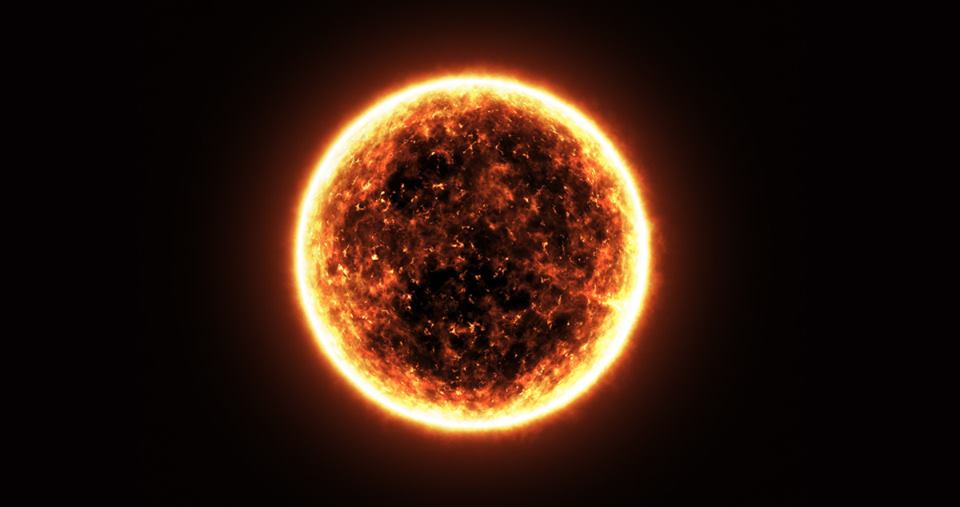






6月 19 2019
素粒子の全体像がようやく見えてきた
最近は等閑にしていた潜在化におけるΨ13~14の内部構成について考えている。
Ψ13~14はψ11~12の等化と中和の次元に当たるのだけど、これは自己側の無意識が他者側のΨ*11~12領域までアクセスしていくことを意味している。ここにレプトンの三世代を配置すると標準理論的に綺麗に収まるのだが、この領域が何を意味するのかが未だにハッキリとつかめていない。
物質粒子(フェルミオン)にはクォークとレプトンの二種類があり、それぞれが以下のような三世代を持つ。
・クォーク
uクォーク・dクォーク
sクォーク・cクォーク
tクォーク・bクォーク
・レプトン
電子・電子ニュートリノ
ミューオン・ミューオンニュートリノ
タウオン・タウオンニュートリノ
OCOT情報では人間の個体意識の構成はΨ11~12で完成され、それぞれ人間の意識の定質、性質と呼ばれる。そして、それらが電子とニュートリノの関係にあたる(『人神』や『シリウス革命』では電子とニュートリノはΨ5~6にしていたが、次元の多重性が見えてきたために現行のヌーソロジーでは大きく変更されている)。
そこから先にΨ13~14という段階があるのだが、ここが今ひとつ謎。クォークとレプトンが三世代存在していることと関係があるとの直感があるが、どうもうまく整理できない。
Ψ11~12はΨ *5~Ψ *6領域へと凝縮し、電子と電子ニュートリノの位置を作る。これはちょうどu,dクォーク(Ψ5~6)のウラに相当してくる。トップとボトムクォークもそこに重なっている。
この辺りはヒッグス場とも関係してくる。というのも、トップクォークやダウンクォークはヒッグス場の崩壊から出てくるとされているからだ。同時にWボゾンも絡んでる。弱い相互作用の場というのは様々な次元のレイヤーで入り組んでる。このあたりのことを正確に理解するためには最先端の素粒子物理学の正確な理解が必要なのだが、これがまた難しい・・・。
あと、面白いのは、ニュートリノには左巻きしか存在しないという実験事実だ。電子ニュートリノ・ミューオンニュートリノ・タウオンニュートリノに右巻きが存在しないということは、そこでは「対化=他者性」が生まれていないということを意味している。
つまり、Ψ13~14は「一者性」の温床のような領域になっており、ここで「自己意識は自己で閉じる仕組みを与えられている」と言い換えてもいい。対化としての自己性と他者性の等化の連続的な運動がそこで切断されている。
とりあえず大系観察子のケイブコンパスを使って、標準理論の素粒子群の布置を表してみた(下図参照)。
結構美しい。この構成だと超対称性は次元の交替化(赤と青の相互変換)の意味を持つことになる。
簡単に図を説明しておこう。
フェルミオンは超越論的主観性のシステムを表す。ボゾンはそのシステムを前提として働かされる人間の意識の様々な役割(カント的にいうなら感性・悟性・理性等)に当てることができる。この構成はSU(3)で構成され、それらの統覚(自己意識を「わたし」という主体意識で取りまとめる働き)を電子・電子ニュートリノがとりもつ。
こう考えると、レプトンの残りの2世代は、人間における死後の意識領域ということにでもなるだろうか…。
フェルミオンとはヌースの言葉でいうなら「垂質」の構造体だ。それは垂直的にレイヤー化した持続空間の階層性と言ってもいい。存在の思考が作るカタチの世界である。この思考が再開されるためには、まずは非局所的空間を「前」の中に発見するしかない。それがヌーソロジーが「奥行き」と呼ぶものだと思ってほしい。
By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, クォーク, ケイブコンパス, シリウス革命, ニュートリノ, 人類が神を見る日, 奥行き, 素粒子