11月 25 2008
時間と別れるための50の方法(53)
●4つの霊珠(たま)
七つの玉には7人の姫がついて守っておるのじゃぞ。
その姫たちが目覚めて、いよいよ岩戸開きの到来じゃ。
天と地がぐでんとひっくり返るぞ。
こころしてかかれよ。
今まで見えぬものが見えるようになり、見えたものが見えなくなるぞ。
あるものがなくなり、ないものが出現するぞ。
ちょっとヌーソロジーっぽくないコテコテの前振りではありますが、今まで説明してきた次元観察子ψ1~ψ8の構成をごくごく単純にまとめると下図1のような4重階層の球空間として表すことができます。これでヌース(旋回的知性)が7つの玉のうち4つをつかみ取ったことになります。もちろん、残りの3つの玉とは次元観察子ψ9〜ψ10、ψ11〜ψ12、ψ13〜ψ14のことです。
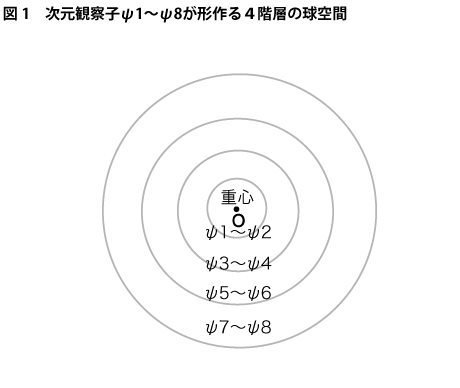
これら4つの球空間のうち、次元観察子ψ1~ψ2を除く三つの球空間はそれぞれが相互反転関係にあるペアを持っていると考えて下さい。そのペアが奇数系観察子と偶数系観察子が形作る球空間の関係に相当します。各球空間について再度まとめておきましょう。
1、第1のたま(点球)………次元観察子ψ1~ψ2(触覚空間?)
モノの内部を構成している球空間。モノがどんどん膨張していくようなイメージの方向が次元観察子ψ1。反対にモノがモノの中心方向に縮んでいくようなイメージの方向がψ2に当たる。結果的にミクロからマクロへの空間の膨張イメージがψ1となり、マクロからミクロへの空間の収縮イメージがψ2となる(下図2参照)。
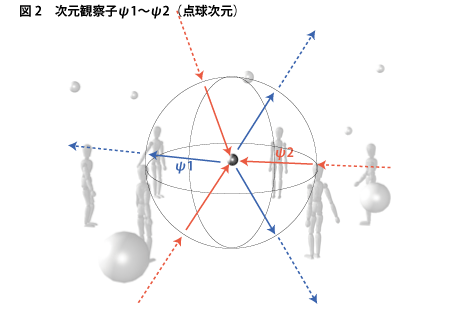
上で次元観察子ψ1~ψ2だけは相互反転性を持っていないと書きましたが、これはどういうことかと言うと、現在の人間の意識にはψ1とψ*1、ψ2とψ2がそれぞれ同じものに見えているために、球体の表面を単なる球面としてしか捉えることができません。これは自己側のψ1~ψ2と他者側のψ*1~ψ*2が相互に捻れを持った関係(キアスム)で認識されていないということです。このようなノッペリとした球体認識がψ3に始まる次元観察子の顕在化を抑止しています。ヌーソロジーではこの抑止状態のことを「止核(しかく)」と言います。比喩的に言えば、プレアデスに降ろされた錨のことです。この「止核」は端的に言えば「物質」という概念のことと考えるといいでしょう。
「止核」は人間の意識次元を安定して活動させるために真実の人間の意識が作り出しているものです。しかし、止核の力が強大になりすぎると人間の意識は精神の方向性を持つことが難しくなってきます。止核がもたらす最も大きな弊害の一つに尺度概念の絶対化が挙げられるでしょう。尺度は空間を均一的な場と見立て、モノが存在しないところにまで長さや面積、体積等の度量衡をあてがい、空間に潜在化している次元の差異を見えなくさせてしまいます。『人神/アドバンストエディション』にも書きましたが、例えば、科学者たちが「宇宙の大きさは半径約137億光年である」と言うとき、そこでイメージされている空間は目の前にあるパスケットボールを極限にまで膨張させたようなイメージの空間になっていることが分かるはずです。このイメージ形成はモノの内部の球空間の表象が、そのままモノの外部空間=ψ3や人間が生きる場=ψ5、さらには人間全体の生きる場=ψ7を闇で包み込んでいるも同然です。この尺度化の体制は今や地球の外部空間はおろか宇宙全体の空間までをも支配し、人間の意識を物質的な空間の中に閉じ込めてしまっているわけです。
このように空間を次元観察子ψ1~ψ2のみの中で思考することは、人間の空間認識がモノの内部に幽閉されているのと同じ意味を持っていることが分ります。モノの内部次元である点球は、そこには観測者は存在し得ない(つまり、見えない)という意味で光なき世界であり、点球の内部にすっぽりと包み込まれてしまって認識されている宇宙はある意味、すべて幻影世界と呼んでいいものです。しかし、ヌーソロジーの観点から言えば、これは意識進化のための必然だと考えられます。というのも、こうした尺度化の体制がミクロからマクロの全域に及んだとき、上次元が止核を解除し、人間の意識に最終構成を働きかけてくるような仕組みが精神構造の全体性には存在させられているからです。——鍋の底抜けたら、帰りましょ。というやつですね。
2、第2のたま(垂子)………次元観察子ψ3~ψ4(視覚空間?)
観測者がモノの周囲を巡ったときに、モノの外部を構成しているように認識されている球空間。この球空間には二通りのものがある。一つはモノの背景方向を半径とする球空間。もう一つはモノの手前方向を半径とする球空間。前者が次元観察子ψ3で後者が次元観察子ψ4。ψ3の球空間の内壁は見えるが、ψ4の球空間の内壁は見えない(下図3参照)。
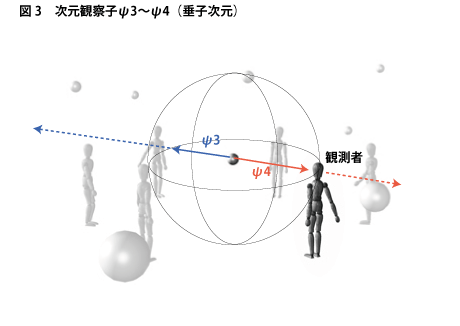
ψ3の球空間への方向性は、まずはモノの背景空間として出現してきます。この背景空間の登場によって、モノを「図」、背景を「地」としたモノの内部と外部の差異が出現してくることが分かります。このときモノの背後方向に無限の長さを持つと想定されている奥行きの線分は人間の外面では一点同一視され、4次元空間のルートを通してモノの中心点付近まで縮んで入り込んできます。いわゆる光のゼロベクトルです。これは人間の外面がモノの内部側に入り込んでくる最初のルートとなります。この空間ではモノにおける全表相の見えの記憶がイマージュ(ベルクソン)として蓄えられていると考えられます。結果、ψ3の球空間は一つのモノに対する主体の位置となります。
ψ4の球空間はψ3がψ*3によって相殺されて生まれる位置です。ψ4にとってはψ3が消え去っているわけですから、このψ4は意識がψ1~ψ2に戻されている領域という言い方もできますが、ψ3を経験したあとに戻されているという意味で、最初のψ1~ψ2とは位置的に若干の違いがあると考えて下さい。つまり、ψ1~ψ2では観測者は不在ですが、ψ4になると観測者が内面(対象の手前側の位置)に把握されるようになるということです。人間が一つのモノの外部に広がる3次元空間を描像するときには必ずそのどれか一方向に自分の目の位置を感じ取っているはずです。その目の位置がモノの周囲を動き回ることによってψ4が形成されているということになります。言うまでもなく、自分の目の位置というのはψ3とψ*3(自己の視野と他者の視野)があって、初めて存在できるものなのです。――つづく







12月 19 2008
時間と別れるための50の方法(59)
●霊(ひ)足りて、身着る場所へ
とりあえずこれで人間の存在論的な意味での無意識構造の母胎となる元止揚空間(次元観察子ψ7~ψ8)の描像に関する説明は終わりになりますが、最後にこの元止揚空間の次の段階となる次元観察子ψ9~ψ10について、予告編の意味も含めて少し書き記しておきます。
1、対化の交差について
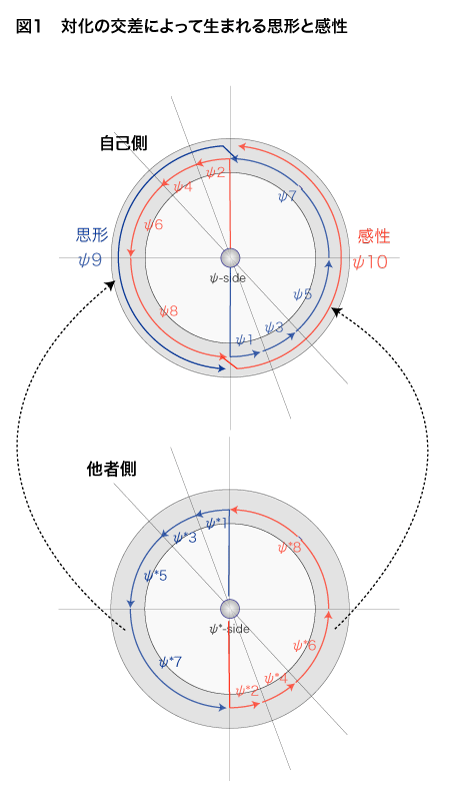
前回、ケイブコンパスで示した次元観察子ψ7~ψ8、ψ*7~ψ*8という双対的な構成のことを「元止揚の対化」と言います。早い話、これは自己側から見た人間の外面と内面(内在と外在の場所性)の総体と他者側から見たそれとの相互反転関係のことです。自他を構成する空間の間にこうした高次元の捻れ(4次元の捻れに相当します)が存在していることにより、精神は等化というその特性を用いてさらなる高次の差異を回転によって生産し、そこに「志向性(ノエシス)」という力の流動性を作り出すことが可能になってきます。
元止揚の対化(ψ7~ψ8、ψ*7~ψ*8)は、それこそ対極図にある「陰の中の陽、陽の中の陰」の関係のように、互いに互いの構造を反照させ合い、そこに複合的な構造をもたらしてきますが、こうした段階に元止揚が入ることをヌーソロジーでは「対化の交差(たいかのこうさ)」と言います。自他における人間の精神と付帯質という二組の対化が互いに交差を起こすということです。自己側から見た対化の交差の状態をケイブコンパスで示すと、おおよそ下図1のようになります。
この図1からも分かるように、対化の交差が作り出す方向性には基本的に二通りの流れが存在しています。一つは精神=ψ7が付帯質=ψ8を交差する方向性、もう一つは付帯質=ψ8が精神=ψ7を交差する方向性です。図からも分かるように、この二つの方向性は、互いの対化(精神と付帯質)の存在によって方向づけられているものであり、例えば、次元観察子ψ7のψ8への交差は裏で次元観察子ψ*7という片割れの精神が作用していることが原因となっていると考えて下さい。
この二通りの交差の部分の働きに対応するのが次元観察子ψ9とψ10で、ヌーソロジーではこれら両者をそれぞれ「人間の意識における思形(しけい)」と「人間の意識における感性(かんせい)」と呼びます。ここでわざわざ「人間の意識における」という形容句がついているのは、タカヒマラ自体には「ヒトの意識における思形と感性」や「真実の人間の意識における思形と感性」といったより上次元の思形や感性という働きが存在させられているからですが、それらについてはいずれまた詳しく説明していきますが、当面は、思形と感性という言葉が出てきたら、この次元観察子ψ9とψ10のことと考えて結構です。
2、思形と感性
思形と感性とは、簡単に言えば、外在を認識する意識と内在を認識する意識という言い方ができます。哲学の言葉で言えば、悟性と感性です。ベルクソン的に延長世界の認識と持続世界の認識と言い換えてもいいでしょう。思形は時空全体に首を突っ込んでいくことによって、時空を認識する力となっており、感性は精神に首を突っ込んでいくことによって、内在としての知覚や感情等を観察する力となっていると考えると分り易いかもしれません。
これら次元観察子ψ9~ψ10が持つ空間構造としての特徴は、元止揚の対化として存在していた内面=外面*、外面=内面*という双対性による調和的な位相の捻れが、少なくとも表面的は反古にされてしまうような働きを持っているということです。ケイブコンパスが示す矢印の構成からも直観的に分かるように、ψ9~ψ10段階に入ると、外面としての力が今度は外面*の方向を指向するようになり、また、内面としての力が同じく内面*の方向を指向するようになります。これによって、元止揚の対化が持っていた4値的な関係は見えなくさせられ、結局のところ、外面=外面*、内面=内面*という等化が起こり、自他においての外面と内面が共に同じものとして見なされるような空間構造を作り出してくるのです。
実際、わたしたちは自他の間においてモノの内部と外部の認識を共通なものとして相互了解しているはずです。モノの表面が単なる2次元の球面に見えているわけです。内部と外部の分節が起こっているわけですね。別の言い方をすれば、いわゆる内包空間として作用していた霊(たま=3次元球面)から、その一部がトポロジー的変換を受け、もの(3次元球体=点球)として顔を出してくるわけです。
もちろん、この内部/外部といった二項対立の認識回路は元止揚空間の上位に上書きされ地層化されているだけであって、基盤となる元止揚空間が完全に破壊されてしまうわけではありませんが、ただ、表層部にψ9~ψ10が被ってくることによって、元止揚空間の働きは無意識的な意識の回路として抑圧を受けざるを得ません。
細かい論証は新しく予定しているシリーズの『ケイブコンパス/4つの無意識機械』で書いていこうと思っていますが、この次元観察子ψ9~ψ10は、第56回の図2で示したように、ψ7~ψ8が自他の身体における「前-後」軸を中心とした空間認識の領域だとすれば、「左-右」軸へとその認識軸が回転を起こした世界と言うことができます。
3、左右とは5次元の方向である
これはやまと言葉風に言えば、「左(霊足り)」て「右(身着る)」世界への侵入とも言えます。「左」が霊足りて思形となった力が位置する方向で、「右」が身体を自我極として働かせるための感性が位置する方向です。左脳的な世界と右脳的世界と言った方が皆さんには分かり易いかもしれません。元止揚空間としてのψ7の力が確実化し、まさに霊が内包空間の中で充満に達するとき、4次元における個々の観察軸は前-後(自-他)を等化し、左-右方向へとその軸を遷移させ、今度はそこから全く別種の意識的な位相で世界を観察する力を持つということです。ここでいう、前-後、左-右とは、前にも言ったように身体における絶対的な前-後と左-右、いや、もっと言えば、すべての人間の身体にとっての前-後、左-右という方向性のことだと考えて下さい。ですから、実際のところ、左-右方向から世界を実像として見ることができる者など世界に一人も存在していません。これは実存的ではない第三者的な視線が人間の意識に発現してくることを意味しています。こうした第三者とはすなわち「客」のことですから、自己でも他者でもない客観者としての視線が客体を構成するためにここに登場してくることになります。この視線の在り処がヌーソロジーが説く5次元空間です(感性は5次元時空という言い方ができます)。
「直交性は観察を意味する」というヌーソロジーの鉄則からすれば、観察軸のこの左右方向への90度回転によって、精神は前-後軸が作り出していた場所の観察を可能にしているということになります。すなわち、奥行きを幅と同じもののようにして感覚化させている視線です。皆さんの意識の中にもこの左-右軸からの観察力が必ず働いているはずですから、それらが意識において何を行っているのか、その生態をより詳しく調べてみるといいでしょう。この視線は単に奥行きだけではなく、モノ概念や言語、さらには鏡像的自我といった人間の意識を構成するための様々な要素を構成させてくることになります。対化の交差とは言うなれば、人間の意識における内在的なものと超越的なものを結ぶ架橋となるものなのです。――つづく
By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 1 • Tags: ケイブコンパス, タカヒマラ, ベルクソン, 付帯質, 元止揚空間, 内面と外面