1月 5 2009
紀要用の原稿書き終了!!
今日から、2009年の仕事始めです。
さっそく昨年、依頼のあったM大の日本総合研究所の紀要に掲載する小論を仕上げました。
論題は「知覚正面における本性上の差異に関する一試論」です。
大森荘蔵、ベルクソン、メルロ=ポンティから1センテンスづつを引用し、
4次元時空に被投された知覚正面の状況について簡単な考察をしています。
ヌーソロジーでいう「人間の外面」の哲学的裏付けを取るには、
この大森荘蔵の「知覚正面」論はシンプルですが、とても重要な概念です。
知覚正面(大森荘蔵)→イマージュ(ベルクソン)→奥行き(メルロ=ポンティ)。
この三者を時間をキーワードにして横断させたところに「人間の外面」というヌーソロジーの重要な概念が立ち上がっています。
記憶とは脳ではなく、今みている光の中に蓄えられている——。
ってことなのかな。。。証明は難しいけどね。。







1月 16 2009
交信記録19940130-3
交信記録19940130-3
生命体が炭素を中心に構成されているのはなぜですか。
それは生命が次元進化の反映として生み出されているからですが、中和の交差が多くのものを作り出すためには必要だからです。中和とは自己と他者を生み出すための重畳した部分。
水とは何ですか。
中性質は表相を内面から生み出します。水とは表相によって変えられたものを内面に生み出します。人間の意識が人間を観察し調整しているところ。
酸化とはどういう意味があるのですか。
中和の交差の還元作用に当たります。
次元の方向性における6番目(炭素)と8番目(酸素)の関係はどういうものですか。
使われたところにあるものを交差させたところに戻すということです。
水素イオンとは。
中和の交差の表相を人間の意識に見えさせているもの。水素イオンそのものには進化を作り出すことはできませんが、水素イオンによって生み出された交差を持つものには進化を作り出すことができます。
水酸イオンとは。
中和の交差の表相を力に変えさせているもの。水素イオンが多いということは力を持つことができないということです。力とは進化の方向におけるすべての力。力を持つことができないというのは反性質が弱いということです。
■解説
OCOT情報によれば、原子番号3〜14までの元素界は人間の意識の覚醒が起こる次元を表していると言う。つまりトランスフォーマーの意識が作り出しているものだ。その意味でいえば、覚醒以前の人間の意識領域はすべて原子番号1番と2番の水素-ヘリウムの内部世界に幽閉されており、自然界の創造活動からは疎外されていると言っていい。つまり、人間という存在は自然界から一方的に贈与を受けるだけの存在であって、その本質はバタイユがいうように、世界を貪るだけ貪り尽くし、消尽するものたということである——太陽肛門としての人間。そこから排泄される熱、放射能、そしてエントロピー。
意識が水素-ヘリウム構造の中で流動している状態をヌーソロジーでは「潜在化の次元」と呼んでいる。本当は表に出るべきものが、裏に回って人知れず動いている。秘密の舞台裏。これが無意識というものだ。無意識の構造をはっきりと知性によってつかみ取ること。これによって、潜在化は顕在化へと裏返ることができる。無意識という概念が生まれてきたのは20世紀になってからのことだが、フロイトがその概念を提唱して以来、その詮索は、フッサール、ハイデガー等の現象学やベルクソンの哲学とも絡み合いながら、思想の世界では構造主義、ポスト構造主義へと発展してきた。しかし、残念ながらこの無意識構造が明確な構造を持って把握されたことはない。わずか晩年のラカンのみがその幾何学化に果敢に挑んだが、結局、誰一人その後を継承する者はなく、人間精神や意識への言及は相も変わらず、旧哲学の体制が紡ぎ出すジャーゴンによって糊塗されつづけ、重装備化された重苦しい観念の同一性の中で息絶えようとしている。
潜在的に作動しているもの——無意識構造。それを理念(イデア)と呼んでもいいが、この力はOCOT情報に従えば言語ではなく幾何学の中に宿っている。人間の意識の背景にこうした理念としての幾何学が潜んでいるからこそ、人間は主体と客体を持ち、自己と他者を持ち、希望と絶望を持っていると考えるのが自然だろう。この無意識の構造を支える幾何学を意味する概念が、他でもない、ヌーソロジーが次元観察子と呼んでいるものなのである。
一般に現代思想においては神秘思想に倣って人間は倒錯者として見なされる。この倒錯を正常な位置に戻すためには、再度、倒錯を行なうのが早道なのだが、倒錯する方向にも二つあるので、一歩道を誤るととんでもないことになる。幼児になること。倒錯者になること。分裂症になること。ニーチェ、バタイユ、ドゥルーズ=ガタリの系譜は軽やかにこの倒錯者への道を語るのだが、これは別に赤ちゃんプレイをしろ、オカマになれ、キチガイになれ、と言っているわけではない。彼らのいう倒錯者への道が具体的に何を指示しているかは残念ながら今ひとつ不明だが、この倒錯への意思をヌーソロジーの文脈に当てはめると、それは潜在化から顕在化への反転の意になると言える。つまり、次元観察子でいうところの偶数系先手の構成から奇数系先手への構造へ。付帯質ではなく、精神を目覚めさすこと。それだ。
今まで何度も示してきたように次元観察子はψ1〜ψ14、ψ*1〜ψ*14の総計28個の観察子で構成されている。人間の意識ではあくまでも偶数系観察子が先手で動いており、奇数系は後手に回っている。偶数系先手の意識は人間の内面の意識と呼ばれ、これは外在世界、物質世界を流動している言語としての理性の活動を司っている意識のことだ。一方、人間の外面の意識は奇数先手で流動しており、これが一般に言われている無意識に相当している。無意識は等化の連なりであり、ドゥルーズのいうように、絶えず、表裏を捻り合わせながら襞を作り上げ、内在面を形成している。折り紙が元を正せば一枚の平面であるように、この複雑な襞も滑降する一つの連続した面であり、意識はこのn次元連続体としての内在面上をガラス面の上を滑る氷のように滑走していっている。
人間の内面の意識がなぞる順番 ψ2→ψ1→ψ4→ψ3→………
人間の外面の意識がなぞる順番 ψ1→ψ2→ψ3→ψ4→………
一方、偶数系の系列とは中和作用の連なりであり、それは空間の同質性として作用している。巨大な同一性の大海のことである。平板的でのっぺらぼうな差異なき漆黒の海。この大海に迷い込んだ偶数系先手の意識には自他の意識に方向性の差異があるということは分らない。もちろん、ここには空間の差異もない。外と内の差異もない。もちろん、意識が創造に関わるルートも見えることはない。時空という物質世界の中ですべてを思考し、すべてを説明してしまおうとする貪欲かつ保守的な理性の帝国だ。これが唯物論的な科学主義に代表される偶数先手の中和における人間の意識の在り方と考えるといい。もちろんこの同一性から差異化を諮ろうとする哲学や宗教、芸術の試みもあるが、それらは中和が先手を持った上での後手としての等化の運動ゆえに、力が極めてひ弱い。このひ弱さは後手すなわち反動者として運命づけられたものであり、資本主義の精神回路においてそれらが科学よりも優位に立つことはあり得ないだろう。
ごたくを並べるのはこのくらいにして、交信記録の解説に入ろう。
まずは、潜在化と顕在化の次元についてだが、これらは物質世界では次のようなものとして反映されていると考えて欲しい(理由はヌーソロジー本論の中で解説していくことになります)。
1、潜在化の次元=素粒子構造(ボゾンとフェルミオン)
2、顕在化の次元=次元観察子ψ1〜ψ14はそのまま原子番号に対応し、原子番号1番の水素から14番のケイ素までの元素に反映されている。
よって、上の交信記録にある内容は主に元素についての内容なので、顕在化の次元と関わりが深いことになる。上の内容のすべてを説明するのは大変なので、とりあえずは、水素イオンと水酸イオンについて簡単な解説をしておこうと思う。
水素イオンと水酸イオンは、ご存知の通り化学ではそれぞれ酸とアルカリの原因となるものとされている。水素イオンはH+、水酸イオンはOH-という状態で、水分子H2Oの電離状態として存在している。ここに次元観察子の概念を当てはめると、水素は原子番号1、酸素は原子番号8であることから、水素分子は点球次元における対化(ψ1とψ*1)、酸素はψ8(転換位置)、プラスイオンとマイナスイオンは潜在化におけるψ3とψ4に対応していることが分る。つまり、イオンとは顕在化が作り出したカタチに対する人間の意識が持った不安定部分の活動を意味していると考えられる。プラスの電荷は人間の内面認識としてのモノ、すなわち客体意識のことで、一方のマイナスは外面認識してのモノ、すなわち主体意識のことだ(下図1参照)。
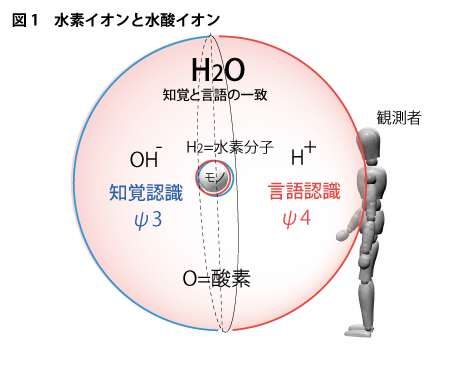
この図の補足説明をしておくと、この場合、O=酸素が外在時空で、H2=水素分子がモノだと考えるといい。モノがH2というように二つの水素原子して表されているのは、モノが必然的に自己と他者という二つの対峙する方向性を持たされているからと考えるといい。すなわち、わたしが見ているモノか、あなたが見ているモノかの二つだ。これは、言い換えれば、人間の外面として知覚されているモノか、人間の内面に想像されているモノかということでもあるのだが、すでに「時間と分かれるための50の方法」を十分に読みこなした方には、これらが客体側としてのモノと主体側としてのモノに当たることはある程度察しがつくことだろう。
目の前のモノに相互反転性を与えてみよう。まずはしっかりと見えているモノがある。今度はその球空間の表面の輪郭だけを取って、例によって中心点にまで縮め、そこで反転させ膨らまし、もとの輪郭の大きさまで持ってくる。これで相互反転したモノのイメージのできあがりだ。裏返ったモノの輪郭の方は元のモノの表面の裏面に反転し、見えなくなっているのが分かるだろう。
見えないのになぜ客体としての存在感覚が意識に生まれているのか——それは人間の内面が言葉によって支えられている領域だからだと考えるといい。人間の内面には知覚はないのでモノは存在していないのだが、言語があたかもモノが存在するかのように意識に錯覚を与えている。この言語の場の理念として活動しているのが、水素イオンとしてのH+である。上に書いたように、マイナスの電荷は潜在化においてψ3(人間の外面)、プラスの電荷は同じく潜在化においてはψ4(人間の内面)として働いている。以上、まとめると次のようになる。
H+(水素イオン)=モノ一つを名指している言語の位置。
OH-(水酸イオン)=時空上のモノ一つに対する知覚(主体)の位置。
H2O(水)=知覚と言語の一致。すなわち時空上の一個のモノという認識のカタチ。
こうした構造から見ても分るように、水は人間の内面と外面の意識の結節点のカタチであり、精神の方向性がニュートラルな状態としての空間、つまり、客観時空に置かれた一つのモノという理念的構成の射影ということになる。 即自としてのモノ(観測者抜きでも独立に存在していると思われているモノ)と対自としてのモノ(観測者が知覚していることによって存在となり得ているモノ)の一致点という言い方ができるだろう。タカヒマラ全体からすると始まり=1と終わり=8をつなぐものの原型である。OCOTたちが水のことを別名、「脈質(みゃくしつ)」と呼んでいるのはこのような理由に拠る。
——ここからは私的雑感。あまり物質的な生き方をすると血液が酸性になるぞ。外面優位の意識を志せば身体は自ずと健康になる。ってのはあまりに単純な考え方。人間は内面方向に負荷をかけられている。つまり、内面に負荷をかけなければ外面の発達は望めないのだ。だから、オレは適度な不健全さを生きる。適度な物質性を生きる。健全さを先手に取るとロクなことにならない。黒を極めて初めて白に至れるのだぁ〜。べらぼうめってんだ。
By kohsen • 04_シリウスファイル解説 • 5 • Tags: タカヒマラ, ドゥルーズ, ニーチェ, ハイデガー, フロイト, ベルクソン, ラカン, 中性質, 付帯質, 内面と外面, 素粒子, 表相