10月 12 2008
時間と別れるための50の方法(43)
●ψ*6上でψ5はどのように見えるのか――位置の等化の風景
わたしが自分の周囲に広大な空間の広がりを意識しているとき、その広がり自体が人間の内面*としてのψ*6になっているということを前々回にお話しました。このとき実際に見えている人間の外面としての知覚球体=ψ5自体は、何度も言うように奥行きが同一視されることによって超ミクロの微小領域の中に3次元球面として丸められており、ψ*6が意味する時空の原点Oに貼り付いたようにして入り込んでいます。
このように、次元観察子という概念を通して見ると、僕らが普段「わたしを中心とする空間の広がり」と何気に称している空間は「わたし」を規定するψ5と、「わたし」からの広がりを規定するψ*6が二重に重なり合うことによって成り立っていることが分かってきます。ヌーソロジーの考え方からすれば、前者は哲学者たちが実存(知覚の場所)と呼んでいるもの、後者は科学者たちが実存(物質の場所)と呼んでいるものにとても似ていると言えます。
また、このような空間の二重性を前提におくことによって、「現時刻」という瞬間性の中にすべての時間が集約された形で現象化している人間の意識の在り方をうまく説明することができるようになります。つまり、周囲の空間を時空=ψ*6として捉えているときには、その中心点では刻一刻と時間が刻まれ、毎瞬、毎瞬という点時刻があたかも車窓から見る風景のようにあっと言う間に過去へと流れ去って行き、その反対に周囲の空間を自分自身=ψ5として捉えたときは、そこでは過去、現在、未来へと至る時間はすべてその知覚球体の直径の中に4次元空間として凝縮されおり、そこには、永遠の現在が現れるというからくりになっているわけです。人間の意識において、瞬間と持続が「今」という現象において重なり合い、想起や直感がつねに「現在」として起こるのも、人間という存在が4次元時空と4次元空間が持つこのような二重性の接点として存在させられているからでしょう。
さて、時空*=ψ*6の原点にこうして知覚球面=ψ5が貼り付いているとするならば、僕らが時空として世界を眺望したとき、周囲の風景のいたるところに知覚球面が張り付いていても不思議ではありません。原点とは単に便宜上定められたものであって、時空上のどの位置であろうが原点となり得るからです。たとえば、3日前のこの同じ時刻にもわたしはこの椅子に座っていたとします。その時間を原点と考えれば「いつでも今」としての知覚球体はその3日前に移動していることになります。このときは文字通り主体が三日前にタイムトラベルを行っているわけです。物理的に言えば、当然、そのときの光は3光日(光速度で進んで3日かかる距離)の彼方に飛び去っていることでしょうが、奥行き方向はψ5においては常に同一視されているわけですから、知覚球体自体は時間の経過に対して何の影響も受けません。
では、空間的な移動の方はどうでしょうか。あそこに見えるビルの屋上を時空の原点としよう、と思えば、そこに「どこでもここ」の知覚球体は一瞬にして移動することが可能です。もっとも、このときは時間の移動とは違って、3次元球面として表された知覚球体内部では、原点の空間的移動(x,y,z方向への並進運動)に伴って3次元球面上でそれぞれの3方向への回転が起こることになります。しかし、知覚球体自体としての3次元球面自体はやはり全く同一のものです。
つまり何が言いたいのかと言うと、知覚球体(3次元球面とその自転軸)としての「自己=ψ5」が「いつでも今、どこでもここ」としての存在ならば、時空認識の中ではあらゆるところに偏在することができるということです。となれば、時空上のすべての点は客体であると同時に主体と呼んでいいものになります。このことは、「真の主体は客体の中に息づいている」というベルクソンの達観の幾何学的説明に相当していますが、こうした「遍くわたし」の様子を『人神/アドバンストエディション』では空海の言葉を借用して「即身」と表現しました。
重々にして帝網のごとくなるを即身と名づく――空海が『即身成仏義』で著したこの言葉は華厳経に登場するパールネットワークのイメージを彷彿とさせます。重々帝網とは、いかなる部分にも全体が映り込み、無際限にその像が反射し合っているような状態のことを言います。今風に言えばホログラフィーやフラクタルのイメージです。即身成仏というと、物質概念にまみれた僕らはすぐに即身仏を連想して、お寺の中でミイラ化しているお坊さんを連想しますが、空海が説いた意味は全く違います。もともとサンスクリッド語での「成仏(アビサンボーディ)」という言葉は「仏に成る」ということではなく、「仏である」ことの意で、仏であることとは「現等覚(げんとうかく)」のことであるとされています。現等覚とは読んで字のごとく「あらゆるものが等しいものとして見える」ということです。いわゆる差取り(悟り)ですね。まさに、重々帝網の風景とは、いつでも今、どこでもこことしての、即身成仏の姿そのものであるわけです。
ヌーソロジーではψ5が人間の意識に顕在化を起こした状態を「位置の等化」と言いますが、この状況はまさにこの空海が語った「即身成仏」の風景に酷似しています。主体の位置と客体の位置が同一のものに感じられてきたとき、世界はどのように見えなければならないか——それはまさしく空海が言うように、世界のあらゆるところに世界自身が重々帝網を為して映り込むということです。しかし、こうした描写だけではまだ自我の拠点たる時空概念を解体させるほどの意味の強度は生まれません。見るものは見られるものである、主体は客体の中にいる、これら過去の神秘家や哲学者たちの達観が人間の意識を変えるだけの力を持てなかったのも、その意味の強度に不足していたからだと言えるでしょう。問題はこうした達観をどのようにして僕らの現実的な知識に接続させていくかということなのです。——つづく







10月 16 2008
時間と別れるための50の方法(44)
●スピノール登場
(前回のつづき)この接続を達成するためには、やはり、そのときの空間の構造が重要なカギを握っているのではないかと思います。位置の等化=次元観察子ψ5の幾何学的構造とは時空上のあらゆる点に貼り付つけることができる超ミクロの3次元球面とその自転軸のことだったことを思い出して下さい。もし、こうした空間構造を持つ何ものかが科学者たちにとっての実存として実際に目の前の時空に存在しているのならば、それこそヌーソロジーが描像している自己という存在の場所性が多くの人に合意形成を得ている従来の科学体系と確固とした連結を伴ってこの現実世界に接続してくることになります。つまり、宗教のような超越的な言説、哲学のような観念的な言説を持ち込まずとも、人間存在に対する見方を今までの人間の現実の中から全く別のものへと変革させていける可能性が出てくるわけです。
時空上のあらゆる点に貼り付いた超ミクロの大きさの3次元球面とその自転軸――ヌーソロジーの考え方からすれば、これが「わたし」自身の正体でもあるわけですが、この4次元方向を向いた回転軸はおそらく物理学者たちがスピノールと呼んでいるものではないかと考えられます。これははっきり言ってとても非常識な内容です。ですから、それだけに強度もあるので、再度、強度を強調してリフレインしておきます。――奥行きの同一視によって長さ無限小にまで縮められた4次元軸としての観測者の絶対的前方向、これが物理学者たちがスピノールと呼んでいるものの正体だと考えられます。
もしこの予想が正当性を持つことになれば、僕らは物質と精神の結節点らしきものを初めて描像することに成功したことになるでしょう。というのも、スピノールとは物理学では物質を作る元となっている電子やクォークの自転角運動量(スピン)として登場してくるからです。つまり、人間の外面としての働きである持続-記憶や未来に対する直感はひょっとすると電子やクォークそのものの中にそのすべてが蓄えられているのかもしれない、ということです。
ということで、スピノールそのものの話に入る前に、電子の自転角運動量という概念について物理学がどう語っているか簡単にダイジェストしてみます。自転角運動量といってもよく分からない人もいるでしょうから、まずは通常の物体の角運動量について簡単に説明しておきましょう。
角運動量とは回転している物体が持っている運動量のことを言います。通常の運動量pは質量mと速度vの積mvで表されますが、角運動量の場合はこの運動量pに回転している円の半径rを掛け合わせ、
L=p×r(ベクトルの積です)
角運動量 : L 運動量 : p=mv 回転半径 : r
として表されます。角運動量はベクトル量なので当然、方向を持ち、この方向は回転面に対して垂直な方向、つまり回転軸の方向に現れます。例えば車輪が回っているとするとその車軸の方向ですね。通常の物体の回転はモノが回っているわけですから、その回転は群でいうと2次元回転群SO(2)です。このとき、軸は回転面x-yに対して垂直なz方向に立ち上がり、その方向に自転角運動量ベクトルを形作ってくるわけです(下図1参照)。
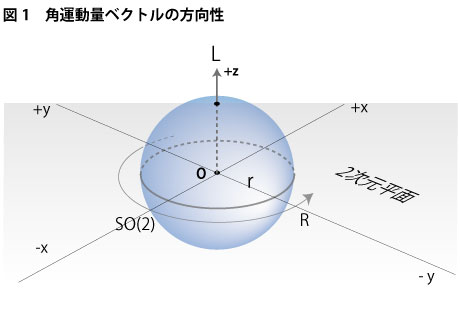
これは「回転とは等化の本質である」というヌーソロジーの論理を使えば、回転という運動にによってx軸とy軸が等化され(対称性を持ち)、2次元から3次元方向にz軸という方向性を作った、という言い方ができます。レベルは低いですが一種のアセンション(次元上昇)です。回転運動が持っているこのような次元上昇の仕組みをまずはここでしっかりと頭に入れておいていただければと思います。というのも、ヌーソロジーが説くヌース(旋回的知性)とは、回転(等化)によって認識の視点を次元上昇させていく知性の在り方のことを言うからです。その意味で言えば、通常の自転角運動量とは2次元に対する観察子位置を3次元に作り出すための負荷ということになるのかもしれません。次元観察子で言えば、ψ1~ψ2レベルからψ3~ψ4レベルへの意識の侵入力です。
まぁ、このへんのヌーソロジー自体の内容は後に回すとして、話を元のスピンに戻しましょう。
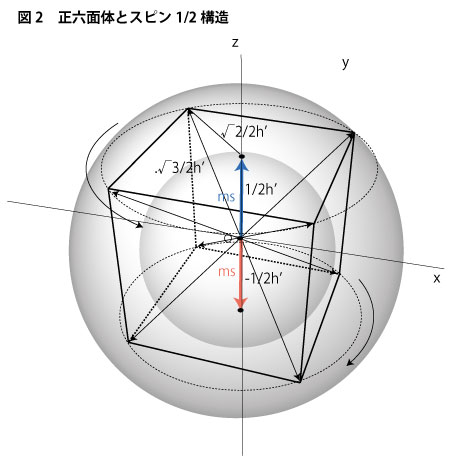
一般に電子やクォークも自転していると考えられています。ここで「一般に」と言ったのは、厳密にはこれらの粒子の自転の場が3次元空間ではなく内部空間と呼ばれている描像不能な場所なので、果たしてそれらの自転を通常の物体の自転のように考えていいかどうかが分らないからです。しかし、回転の性質を持っているといういう意味ではやはり角運動量が存在しています。このときの角運動量がスピン角運動量と呼ばれているものです。スピン角運動量は磁場方向の成分(スピン量子数msと呼ばれます)を取ると常に一定となっており、その値は±1/2h’(h’=h/2π)です(hはプランク定数で光1振動分のエネルギーを表します)。ヌースでもよく話が出てくる「スピン1/2」というのはこの値のことを指しています。
物理学の言葉が一挙に出てきて、ちょっと話が分かりにくくなったかもしれないので、イメージが涌くようにスピンの詳細を図で説明しておきます。
電子やクォークが自転していると言っても、その自転軸はピンッと直立不動で立っているわけではありません。上図2に示すようにちょうど回転力が衰えたときのコマのように回転軸自体が傾斜して回っています。このとき傾斜軸の角運動量は√3/2h’とされています。そして、このとき起こっている傾斜軸自体の回転におけるz方向の成分がスピン量子数と呼ばれるものです。ピタゴラスの定理からz方向の成分の値がさきほどご紹介したように±1/2h’になっているのが簡単に分ると思います。この比の関係性はちょうど直径√3の長さを持つ球体に正六面体を内接させて、その4本の立体対角線をすべて「等化」させるような回転が起こっていると考えればイメージが簡単になります。つまり、この回転の磁場方向の成分を表すスピン量子数±1/2という値は、この正六面体に内接する球体の半径の大きさに対応してくるわけです。このように、電子やクォークのスピンの成り立ちには1:√2:.√3という正六面体の構成比が深く関係しているわけです。このことは、物質の根底が極めてシンプルな幾何学比によって支配されているということを示唆しています。
――つづく
By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 7 • Tags: アセンション, クォーク, 位置の等化, 内面と外面