11月 4 2014
分離意識は〈繰り広げ〉、未分離意識は〈巻き込み〉
主客未分離の意識を意識と呼べるかどうかは別として、時空を主客分離の意識の場とするなら、未分離意識の場が数学的形式として表現されたものが複素空間です。
ベルクソンがいうように、僕たちは、ほんとうは、物がある場所において物を知覚しています。知覚は僕らを一気に物の中に置いているということです。今まで、このような構図が数学的形式として表現されることはありませんでした。この様子を複素空間として考えることで、意識と物質のつながりを構造として思考していくことが可能になってきます。
ここではベルクソンがいう主観性の線(奥行き)は虚軸として表されます。この虚軸には、感覚性や記憶内容としての記憶、さらには収縮としての記憶がならんでいると考えられます。これらはボゾンやフェルミオンといった素粒子の分類の中で表されていくことになると予想しています。
複素空間は時空から見れば回転しているように見えます。この回転が時間と空間の関数として表されたものが波動関数ψ(x,t)です。これは時空と複素空間の接点の役割を果たしている表相(=視覚表象の位置)を発出点として、意識が持つ可能的次元を形成するための運動だと考えられます。
わたしたちの経験は、この表象を境界として、時空と複素空間に分化した意識の二つの方向性の混合において成り立っていると言えます。この混合をベルクソンが言うように注意深く分けなくてはいけません。
そのためには世界を時空と複素空間という二つの空間形式のレイヤーとして見る知性が必要になってきます。この空間のメタ知覚が生まれてくれば、もはや、物質と精神は別々のものとは見えなくなってくるでしょう。
日本人は、遥か古代にこうした空間知覚を持っていたのではないかと僕なんかは想像しています。たとえば、「先代旧事本紀」が伝える十種神宝には、このレイヤー空間の仕組みが、鏡と剣と玉という象徴を用いて、詳しく記述されています。古代の日本人が持っていた物=霊の思想を現代に再び、蘇らせることが必要です。
ドゥルーズの表現で言えば、複素空間は〈巻き込み〉の空間です。一方、時間と空間は〈繰り広げ〉の空間です。両者はどちらが先行しているか甲乙つけがたい関係にありますが、はっきり言えるのは、現在の人間の認識においては、時間と空間が先行しているということです。巻き込みの空間は無意識化しているということです。
この先行性のために、複素空間は時間と空間に対して、圧が低い状態になっていて、ちょうど台風のように、時間と空間として出現している人間の意識を内部に巻き込んでいます。光子なんかはその巻き込みの最初の部分です。しかし、この巻き込みにおいては、自己と他者の渦は互いに逆向きになっていて、そこに二つの主観性が立ち上がっています。光子で言えば、スピンの固有値の1と−1がそれに当たります。
問題はこの二つの主観性が、複素空間の内部に存在する高次元のシステムによって、元の〈繰り広げ〉の場へと同一化させられて、吐き出されているところにあります。〈繰り広げ〉と〈巻き込み〉が反復のループを作っているわけですね。これがフロイトやラカンなんかがいう無意識の反復のシステムです。
この反復回路を切断して、この存在のループから抜け出すためには、先行性を時間と空間ではなく、複素空間の方に持たせる必要があります。それがヌーソロジーでいう「顕在化」です。「反転の創造空間」というやつですね。

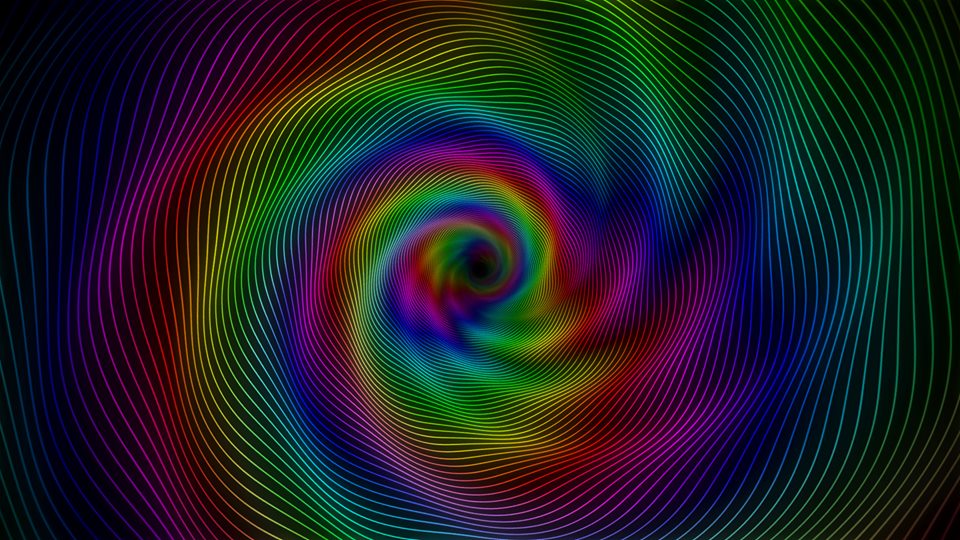






12月 24 2014
ヌースレクチャー#3のためのドゥルーズ哲学の予備知識——その3
3.ドゥルーズが研究した哲学者たちとそのキーワード・「ヒューム」/経験論」
『差異と反復』を発表する前の初期のドゥルーズはヒューム、ベルクソン、スピノザ、ニーチェといった哲学者たちの思想を研究していったんだけど、『差異と反復』で結晶化してくるドゥルーズ哲学の形(なり)を見ると、ドゥルーズは半ば確信犯的にこれらの哲学者たちを追いかけていったのだな、ということが想像されてくるんだよね。ここで「確信犯的」と言ってるのは、ドゥルーズには実は最初から自分が構築していくべき哲学のビジョンというものが明確にあって、その構築に向けて必要となる哲学者たちをチョイスし、これから自分が作り上げるべき思想に沿って、彼らの思考の足跡を分析、解釈していったふしがある、ということなの。麻雀で言う「決め打ち」ってやつかな^^。そして、引きが強いドゥルーズは自分の直感通りに牌を引いてきた。もちろん、最終的に「ロン!!」というところまでは行けなかったのだけど、僕的にはドゥルーズは役満をテンパってると思ってる。あとは世界が当たり牌を振り込んでくれるのを待つのみってところ。そこでウラドラの役割を果たすのがヌーソロジーかもしれない。。上がりのオマケがポコポコついてくる。ダブル役満!! トリプル役満!!\(^o^)/ ってな感じで(笑)。
で、若き日のドゥルーズが「確信犯的」に何を目論んでいたのか、ということなんだけど、これは一言でいうなら「主体性の哲学からの脱却」と言っていいと思うよ。「主体性の哲学」とは、簡単に言えば、いつも「オレ、オレ」とか「わたし、わたし」といった囁き声が中心にあって、そうしたかしましい自我中心体から抜け出ることのできない思考から組み立てられた哲学、のこと。「われ思うゆえにわれあり」と言い放ったデカルトの哲学などはその典型だね。こうした自我中心の哲学を解体すること。ドゥルーズの思考はスタートから、そこだけに照準を向けて蠢めき出したように見えるんだよね。
そこで最初に研究したのがヒュームという哲学者だった。何でヒュームかというと、ヒュームは「経験論」の哲学者として「合理論」の哲学者であるデカルトを徹底して批判してたから。経験論とは、一言でいえば、主体は経験によって立ち上がってくると考える哲学のこと。デカルトのように「我」が理性とともに最初から意識を支配しているのではなく、主体(人間の心)というものは、本来、経験の寄せ集めのようなものでしかなく「知覚の束」として立ち上がってくるとする考え方。「わたし」が世界を経験しているのではなく、世界の経験が「わたし」を作ってるという考え方だね。
こうした経験論の哲学で重要視されるのは、理性によって客観化された世界の事物云々ではなく、主観によって現実的に経験されている知覚世界の方であり、またその知覚とともに活動している情念の力の方ということになる。実際、ヒュームは「理性は情念の奴隷であり、そうあるべきである」とまで言ってるんだよね。そして、否定しがたい事実として、僕ら生身の人間にとっても、情念の力の方が理性の力よりもいい意味でも悪い意味でも勝ってるというのは明白なところ。ここに、すでに主観的なものの方向に意識の脱出口を求めるドゥルーズの思考の萌芽があるんだよね。「合理論」より「経験論」の重視。客観(理性)より主観(感性)の重視(正確には「主体なき主観」といった方がいいけど)。これがまずドゥルーズの第一の立ち位置と思ってもらえばいいよ。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: デカルト, ドゥルーズ, ニーチェ, ヒューム, ベルクソン, 差異と反復