11月 21 2008
時間と別れるための50の方法(52)
●相互反転した二つの客観の位置
顕在化した次元観察子ψ7とψ8。前回までの話でこれら両者の関係が客観的な点概念と時空概念の関係であり、その3次元世界への射影が僕らが陽子と中性子と呼ぶものになっているという結論を引き出してきたわけですが、もっとシンプルに言ってしまえば、単に人間全体の身体における「前」が陽子で、「後」が中性子だということになります。つまり、「前」は潰されて点の中に入り込んでおり、「後」は広げられてその周囲を囲い込む広大な空間となっているということです。あまりに単純すぎて、僕自身この描像に行き着いたときは驚愕すると同時に拍子抜けしたものです。その描像を皆さんも理解していただけるように、第49回で示した図2を使って再度、次元観察子ψ7とψ8の関係を示してみることにします(下図1参照)。
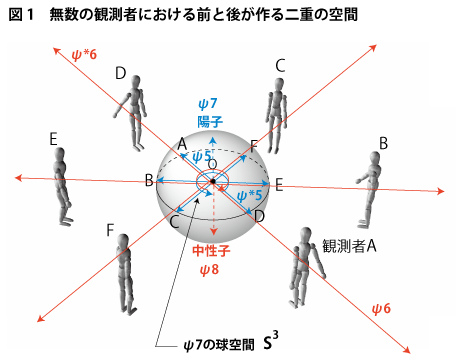
キアスムの関係をそのまま図示しているのでちょっと分りにくいかもしれませんが、言わんとせんとするところは極めて単純明解なことが分るでしょう。例えば、観測者Aにおける絶対的「前」は青い矢印で示したψ5のスピノールの部分に集約されて入り込んできています。すると、自動的にその絶対的「後」は原点Oを挟んでψ5の反対方向となる赤い矢印で描いたψ6の矢印に対応してくることになります。結果、ψ7とψ8はこのψ5とψ6の関係を形作る2本の矢印を、モノ(点でもよい)の周囲を取り込んだ無数の観測者の位置に交差させるように回転させていけばいい訳ですから、図2に示したような様子になります。陽子のアイソスピンはψ5-ψ*5の等化回転を一本のスピノールに集約させ、同様に中性子のアイソスピンはψ6-ψ*6を同一化させる回転を一本のスピノールに集約させています。結果的に、このアイソスピンの軸を3軸回転(SU(2)になります)させれば、相互反転した二つの3次元球面が形作られることになります。このときの二つの球空間が次元観察子ψ7とψ8の球空間に対応します。ψ7が客観的な点概念、ψ8が客観的な時空概念という意味が容易に理解できるのではないかと思います。
人間の内面の意識にとっては、この二つの球空間には半径無限小か無限大かという違いが出てきますが、人間の外面認識は時間距離tが存在しない永遠の領域なので、ψ8は単にψ7の反映にすぎず同じく無限小空間の中で構成された形で見えることになります。このような意味を付加させて図1を書き直したものが下図2です。3次元球面の相互反転関係と陽子と中性子がともにミクロ方向に重なり合って形成されている様子と、その意味が何となくは理解していただけるのではないかと思います。
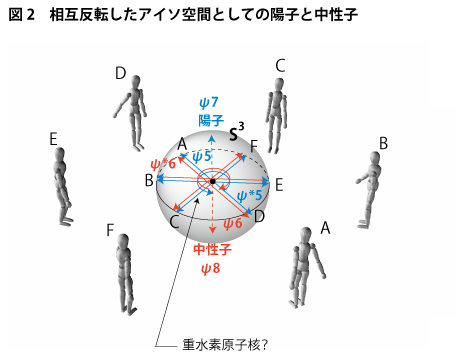
さて、ここで付け加えることがあるとすれば、人間の外面の意識が顕在化してくると観測者の身体の位置は対象の中心点Oと同じ位置として見なされてくるということです。人間の外面においては奥行き方向はどこも同じ位置であるので、対象の中心点に自分がいるという感覚が自然な感覚に思えてくるようになります。このような認識で身体の位置が捉えられたとき、この位置のことをヌーソロジーでは「重心(じゅうしん)」と呼んでいます。重心とはヌーソロジーの理論構成全体から言えば、精神構造におけるあらゆる対化の等化を行なっていくための変換の中点という意味ですが、この次元観察子ψ7〜ψ8段階では、人間の内面と外面を相互変換させるための支点というぐらいの意味で解釈しておけばよいと思います。重心はまたOCOT情報では神の定義ともされています。
重心とは何ですか。
地球と太陽の交点。あらゆるものの交点。交点が神。神が交点。(シリウスファイル)
重心感覚という表現もあるように、OCOT情報によれば、この「重心」は字義通り、僕らが物体の重心と呼ぶもののことでもあるようです。重力や質量の本質がヌーソロジー的に何か分ってくれば、OCOT情報のいわんとするところがより明確になってくるでしょう。地球と太陽の交点という言い回しも何やら意味深で興味深いところです。
本当の身体的位置が重心であり、それが人間の内面と外面の変換点そのものだとすれば、図1や図2に示したような形で把握されている僕らの一般的な身体位置のイメージとは一体何なのでしょうか。これはOCOT情報では「転換位置(転換位置)」と呼ばれます。いわゆる物質的身体のことです。転換位置は精神が等化作用を進めていくときに、その反映として作り出された中和の力が何層にも多層化されていくところと呼び変えてもいいかもしれません。物質側が等化作用(精神)の多層化ならば、肉体側は中和作用(付帯質)の焦点化と言い換えることができると思います。タカヒマラの精神構造は次元観察子ψに始まって、大系観察子Ω、脈性観察子φというように、数えきれない等化と中和の作用の階層構造を持っているので、その関係性が外界の物質構造全般と人間の肉体を構成している物質構造の違いとなって現れてきます。その意味で言えば、現代医学はこうした、単なる物質と人間を構成する物質のその次元的な差異が全く見えていないと言えます。
別の言い方をすれば、転換位置とは人間の内面の意識における身体の把握の仕方にすぎず、この身体には裏身体とも呼べるような本当の身体が存在しているということでもあります。それは言うまでもなく、人間の外面としての身体性のことであり、その位置は人間の内面の意識においてはモノの中心点にあるということなのです。転換位置としての身体認識は、主体が他者の身体と空間の関係性を見て、その様子を自分の身体と空間の関係に上書きすることによって生まれてきているものにすぎません。次元観察子で言えば、ψ5がψ6を見て、ψ5にψ*6のイメージを重ね合わせてしまうということです。想像的自我の土台を作るということですね。『人神/アドバンストエディション』ではこのへんの仕組みを次のように書きました。
——つまり、「君の前」がいつのまにか「僕の後ろ」とすり替えられてしまい、君は他者にとっての他者として自分を把握してしまっているのだ。君が前の集まりとして感じている空間、僕がいくら前には距離がないと言っても、いや、現にあるじゃないかと言って、前に3次元の奥行き感を作り出している思考性、それが君自身の自我の本性であり、ここでψ*6と呼んでいる次元観察子のことなのだ。つまり、君も僕も「前」を「前」として見ることができず、互いの「前」を相手側の「後ろ」として見て、自分からの広がりを想像的に認識してしまっているということだ。これが鏡像交換、想像界的癒着を作り出しているψ6〜*ψ6の空間構造的な意味合いである。(『人神/アドバンストエディション』p.407)
こうして今度はψ6(他者の身体からの空間の広がり)とψ*6(自己の身体からの空間の広がり)を同一化させるための回転がψ7の反映として起こってきます。その結果生まれてくるのが次元観察子ψ8だというわけです。ここでは詳しく書きませんが、これは物理学的に考えると時空座標の回転群に相当してきますから、特殊相対性理論に顔を出すローレンツ変換と呼ばれる変換の群の構造と同じものだと考えられます。その意味で言えば、ニュートンの絶対空間、絶対時間をベースにした古典力学からアインシュタインの相対論に始まる現代物理学への遷移は、事象分析に観測者が組み入れらていないかいるかの違いとも言えるでのかもしれません。現代物理学の骨格は相対論と量子論ですから、その流れから言えば、相対論においてまず人間の内面における観測者の役割が取り込まれ、次に量子論で人間の外面における観測者を取り込まなくてはいけない状況に入り込んできてしまったのでしょう。ヌーソロジーから言えば、この両者は次元観察子ψ8とψ7の空間領域を人間の意識が理性によって数学的に解析し始めたことと同意です。では、なぜ、そのような発展を物理学は辿ってきたのか………。OCOTに言わせれば、それ自体が「人間の最終構成」を行なわせるための準備活動だったということになります。冥王星の力です。——つづく







12月 2 2014
量子論は認識論を解体する
主体と客体が分離した認識では、認識は世界をつねに直線的に見る。というのも、無限遠点自体が主体の位置になっていることを、主体自身がまだ気づいていないからだ。直線の果てにあるものが何か分からない。この宇宙の果てには何があるのだろう。主体はそうやって、「無限」に想いを馳せるのだ。それが世界を見ている自分自身の位置であるということに気づくこともなく。。
こうして、当然のことながら、主体と客体が分離した世界では、空間も時間も直線的にイメージされることになる。古典物理学の記述様式はこうした認識に素直に従っている。物理学がいう「実在」とは、こうした直線的世界で捉えられる対象のことをいうのであり、それらはすべて計測可能、量的に実数化が可能なものとしてある。
しかし、20世紀になって、ミクロの世界からこうした記述様式には収まらない現象が現れてきた。それが量子の世界だ。まず、この量子の世界には直線がない。量子力学の世界はe^iθという複素平面上の円環によって支配された世界であり、そこに直線は存在していないのだ。物理学はこうした謎めいた円環から、彼らのいう「実在」としての物理量を引き出すために、円環を無理矢理、直線化させる手法を取らざるを得なかった。それが運動量やエネルギーの量子化という手法だ。運動量であれば、∂/∂x、エネルギーであれば∂/∂tを用いて、円環から接線を導出し、無理矢理、直線化させるのだ。
物理学はどうしても、こうした直線化された時間と空間の世界に、存在を見たがる。それが、物理学のいう「実在」なのだから、致し方ないことではあるのだが、直線の世界は、もともと円環の微分化によって出現してきたものだ。量子現象から見れば、物理現象の本質は円環の方にある。なのに、どうしても直線化しないと気が済まない。量子論が分かりにくくなっているのは、物理学が持ったこの実在に対する見誤りにある。
話を元に戻そう。世界を認識しているわたしたち人間の位置は時間と空間の中にはいない。確かに物質的身体は時間と空間の中にあるものだが、認識の当体である精神の位置は時間と空間の外部にある。それが「無限遠点」だ。主体の、この無限遠点への収まりによって、すべての直線は円環化される。そうすると、世界から3次元空間と1次元の時間は消え去る。そして、そこにe^iθという円環が現れてくる。つまり、量子の世界とは、主体が無限遠点として世界の中に入り込むことによって、主客未分離となった世界の数学的形式化になっているのだ。
神秘家や哲学者たちは、この主客未分離の世界について、幾多の言葉を使っていろいろと表現してきた。しかし、それらの言葉は言ってみれば、ムードの言葉であって、それを確かめる自然的根拠に欠けている。でも、いまや、わたしたちは量子論という自然学を手にしている。主客未分離の世界が具体的にどういう生態を持っているかを知りたければ、量子論が展開している素粒子の構造の内部へと、無限遠点を住処とした自らの命を持って侵入していけばいい。そこでは、思考するものと思考されるものの見事な一体化が起きている。理性がイデアに触れる現場がそこにはあるのだ。こうした思考は同時に、デカルトやカント以来、わたしたち人間を支配していた主体性の哲学、認識論を終焉へと導く。
認識論のこの終焉のもとに、世界を対象として眼差すような意識は静かに息を引き取っていくことだろう。認識は世界の根底に存在そのものとなって入り込み、「永遠」としての認識を開始し始めることになる。そのとき、「あるもの」は、すべて「なるもの」へとメタモルフォーゼを起こすのだ。
By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: 量子論