9月 6 2010
ヌースレクチャー2009〜2010の総括およびDVDのPR——VOL.1
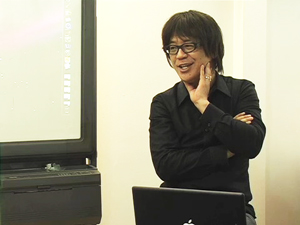
7年ぶりのレクチャーワークもひとまず無事、終了し、現在一息ついているところなのだが、今週から、全12回のDVDを反省会も兼ねて見直してみることにした。う〜ん、以前のレクチャーよりも多少は洗練されてきてはいるものの、まだまだヌーソロジーの可能性を十分に表現し切れていないという感じがするなぁ。。とりあえず、DVDのプロモーションも兼ねて一巻づつ簡単なレビューでも書いていってみることに。。。
●VOL.1――2012年問題について
久々のレクチャーシリーズの再開ということも手伝ってか、出足は若干緊張気味です(笑)。表情が硬いネ。お題の方も初っぱなからヌーソロジックな話は参加者にも酷だろうと勝手に判断し、ウォーミングアップとして「2012年問題」というカジュアルな話題でスタートさせた。
・DISC1 2012年問題について
前半はマヤ暦、ホピ族の神話、フォトンベルト、Ωボイント理論(テイヤール・ド・シャルダン)、タイムウェーブ・ゼロ理論(テレンス・マッケンナ)等、2012年問題と関連の深いタームのあらましをジャーナリスティックに解説し、2012年問題自体が孕む問題点についていろいろと語らせてもらった。
まぁ、前半の内容自体は、本来2012年問題なんてものはスピリチュアルマイノリティーが作り出したルサンチマンの産物にすぎない、というのが大筋なのだが、それはあくまでも僕の理性的な脳が話している内容であって、感性的な脳みその方は一概にはそうとも片付けられんぞと常に注意を促してきている。それは世の中の理性的なものが孕んでいる現状を見ればすぐに分かる。
今や世界はリベラルな民主主義の体制で全面覆われ、これといったイデオロギー対立もなくなってしまった。社会の中では価値中心は細かく分散化し、小さな物語、小さなコミュニティーがひしめき合い、そこでは冗長なおしゃべりだけが延々と続けられている。お固い言論の世界も例外じゃない。昔ながらの真や、善や、美を説く哲学や思想はすでに絶滅の危機に瀕していて、政治学や社会学といった近視眼的で実生活的な人文だけが、こちらのほうがより”アクチャル”だ、という理由だけで、ますます幅を利かせている。こうした主流に対し大きな物語の復活を声高に主張していくことがいかにカッコ悪いことであるかは重々承知してはいるつもりだが、自分の形(ナリ)としては、そんな時代だからこそ逆に反時代的に生きるトリックスターがおらんといかんやろ、と思えて仕方ないので、ヌーソロジーの構築に全身全霊を注いでいる。
と言って、僕自身はスピリチュアル業界で云々されている2012年問題にはほとんど関心がない。ヌーソロジーが問題としたいのはむしろ2012年以後の世界のことだ。2012年が例の1999年と同じようにまったりと何事もなく惰性で過ぎ去っていったとき、従来の理性たちから、スピリチュアリズムがますますお笑いネタにされるのは目に見えている。しかし、こうした社会的な理性が浴びせかけてくる嘲笑も愛を連呼するスピリチュアリズムと同じくらいに僕としては気持ちが悪い。両者を作動させている情念は結局のところ自我という同じコインの表裏にすぎない。僕が行きたいのはこの両者の間から垂上していくベクトルの方向。マテリアル(理性的)でもスピリチュアル(感性的)でもない、何か全く別の方向なのだ。
・DISC2 トランスフォーマーとは何か
後半はヌーソロジーの世界に入っていくための最初の立ち位置の説明をしたんだけど、その際、キータームとなっているのが「トランスフォーマー」というちょっと怪しげなタームだ。トランスフォーマーとは現行の世界観、宇宙観、人間観をその根底から転覆させるような、ニーチェで言うならばあらゆる価値の転換を図るようなメタ知性を所持する新人類たちの異名のことを指すのだけど、ヌーソロジーではこうしたニューブリードたちが2013年以降の世界に続々と登場してくると予測している(もちろんひとりよがりの予測なのは言うまでもない)。
人間とトランスフォーマーの思考様式における最も大きな違いは時間に対する考え方にあると感じている。西田幾多郎の言い方を借りれば、「歴史が自然を生成した」と考えるのが人間で、「自然が時間を生成した」としたと考えるのがトランスフォーマーだ。トランスフォーマーにおいては時間は決して絶対的な実在物ではなく、無意識が作り上げている一つの概念の形式にすぎない。トランスフォーマーというのはアプリオリな無意識の構造を意識化させる視力の獲得によって、この時間概念を成立させている基盤自体を解体させ、無時間という場所から宇宙の生成原理を構成していく知的作業に就く者たちのことをいう。
トランスフォーマーの認識にとっては時間概念自体が人間の存在様式に見えているので、時間概念を超越論的に乗り越えた主体意識はごく自然に人間を人間たらしめている概念枠から脱却していくことになるというストーリーだ。つまり、僕にとっての2012年で人類が滅亡するという言説は、人間という概念そのものが解体を始めますよという意味であり、当然のことながら、その解体は自然環境や社会システムといった外存世界における破局ではなく(もちろん多少のドタバタはあるだろうが)、あくまでも今までの内在野の在り方が全く別のものへと変えられていくということなのだろうと思ってる。。。DISC2では、まぁ、そんなことを2時間近くくっちゃべっています。
PR——レクチャーDVD.VOL.1に興味がある方はこちらへ→NOOS ACADEMEIA.shop







11月 22 2010
ドゥルーズのバトン
最近、ドゥルーズの本ばかり読んでいる。ドゥルーズに初めて触れたのは今から10年ちょっと前ぐらいだったか。丁度、ヌースアカデメイアのサイトを立ち上げた頃だった。友人でもある詩人の河村さんに、半田さんはドゥルーズを読むといいんじゃない、と言われ、最初に何気に手に取ったのが『アンチ・オイディプス』(ガタリとの共著)という本だった。今思い出しても強烈な体験だった。読み始めると同時に、それこそ頭蓋骨にハンマーが振り下ろされるような一撃を喰らった。なぜなら、それまで、OCOT情報と格闘しながら自らの拙い思考で整備していた無意識機械の構成部品の数々が、この書物を手にしたことによって、まるでマジンガーZの合体シーンのようにカシーン、カシーンと金属音を響かせながら一挙に脳内に組み上がってきたからだ。そうやって姿を表したのが現在ヌーソロジーの骨格として使用している「ケイブコンパス」というフィギレーションである。
『アンチ・オイディプス』が打ち出すビート感とドライブ感に一発で魅せられた僕は、その後、『千のプラトー』『差異と反復』『哲学とは何か』など、K書房新社から出ている高価な単行本を買い求めては、ドゥルーズが見ている内在野の風景が果たして、OCOT情報から僕が読み取ったもの(OCOT情報ではドゥルーズが概念化している内在面のことを「付帯質の内面」といったような言い方をする)と同じものなのかどうか、それを確かめたい一心で読み漁った。しかし、悲しいかな、ドゥルーズの本は、哲学の基礎教育を受けていない僕のような素人にはどれも皆、難解なものばかりだった。書物全体に散りばめられている語彙の出所は、哲学はもとより、神話、古代思想、神学、文学、絵画、音楽、映画etc…と広大な射程を持っていて、聞いたことのないような単語でベージが埋め尽くされていることも多々ある。西洋の人文科学史の全体を覆い尽くす知の全体からこぼれ出してくるその語彙群の夥しさは、まるでカマキリの孵化を見ているかのような強度で、時折、目眩を誘発させることもある。
まぁ、しかし、こうした語彙の難解さは知識の補強で済むことではある。実はドゥルーズの難解さの本質はそんなことではない。ドゥルーズは明晰さなどは微塵も追求してはいない。つまり、読者に自分の哲学を理解してもらおうなどとはこれっぽっちも思っていないということだ。このへんはOCOT情報に酷似していて面白い(笑)。つまりドゥルーズは哲学の先生でもなければ、哲学の評論家でもない。ただ生粋の哲学者だということだ。「哲学とは概念を創造することだ」というドゥルーズ自身の言葉にもある通り、ドゥルーズは概念のクリエーターであり未知の思考そのものを生きている人である。ここでドゥルーズがいう「創造」とは、〈表象=再現前化〉が支配する自我の同一性から解放された思考の所作を意味している。一般に思考というものが〈表象=再現前化〉のループの中で展開されるものである限り(実際、思考というものは事物の自己同一性が担保されていなければ成り立たない)、ドゥルーズのいう創造とは思考不可能なものを思考することの意となる。しかも、ドゥルーズは、自身の思考の中で次々と切り開かれてくる概念の蠢きをそのまま自分自身の「書く」という行為の中へと直裁的に反映させる表現者でもあった。つまり、彼が作り出す諸概念は「エクリチュール機械」の中に即座にインプットされ、その文法、構文、文体を通してすぐさま「表現されたもの」という事件として出現してくる――意味につかまらないこと、主語の同一性に捕縛され直線的になりがちな論説に絶えずクリナメン(ずれ)の一撃を与えること、同一の主題に常に変奏のリトルネロを与えること——そうやってドゥルーズの文体は常に神経症的な記述と分裂症的な記述の間を意図的に反復させながら、ロジカルに文脈を追おうとする読み手の理性の関節を脱臼させようとさせるのだ。
こんな化け物のような書き言葉の束を相手に、たった一つの動機で、ただどうしてもOCOT情報を読み解きたいというだけの動機で、僕なりの「差異と反復」が、OCOT情報とドゥルーズ哲学の間を巡って今もまだ執拗に続いているというわけだ。
哲学書というものは最低でも10年ぐらいかけて読むべきものなのだろう。ドゥルーズを知ってからというもの、自分の哲学的無知さ加減をいやというほど知らされ、その間にまがいなりにも、スピノザやカント,フッサール、ベルクソンやフロイトなどをつまみ読みした。その甲斐あってか、最近になってようやく、西洋の哲学が一体何を問題としてきたのか、その全体像というものが茫洋と見え始め、それがフィードバックされて、以前よりもさらに高い解像度でドゥルーズの思考の軌跡が追えるようになったように思える。あと、ヌーソロジーの側面から、ケイブコンパスがその内部に孕んでいる空間構造をかなり緻密に思い描けるようになったことも手伝っているのかもしれない。とにかく、ドゥルーズの言ってることの輪郭がひとりよがりではあれ、極めてクリアにつかめるようになってきた。それと並行して、OCOT情報の蓄積があるおかげだろうか、一方でドゥルーズには見えていない部分も見えるようになってきた。ドゥルーズが自分の思考を表現しようとして、その比喩が不十分である部分、また、読み手にどうしても誤読を誘ってしまっているような部分、そして、ドゥルーズ哲学に根本的に欠如している部分等。。。(特にハイデガーの存在論的差異にニーチェの永遠回帰を接合させた部分の論証が具体的に展開されている箇所が全く見当たらないのが個人的には物足りなく思っている)
ソーカル事件でドゥルーズを初めとするポストモダンの思想家たちが厳しく批判されたせいもあるのだろう。今の思想の世界では、もうドゥルーズは終わったなどと言う人もいる。ドゥルーズを21世紀に甦らせるためには、ドゥルーズを解説するのではなく、ドゥルーズに欠如した部分を補い、かつ、その完全化したドゥルーズを実証を持って証明することが必要だ。そのためにはまずは潜在性としてうごめいてきた哲学的な諸概念を実在性としての物理学的な概念へと接続させることが絶対条件である。僕が執拗に、哲学者たちが語っているアプリオリ(超越論的構成)とは素粒子構造のことなのだと言っているのもそのあがきのようなものである。そして、それはドゥルーズのライプニッツ論やイデア論からすれば全く持って正統な主張のように思える。そして、その〈差異化=微分化〉の思考自らがバロック的な「襞」となって、実在の中に〈異化~分化〉としての新しい物質的表現を持たなくてはならない(それが反物質となるか超対称性物質となるかはまだ分からない。新しい原子ともいうべきか。)。つまりは、ドゥルーズの生成論を現実としての生成へと転換しなくてはならないということだ。それによって、思考は〈思考する私ー自我〉という思考システムの同一性から離脱し、生成の内在面を駆け抜ける生ける強度となって新しい存在への道を切り開くのである。晴れてこの切り開きが起こった暁には、哲学は相転移を起こし、哲学自身を一つの宇宙的な創造行為へと変態させることだろう。そこではもう、思考と実在を区別する術はない。すべてはありてあるもの、つまり存在の一義性の中に融一し、世界から人間という体制は消え去っていく。元素界というトランスフォーマーの空間が顕現するのだ。
この一点のみにおいてヌーソロジーはドゥルーズのバトンをしっかりと受け継いでいる。この一点のみにおいて。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, 06_書籍・雑誌, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: アンチ・オイディプス, カント, ケイブコンパス, スピノザ, ドゥルーズ, ニーチェ, ハイデガー, フロイト, ベルクソン, ライプニッツ, 付帯質, 差異と反復, 河村悟, 素粒子