2月 28 2018
ヌーソロジーの弁明—簡明なものを底支えするために
ヌーソロジーはOCOT情報というチャネリング情報をベースに構築中の現在進行形のコスモロジーだ。スタイルとしてはグノーシス的なのだが、神秘主義的観想というよりも、幾何学的瞑想を通した空間認識の変革というメソッドを採っている。「トランスフォーマー型ゲシュタルト」と呼ぶものだ。
この幾何学はいわゆるイデア(精神の形相)に相当するものだが、ただ、この幾何学が正しいものかどうかという保証はどこにもない。そこで、とりあえず、その正当性を確認するための作業が必要となる。
イデアなのだから、それは物質や意識の発生論的境位に深く関わってないといけない。果たしてOCOT情報が伝えてきた幾何学的布置が本当にイデア足りえるかという吟味、裏取りが必要なわけだ。厄介なことに、このような発生論的分野を語っている信頼できる筋は物質なら現代物理学、意識については哲学しかジャンルがない(伝統的宗教やオカルティズムは、それこそ人間の体制によって大きく捻じ曲げられているように感じる)。
そこで致し方なく、その説明はシリウス言語、物理学用語、哲学用語という、ジャーゴン(難解な専門用語)のトリニティで埋め尽くされてしまうことになる。望んでやっているわけじゃないのだが、他に材料が見つからないのだから致し方ない。
今は、そうした七面倒くさい裏取りをやっている段階なので、複雑で難解に見えるかもしれないが、裏が取れれば、物理学と哲学の言葉はおそらく不要になるのではないかと思っている。というのも、シリウス言語自体、その両者が融合したような新種の概念で網羅されているので、その概念の工事が終了しさえすれば、そういった重たい道具類は不要になるのではないかと考えているからだ。ヌーソロジーが幻視する新時代にとっては、精神=物質なのだから、まぁ、これは当然の話ではあるのだが。
ただ、裏取りに哲学と物理学が必要になると言っても、その道の専門家からすれば、おそらく、ごく基本的な内容に止まっている。そんなに深く足を突っ込む必要もないだろう。哲学にしろ、物理学にしろ、それを本格的にマスターしようと思ったら、それこそ一生を要するような学問だから、そこに固執していては本流から逸脱してしまう。ヌーソロジーが吟味のために採用しているのは、ドゥルーズの哲学と量子論~素粒子物理のそれぞれ初歩的な部分のみだ。
ドゥルーズに触れて約15年ほど経つが、ドゥルーズの哲学には過去の反体制の哲学の集大成のようなところがある。僕なりに言わせてもらえば、その情動はニーチェであり、その倫理はスピノザであり、その論理はベルクソンであり、その美学はライプニッツである。といったところか。デカルト-カント-ヘーゲルといった体制派の哲学者たちをドゥルーズは常に対岸に見ている。
ニーチェからは永遠回帰(能動的ニヒリズム)、スピノザからは永遠の相(第三の認識)、ベルクソンからは純粋持続(生命的跳躍)、ライプニッツからはモナド(逆モナド)というキーワードをそれぞれ引き出すことができるだろう。ドゥルーズの頭の中ではこれらはすべて美しく繋がっている。
ドゥルーズは「差異」という概念を執拗に訴えるが、要は、新しい時空間の創設を呼びかけているのだ。人間が受動的ニヒリズムの中で自動機械のようにして生きるのではなく、能動的ニヒリズムを持ってアナーキーな存在へと変身できるような場所。そのような解放区(ノマド)を作り出すこと。ドゥルーズにとってそれは理念的空間への侵入を意味している。ドゥルーズ哲学の別名でもある「超越論的経験論(超越論的なものを経験の範疇へと取り込んでいくこと)」というのも、その侵入の意味だと考えていい。
ここで言われている超越論的なものというのは、人間の意識経験のすべてを可能にするためにウラで働く無意識のようなものだ。その無意識の自動機械のような営みの中で、人間は「人間」という体制を余儀なくされ、イメージと言語の生産に躍起となっている。その生産の反復は資本主義機械が紡ぎだす脱領土化/再領土化の中で消費され、その延々と繰り返されるクリシェは、今や大地さえをも回復不可能な状態へと追い込んでいる。
誰もが飽き飽きしているにもかかわらず、それ以外に欲望の持って行き所が分からない。この悪夢のような自動機械(無意識の欲望機械)から逃れる手段はただ一つ——この機械の回路を裏返し、経験不可能とされるこの超越論的なものを経験可能なものにするしかない。ドゥルーズの哲学が「反転の哲学」と呼ばれる所以もここにある。すべてを裏返すこと。ヌーソロジーはここにOCOT情報とドゥルーズ哲学の完全な一致を見ているわけだ。
資本主義機械のチューンを狂わせるためには、まずは、すべてを裏返して見ることのできる知覚を作り出さなくてはいけない。この知覚器官はたぶん思考以外にないだろう。感性の反動として生まれている思考でなく、感性そのものを能動的なものへと変えるような思考。思考がこのように能動化することによって、マクロはミクロへと反転可能となり、主体は客体へと反転し、わたしはあなたへと反転し、死は生へと反転する。そういう世界が、この人間の意識世界を支える裏世界として厳然と存在しているわけだ。ヌーソロジーでいう「ヒト」というのがその裏世界に当たる(ドゥルーズもその世界の住人のことを「ひと(on)」と呼んでいる)。
ヌーソロジーはその来るべき新世界の地図作成に臨んでいると思ってほしい。要は物質を精神へと裏返す作業をすでにマイノリティー(民衆)(ドゥルーズにとって「民衆」とは、やがてやってくる「ひと(on)」のことを指す)として開始しているということ。まだまだ、遠い先のことかもしれないが、今の文明は必ずこの方向へと抜けていく。それを文明と呼んで良ければの話だが。

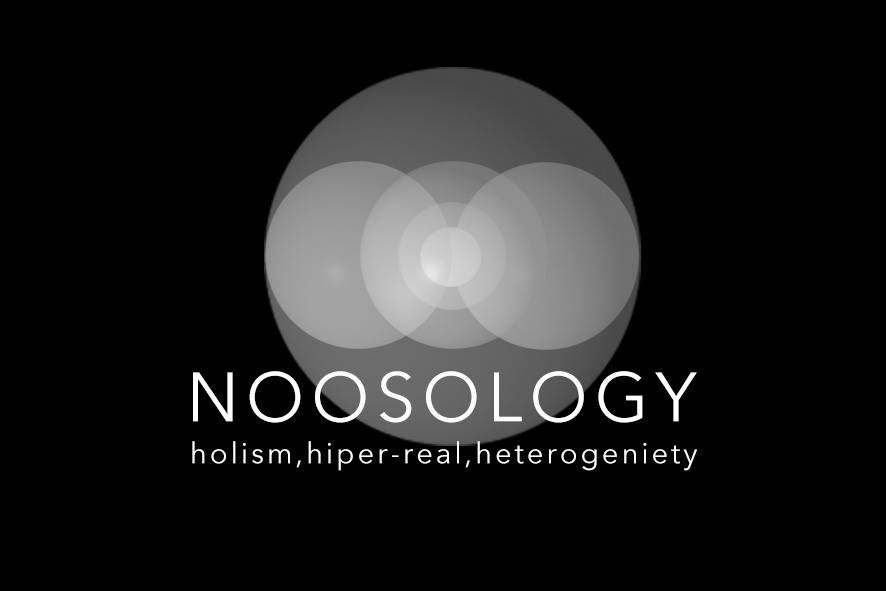






3月 12 2018
ドゥルーズ=ガタリは哲学における高次元思想のようなもの
ヌーソロジーに登場するケイブコンパスのモデルは、ゼロ年代に入ってドゥルーズ=ガタリの『アンチオイディプス』と出会ったときに、それこそ雷鳴の轟きのようにして一気に下りてきたものだった(笑)。それからというもの、僕の中ではOCOT情報とドゥルーズ=ガタリの思想はほとんど同じものに見えている(下図参考)。
ドゥルーズ=ガタリにはもう一冊『千のプラトー』という傑作がある。『アンチオイディプス』がヌーソロジーでいう次元観察子(人間の無意識の欲望機械)の内実についての本だとするなら、この『千のプラトー』の方は大系観察子(器官なき身体)の形成についての本のようにも読める。とにかく凄まじい破壊力を持った鉄槌のような本だ(下写真)。
この『千のプラトー』を読んで、「すべてが知覚の問題である」と語るOCOT情報に深く合点がいった。つまりは、時系列的に秩序立てられていない無時間の領域から大地(自然)の成り立ちをイメージする必要があるということ。そして、そのためには、空間の理念的質料の基礎がどのように構成されているのかを知る必要がある。でもって、その場所は素粒子構造以外にない——というのが、目下、ヌーソロジーが出している結論である。
地層化の反動として蠢いている霊的思考の欲動を、いかにして、この理念的質料の方向と接続させるか——その作業が、ほんと難しい。
時空は物質をミクロからマクロにわたる地層として構造化する。素粒子→原子→分子→DNA→細胞→植物→動物→大地→地球→太陽系→銀河系etcといった具合に。しかし、これらはあくまでも、時系列的な分配によって表現された上っ面の構造に過ぎない。人間はこの構造に沿って、滑るように知覚し、撫でるようにしか思考できない。いわゆる対象化の思考だ。
思考されるべきは、その分配の原理の方である。そこに精神本来の運動がある。精神は常に一義的なものであり、精神の中で時間的距離や地層的な乖離が意味を為すことはない。つまり、そこでは分子の化学反応と人間の言語活動は重なり合い、DNAを通して諸惑星が周回し、鉱物の中で思考の情念が結晶化する——そんな描写が可能となる世界なのだ。
無論、地層化に慣れ親しんだ意識からは、このような知覚は狂気にしか映らないだろう。しかし、この一義的な運動を全うな正気と見なせるような高次知覚のプログラムが存在している。そのプログラムのBASIC言語となっているのが、素粒子が持ったトポロジーシステムであり、それが同時に分配原理とリンクしているのだ。
ゼロ年代に入って、ほとんど忘れられつつあるドゥルーズ=ガタリの思想だが、素粒子がわたしたちの精神の母胎として見えてきた暁には、彼らが描かんとした内在平面の風景がよりコントラストを持った色彩の中に見えてくるのではないかと思ってる。
※下のケイブコンパス図、「資本主義機械のラットホイール」に訂正。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: OCOT情報, ドゥルーズ, 大系観察子, 素粒子