11月 22 2010
ドゥルーズのバトン
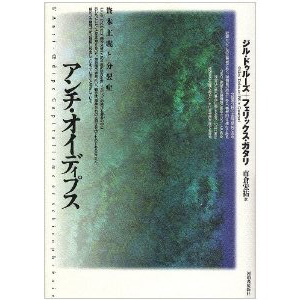
最近、ドゥルーズの本ばかり読んでいる。ドゥルーズに初めて触れたのは今から10年ちょっと前ぐらいだったか。丁度、ヌースアカデメイアのサイトを立ち上げた頃だった。友人でもある詩人の河村さんに、半田さんはドゥルーズを読むといいんじゃない、と言われ、最初に何気に手に取ったのが『アンチ・オイディプス』(ガタリとの共著)という本だった。今思い出しても強烈な体験だった。読み始めると同時に、それこそ頭蓋骨にハンマーが振り下ろされるような一撃を喰らった。なぜなら、それまで、OCOT情報と格闘しながら自らの拙い思考で整備していた無意識機械の構成部品の数々が、この書物を手にしたことによって、まるでマジンガーZの合体シーンのようにカシーン、カシーンと金属音を響かせながら一挙に脳内に組み上がってきたからだ。そうやって姿を表したのが現在ヌーソロジーの骨格として使用している「ケイブコンパス」というフィギレーションである。
『アンチ・オイディプス』が打ち出すビート感とドライブ感に一発で魅せられた僕は、その後、『千のプラトー』『差異と反復』『哲学とは何か』など、K書房新社から出ている高価な単行本を買い求めては、ドゥルーズが見ている内在野の風景が果たして、OCOT情報から僕が読み取ったもの(OCOT情報ではドゥルーズが概念化している内在面のことを「付帯質の内面」といったような言い方をする)と同じものなのかどうか、それを確かめたい一心で読み漁った。しかし、悲しいかな、ドゥルーズの本は、哲学の基礎教育を受けていない僕のような素人にはどれも皆、難解なものばかりだった。書物全体に散りばめられている語彙の出所は、哲学はもとより、神話、古代思想、神学、文学、絵画、音楽、映画etc…と広大な射程を持っていて、聞いたことのないような単語でベージが埋め尽くされていることも多々ある。西洋の人文科学史の全体を覆い尽くす知の全体からこぼれ出してくるその語彙群の夥しさは、まるでカマキリの孵化を見ているかのような強度で、時折、目眩を誘発させることもある。
まぁ、しかし、こうした語彙の難解さは知識の補強で済むことではある。実はドゥルーズの難解さの本質はそんなことではない。ドゥルーズは明晰さなどは微塵も追求してはいない。つまり、読者に自分の哲学を理解してもらおうなどとはこれっぽっちも思っていないということだ。このへんはOCOT情報に酷似していて面白い(笑)。つまりドゥルーズは哲学の先生でもなければ、哲学の評論家でもない。ただ生粋の哲学者だということだ。「哲学とは概念を創造することだ」というドゥルーズ自身の言葉にもある通り、ドゥルーズは概念のクリエーターであり未知の思考そのものを生きている人である。ここでドゥルーズがいう「創造」とは、〈表象=再現前化〉が支配する自我の同一性から解放された思考の所作を意味している。一般に思考というものが〈表象=再現前化〉のループの中で展開されるものである限り(実際、思考というものは事物の自己同一性が担保されていなければ成り立たない)、ドゥルーズのいう創造とは思考不可能なものを思考することの意となる。しかも、ドゥルーズは、自身の思考の中で次々と切り開かれてくる概念の蠢きをそのまま自分自身の「書く」という行為の中へと直裁的に反映させる表現者でもあった。つまり、彼が作り出す諸概念は「エクリチュール機械」の中に即座にインプットされ、その文法、構文、文体を通してすぐさま「表現されたもの」という事件として出現してくる――意味につかまらないこと、主語の同一性に捕縛され直線的になりがちな論説に絶えずクリナメン(ずれ)の一撃を与えること、同一の主題に常に変奏のリトルネロを与えること——そうやってドゥルーズの文体は常に神経症的な記述と分裂症的な記述の間を意図的に反復させながら、ロジカルに文脈を追おうとする読み手の理性の関節を脱臼させようとさせるのだ。
こんな化け物のような書き言葉の束を相手に、たった一つの動機で、ただどうしてもOCOT情報を読み解きたいというだけの動機で、僕なりの「差異と反復」が、OCOT情報とドゥルーズ哲学の間を巡って今もまだ執拗に続いているというわけだ。
哲学書というものは最低でも10年ぐらいかけて読むべきものなのだろう。ドゥルーズを知ってからというもの、自分の哲学的無知さ加減をいやというほど知らされ、その間にまがいなりにも、スピノザやカント,フッサール、ベルクソンやフロイトなどをつまみ読みした。その甲斐あってか、最近になってようやく、西洋の哲学が一体何を問題としてきたのか、その全体像というものが茫洋と見え始め、それがフィードバックされて、以前よりもさらに高い解像度でドゥルーズの思考の軌跡が追えるようになったように思える。あと、ヌーソロジーの側面から、ケイブコンパスがその内部に孕んでいる空間構造をかなり緻密に思い描けるようになったことも手伝っているのかもしれない。とにかく、ドゥルーズの言ってることの輪郭がひとりよがりではあれ、極めてクリアにつかめるようになってきた。それと並行して、OCOT情報の蓄積があるおかげだろうか、一方でドゥルーズには見えていない部分も見えるようになってきた。ドゥルーズが自分の思考を表現しようとして、その比喩が不十分である部分、また、読み手にどうしても誤読を誘ってしまっているような部分、そして、ドゥルーズ哲学に根本的に欠如している部分等。。。(特にハイデガーの存在論的差異にニーチェの永遠回帰を接合させた部分の論証が具体的に展開されている箇所が全く見当たらないのが個人的には物足りなく思っている)
ソーカル事件でドゥルーズを初めとするポストモダンの思想家たちが厳しく批判されたせいもあるのだろう。今の思想の世界では、もうドゥルーズは終わったなどと言う人もいる。ドゥルーズを21世紀に甦らせるためには、ドゥルーズを解説するのではなく、ドゥルーズに欠如した部分を補い、かつ、その完全化したドゥルーズを実証を持って証明することが必要だ。そのためにはまずは潜在性としてうごめいてきた哲学的な諸概念を実在性としての物理学的な概念へと接続させることが絶対条件である。僕が執拗に、哲学者たちが語っているアプリオリ(超越論的構成)とは素粒子構造のことなのだと言っているのもそのあがきのようなものである。そして、それはドゥルーズのライプニッツ論やイデア論からすれば全く持って正統な主張のように思える。そして、その〈差異化=微分化〉の思考自らがバロック的な「襞」となって、実在の中に〈異化~分化〉としての新しい物質的表現を持たなくてはならない(それが反物質となるか超対称性物質となるかはまだ分からない。新しい原子ともいうべきか。)。つまりは、ドゥルーズの生成論を現実としての生成へと転換しなくてはならないということだ。それによって、思考は〈思考する私ー自我〉という思考システムの同一性から離脱し、生成の内在面を駆け抜ける生ける強度となって新しい存在への道を切り開くのである。晴れてこの切り開きが起こった暁には、哲学は相転移を起こし、哲学自身を一つの宇宙的な創造行為へと変態させることだろう。そこではもう、思考と実在を区別する術はない。すべてはありてあるもの、つまり存在の一義性の中に融一し、世界から人間という体制は消え去っていく。元素界というトランスフォーマーの空間が顕現するのだ。
この一点のみにおいてヌーソロジーはドゥルーズのバトンをしっかりと受け継いでいる。この一点のみにおいて。







1月 28 2011
『ドゥルーズと創造の哲学』
『ドゥルーズと創造の哲学』
久々に衝撃的な本に出会った。全体で400ページを超える著作なのだが、最初から最後まで、それこそページをめくるごとにヘビー級並みのパンチを喰らい続け、完全に持っていかれてしまった。今でもまだ足下がふらついている。こんな衝撃は『アンチ・オイディプス』以来10年ぶりのことだ。一体何がそんなに衝撃的だったのか――一言でいえば、僕が常日頃感じとっていたヌーソロジーとドゥルーズ哲学に共通して流れる通奏低音をこれでもかというほど綿密かつ精緻に言語化してくれたこと。これに尽きる。
ドゥルーズ哲学はガタリとのコラボによって紡がれた語彙群(器官なき身体、リゾーム、アレンジメント、脱-領土化、内在平面等)が持ったそのPOPな口当たりの良さも手伝って、ボストモダンの思想家たちに様々な文化境界を横断する思考のツールとして使われてきた。ドゥルーズ自身も後期は自らのイマージュ論をもとに絵画や映画などの作品分析をやっているので、文化批評にドゥルーズを参照することはそれなりに有意義な作業であるとは思う。だけど、僕はこういったポストモダンの識者たちのドゥルーズ論に正直あまりピンとこなかった。というのも、この手の議論はドゥルーズ哲学のごく表層的な水準にすぎず、ドゥルーズ哲学がその根底に持った深い射程を何一つ理解していない作業のように思えていたからだ。
ドゥルーズが哲学史家として追い続けたメンツ(ヒューム、ニーチェ、ベルクソン、スピノザ、ライプニッツ等)を見れば分かるように、ドゥルーズはある一定の照準を持って確信犯的に一つの原理的な水準を保ちながら思考しているように僕には思える。その原理的水準はドゥルーズの圧倒的な知識量とその晦渋かつ華麗な言い回しによって見えにくくはなってはいるものの、僕にとっては古代より綿々と受け継がれてきたグノーシス的知以外の何ものでもない。もちろん、多くの研究者たちはそのことを百も承知しているのかもしれない。しかし、ドゥルーズ哲学が今の社会で学問として成立するためにはそこに触れるのはタブーなのだろう。そうしたグノーシス者ドゥルーズの横顔はつねに隠蔽され続け、浅薄な化粧を施されたドゥルーズだけが、単なる知的なファッションとして現実的世界(表象-再現前化)の水準の中で議論され続けてきた。しかし、ホルワードはこの本でドゥルーズ哲学が持ったまさにグノーシス(霊知)としての本性をいとも鮮やかに暴露している。それもその方向性を徹底的に肯定する意味において。何とスキャンダラスな本であることか。この本は、その意味で、まさに従来のドゥルーズ研究者たち、いや既存の哲学の在り方全体への宣戦布告と言ってもいいような内容なのである。幾つか引用してみよう。
「ドゥルーズの作品群において真に問われていることは、ある種の増進された被造物的な可動性や、現働的相互作用のより柔軟で稔りある諸様態を可能にする一連の技法ではない。そうではなく、問題は、あらゆる個別の被造物がみずからの溶解にその方向性を再転換することを、贖いとして履行することである。自然や歴史または世界の哲学者、あらゆる意味での「肉の唯物論者」であるよりはむしろ、ドゥルーズは精神(霊)的な、贖いの、あるいは減算の思想家、脱-身(物)体化と脱-物質化の機構に取り憑かれた思想家として読むことが最もふさわしい。ドゥルーズ哲学を導くのは、この世界の外へと導いていく無数の逃走線である。ただしそれはこの世以外の別の世界へと導いていく線ではなく、脱-世界の線である。」(P.15)
「現働的なものの反転において、またそれを通してこそ、われわれは潜在的なもの、強度化され、変形され、救済または転回された潜在的なもの、その十全に創造的なポテンシャルを復活させた潜在的なものへと回帰する。」(P.148)
これらたった二つの引用からも分かるように、ホルワードは存在そのものの反転を企図したドゥルーズの思考の核心を見事に言い当てている。ヌーソロジーもまた同じ射程を持つ反転の形而上学であり、この「反転」という鍵概念のもとに人間という存在を律動させている宇宙的運動の機構をその根底から引っくり返すことを目標にしている。OCOT情報が伝えてきた人間型ゲシュタルトから変換人型ゲシュタルトへという指標はまさにドゥルーズ哲学が訴えてきた一連の哲学的思弁をそのまま知覚-表象可能なものとして再構築していくことを意味しているのだ。ドゥルーズ哲学において知覚不可能なもの、表象化不可能なものとされた理念の構造を新しい知覚形式、思考形式のもとに、超感覚的知覚、超感覚的表象として空間に表現していくこと。これがヌーソロジーにとっての創造行為であり、ここにドゥルーズ哲学と共鳴する通奏低音がけたたましく鳴り響いている。
レクチャーに何度出てもヌーソロジーが一体何をやりたいのか分からないと訝しがる人たちがいる。そういう人は是非、この本を読んで欲しい。哲学的な知識がある程度ないとちょっと読みづらい本であることは確かだが、ヌーソロジーがいわゆるニューエイジ的な自分探しの旅や、さらには政治的、社会的な出来事にほとんどコミットしない理由を少しは理解していただけるかもしれない。あとヘルメス知やカバラ、シュタイナーなど神秘学系の知識に精通している人にもオススメだ。一般に神秘学系の人は哲学を言語に偏りすぎた頭でっかちの学問として毛嫌いする傾向があるが、感覚的なものと思考的なものの一致がない限りヘルマフロディートスの生成は現実のものとはならないとする錬金術の戒めを善しとするならば、超越論的に神秘学的知を再構成していくことは、真のオカルティストとしては必要不可欠な作業ではないかと思う。是非とも、この本をきっかけに思考を最重要視するドゥルーズという哲学者の霊知へのアプローチの仕方を知って欲しい。
ヌーソロジーを長年追いかけている人には、この本に頻繁に登場するドゥルーズ哲学を支える〈現働化-潜在化〉という二つの柱を下に挙げたようなヌース用語の対応で読むといい。おそらくホルワードが解読したドゥルーズ像をヌーソロジーの思考を媒介としてスラスラと理解できるし、また、真のグノーシス者、真のキリスト者としてのドゥルーズに出会えるのではないかと思う。
現動化――反定質(人間の意識の内面——偶数系先手の次元観察子の発展)
潜在化――反性質(人間の意識の外面——奇数系後手の次元観察子の発展)
現動的なものの反転――顕在化、または定質の発振(奇数系先手の次元観察子の発展)
ドゥルーズ哲学の先に見えてくるもの。これを巡ってこれからのヌーソロジーは展開していくことになる。ありがとうホルワードさん(泣)。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, 06_書籍・雑誌, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: アンチ・オイディプス, イマージュ, カバラ, グノーシス, スピノザ, ドゥルーズ, ニーチェ, ヌース用語, ヒューム, ベルクソン, 人間型ゲシュタルト, 次元観察子, 神秘学